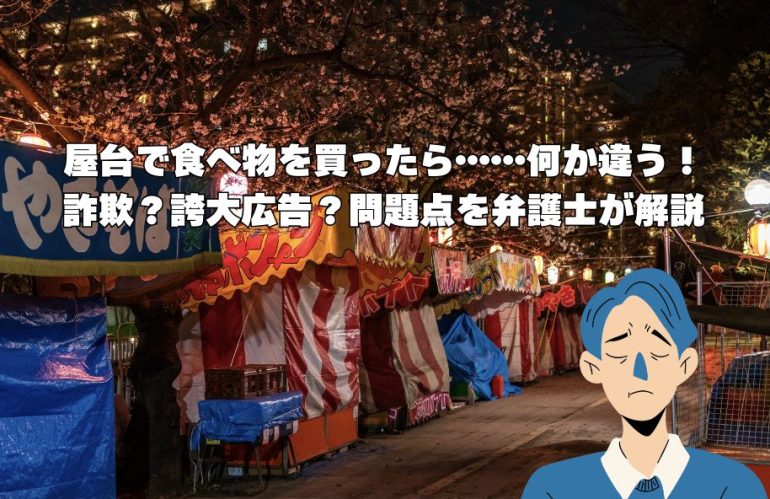
「牛タン」の看板を掲げているにもかかわらず、実際に買ってみたら「豚タン」だったという事例がSNSで話題になりました。
屋台販売を行う事業者の一部は、上記事例のように、実際に提供している商品の質を偽るケースがあるようです。当然ながら、こうした行為は法律上も大いに問題があります。
1. 商品に関するウソの表示は「不正競争防止法違反」
不正競争防止法では、商品の品質などについて誤認させるような表示をすることや、その表示をした商品を譲渡することなどを禁止しています(同法2条1項20号)。
「牛タン」と称して豚タンを販売するなど、商品の品質を偽るような行為は不正競争防止法違反に当たります。違反者は「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金」に処され、または拘禁刑と罰金が併科されます(同法21条3項)。
さらに、法人の代表者や従業員などが上記の違反をした場合は、法人にも「3億円以下の罰金が科されます(同法22条1項3号)。
2. 実際よりも良い商品と勘違いさせる表示は「景品表示法違反」
景品表示法では、以下のいずれかの表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものを禁止しています。
・実際の商品よりも著しく優良であると示す表示
・事実に反して競合他社の商品よりも優良であると示す表示
上記の表示は「優良誤認表示」と呼ばれています。実際には豚タンを販売しているのに、「牛タン」であるという表示をした場合には、優良誤認表示に当たると考えられます。
優良誤認表示をした事業者は、消費者庁長官による措置命令や課徴金納付命令、刑事罰の対象となります。
3. 購入者を騙してお金を払わせたら「詐欺罪」
相手方を騙して金銭を交付させた場合は「詐欺罪」が成立し、「10年以下の拘禁刑」に処されます(刑法246条1項)。
客に対して「牛タンである」と伝え、「牛タンを買える」と勘違いした状態の客にお金を払わせ、実際には豚タンを渡した場合は詐欺罪が成立します。
4. 店名に「牛タン」と掲げつつ、豚タンを販売するのは問題ない?
これまで解説したように、「牛タン」と称して豚タンを販売すると不正競争防止法違反・景品表示法違反・詐欺罪に該当する可能性があります。
「牛タンは店名であって、商品名ではないからOK」という抜け道を主張する投稿が散見されましたが、このような主張は必ずしも正しくないと思われます。
不正競争防止法違反・景品表示法違反・詐欺罪などの成否は、「客は普通どのように受け取るか」という観点で判断されるためです。
「牛タン」を店名に掲げつつ豚タンを販売することが、直ちにダメというわけではありません。販売の際に「豚タン」だと、客が明確に分かる形で伝えれば問題ないのです。
たとえば、メニュー表に牛タンと豚タンを両方並べ、それぞれ価格を明記しておけば大丈夫でしょう。
一方、店名に「牛タン」が入っていて、販売している商品は1種類のみで、店名以外に商品の説明がない場合はどうでしょうか。
この場合、客は販売されている商品が牛タンであると理解するのが普通です。それにもかかわらず、販売しているのが豚タンである場合は、違法と判断される可能性が高いと思われます。
5. 屋台販売での違法行為は摘発できる?
屋台販売において違法行為がなされていても、常設の店舗に比べると、警察が摘発することは困難と思われます。屋台は短期間限定で営業しているものが大半で、違法行為の証拠が残りにくいためです。
しかし、近年ではスマートフォンやSNSが普及し、屋台での違法行為も発覚しやすい環境になってきました。警察のリソースは限られているものの、一般消費者を保護するため、できる限りアンテナを張って違法屋台の取り締まりを強化してほしいものです。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













