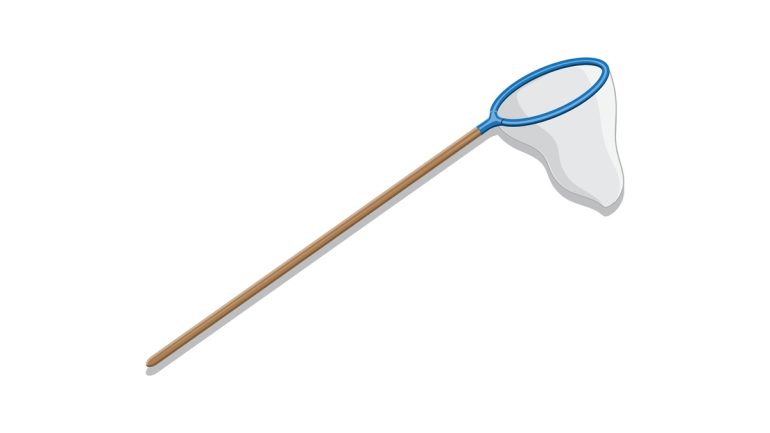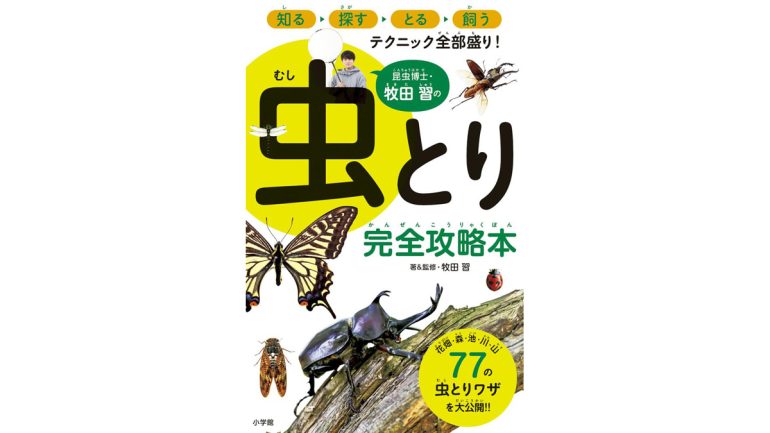夏、外を歩いているとセミの声を耳にすることがよくあると思います。とはいえ、一言にセミと言っても、種類によって鳴き声は異なるのはもちろん、活発に鳴く時間が異なるなど、それぞれの種類が個性豊かな生態を持っています。それらを踏まえて、今回は身近なセミたちの採集方法について解説します。
身近にいるセミたち
現在、日本では35種ほどのセミが知られており、季節や地域によっても見ることのできるセミは異なります。ここでは、東京や大阪などの都市部の近くでも見ることのできる身近なセミ6種類を紹介します。以下、それぞれのセミの鳴き声を紹介していますが、鳴くのはオスのみです。
(1) アブラゼミ
「ジージー」と鳴く5~6cm程のセミで、北海道から九州まで広く分布しており、日本で最も普通に見られる種類。様々な木でよく見られますが、サクラやケヤキの木では見かけることがとても多いです。
(2) ミンミンゼミ
「ミーンミーン」と鳴く5.5~6.5cm程の大きさのセミです。北海道南部から九州まで広く分布していますが、東日本では平地にも多いのに対して、西日本では平地では少なく、主に山地に生息。アブラゼミ同様、サクラやケヤキの木でよく見つかります。
(3) クマゼミ
「シャーシャー」と鳴く6~7cm程の大型のセミです。以前は南日本や西日本を中心に分布していましたが、最近は関東地方でも数が増えてきています。サクラやケヤキに加え、センダンの木などでもよく見かけます。
(4) ニイニイゼミ
「チィー」と鳴く3~4cm程の小型のセミで、北海道から沖縄本島まで分布しています。サクラやケヤキに加え、マツやモミなどの木でも見かけることが多い種類です。
(5) ツクツクボウシ
「ツクツクボーシ」と鳴く4~4.5cm程のセミです。北海道から九州まで分布しており、夏の終わりに数が増えることから、夏の終わりを告げるセミとも言われています。あらゆる種類の木にやってきます。
(6) ヒグラシ
「カナカナカナ」と鳴く4.5~5cm程の大きさのセミで、北海道から九州まで分布しており、薄暗い場所で見つかることが多いです。スギやヒノキなどの木をよく好みます。
種類によって活動する時間が異なる!?
セミは時間によって鳴く種類が異なり、狙う種類が活発に鳴く時間に出かけるのがポイントです。ここでは、早朝、午前中、午後、夕方の4つの時間に分けてそれぞれの時間に活発に鳴くセミについて紹介します。
(1) 早朝(4~8時頃)
先程紹介したセミのうち、ミンミンゼミを除く種類が鳴き出す時間帯です。中でもヒグラシは4~5時頃に鳴くため、早朝に捕まえるにはかなり早起きする必要があります。
(2) 午前中(8~12時頃)
クマゼミ、ツクツクボウシ、ニイニイゼミは早朝から引き続き鳴いていますが、アブラゼミやヒグラシは一旦静かになってしまいます。ミンミンゼミはこの時間から鳴き始めます。
(3) 午後(12~16時頃)
午後になると、クマゼミは落ち着いてしまいますが、アブラゼミは再び鳴き始め、ツクツクボウシやニイニイゼミも引き続き鳴いています。ミンミンゼミは15時頃までよく鳴いています。
(4) 夕方(16~19時頃)
ミンミンゼミは鳴き止んでしまいますが、クマゼミやヒグラシは鳴き始めます。アブラゼミ、ツクツクボウシ、ニイニイゼミも引き続きよく鳴いています。一日のうちで最もセミ採集に適した時間帯とい言えるでしょう。
セミを見つけることができたら、どうやって捕まえる?
ここまで、それぞれのセミの生態や好む時間について解説してきましたが、実際にセミを見つけた際にはどのように捕まえるのがいいでしょうか?まず、セミの採集に適した網について紹介します。セミを捕まえる網はとにかく柄の長さがあるものをおすすめします。木の高い場所に止まっていることも多いので、5m以上伸びるものがいいです。次に重要なのが、網の部分の大きさです。網は大きければ大きいほどいいと思われがちですが、セミ採集においては網が大きすぎると、幹や枝の間を上手くくぐり抜けれなかったりすることもあるため、小さめの網をおすすめします。
網の準備ができたら、セミをめがけてそっと網を近づけていきましょう。セミは網を被せると上方向に飛ぼうとします。そのため、網を下からではなく、上から覆いかぶせるようにしましょう。
網の中にセミが入ったら、網の奥の部分からセミが逃げないように網を折って、手元まで網を戻しましょう。セミを持つ時は横から羽のつけ根をはさむように指で持つのがポイントです。
セミの成虫は飼育するのが難しいです。捕まえたら、その場で逃がしてあげることをおすすめしますが、持ち帰ってよく観察してみると、野外で追いかけているだけでは分かりづらい世界も見えてくると思います。
昆虫ハンター・牧田習
博士(農学)。1996年、兵庫県宝塚市出身。2020年に北海道大学理学部を卒業。同年、東京大学大学院農学生命科学研究科に入学し、2025年3月に同大学院博士課程を修了。昆虫採集のために14ヵ国を訪れ、9種の新種を発見している。「ダーウィンが来た!」(NHK)「アナザースカイ」(NTV)などに出演。現在は「趣味の園芸 やさいの時間 里山菜園 有機のチカラ」(NHK)、「猫のひたいほどワイド」(テレビ神奈川)にレギュラー出演中。昆虫をテーマにしたイベントにも多数出演している。
『昆虫博士・牧田習の虫とり完全攻略本』
【Amazonで買う】
【楽天ブックスで買う】
著書:「昆虫博士・牧田習の虫とり完全攻略本」(小学館)、「昆虫ハンター・牧田習のオドロキ!!昆虫雑学99」(KADOKAWA)、「昆虫ハンター・牧田習と親子で見つけるにほんの昆虫たち」(日東書院本社)、「春夏秋冬いつでも楽しめる昆虫探し」(PARCO出版)好評発売中。Instagram・Xともに@shu1014my
文/牧田 習















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE