
人生100年時代。年齢を重ねることは、経験と知恵が深まる素晴らしい旅です。でも、一方で記憶力や集中力の低下に不安を感じることがあるかもしれません。
そんな中、脳科学者・西剛志氏が提案するのは、「脳の若さ」を保つためのシンプルな習慣。実際に、80歳を過ぎても好奇心を持ち続け、学びを楽しむ人たちが実践していることとは?
この記事では、書籍『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』から、脳を元気に保つヒントを抜粋・再編集してわかりやすくご紹介します。
年齢に関係なく、今から始められる「脳のメンテナンス」を一緒に学びましょう。
「なんとかなるさ」と「石橋をたたいて渡る」は、どちらも不正解
たとえば、こんな視点の差は、コミュニケーションがうまくいく人といかない人の違いです。
もう昔のことかもしれませんが、あなたの学生時代を思い出してください。長い夏休みも後半に差し掛かったとき。
「あ~、もう少しで夏休みが終わってしまう。もっと夏休みが長ければいいのになあ~」
と思うか、
「ここまでたくさん楽しんできたし、まだ残りの夏休みもあるので思いっきり楽しもう」
と思うか。
あなたは、どちらのタイプでしたか?
私は、以前は完全に前者のタイプでした。
残りの時間に意識がいって「夏休みも残りわずか」と残念な気持ちになっていました。
これは、プラスの視点とマイナスの視点の話です。
●プラスの視点が強い→楽観主義、ポジティブバイアス
●マイナスの視点が強い→悲観主義、ネガティブバイアス
半分のコップの話をご存じでしょうか。
コップに水が半分入っている。このときに、「もう半分しか入っていない」と思う人と、「まだ半分も入っている」と思う人がいます。
これはマイナスの視点が優位か、プラスの視点が優位かの違いです。
プラスに注目しやすい人は、楽観的な人が多いです。「なんとかなるさ」のような精神です。プラスの視点を持っている人からすると、マイナスの視点を持つ人のことが理解できません。
「なんで、そんなにネガティブなんだろうか」「なぜ、過去の失敗体験に囚われてばかりなんだろうか」「なんで、いつまでたっても行動に移さないのだろう」「なんで、くよくよしているんだろう」……。
プラスの視点が強い人はこう思いがちなのです。
プラスの視点の人が、マイナスの視点の人にストレートに考えを伝えても、なかなか通じなそうというのは、イメージできるのではないでしょうか。逆もしかりです。
妻と夫の視点が違うと、夫婦間の会話で、こんなことが起きるかもしれません。
妻はプラス視点の人。夫はマイナス視点の人です。
妻「(ちょっとハイテンション気味で)見て! この雑誌に特集されている温泉宿、料理もお値打ちで最新の足湯施設もあるんだって。久しぶりに出かけましょうよ! オープン記念の特典もあるんですって!」
夫「オープンしてすぐは、人が殺到するから、そんなに楽しめないかもよ。人がたくさん来るのがわかっているから、料理だって本当はもっと安く食べられるんじゃない? 足湯も、人が多いとゆっくりつかれないかもよ」
こんな感じで、お互いの頭の中は全く違うので、理解し合うことは難しい状態です。せっかくの楽しい提案が台無しになってしまうだけでなく、ひょっとすると、ケンカの原因になってしまう可能性もあります。
では、視点が違う人同士がうまくコミュニケーションをとり合うためにはどうしたらいいのでしょうか?
プラスの視点を持っている人からしたら、マイナスの視点の人のことが理解できないかもしれません。
マイナスの視点の人からしたら、プラスの視点の人のことが全くわからないかもしれません。
そこで大切なのが、「相手の頭の中」を想像してみることです。
なぜ相手はマイナスの視点を持っているのか、なぜ相手はプラスの視点を持っているのかを。
たとえば、マイナス視点の人の頭の中をこんなふうに想像します。
「マイナスの視点を持っているのは、人が多くて時間がかかることや、高齢のため、人混みの中でインフルエンザなどに感染する恐れがあることが嫌なのかもしれない。であれば、少し時期をずらして伝えたほうがよさそうだ」
「マイナスの視点を持っているのは、料金が高いと過度に心配しているからかもしれない。であれば、インターネットで調べて、3カ月後と比べると、今回のオープン料金がどれくらいお得かを伝えたほうがいいかもしれない」
こんなふうに、相手の頭の中をできるだけイメージすることで、コミュニケーションの糸口を発見できるはずです。
相手がどういう世界を見ているかを想像することは、コミュニケーションをうまくとる秘訣です。
ちなみに、ネガティブな視点の人にはマイナスのイメージがあるかもしれませんが、研究ではそうでもないことがわかっています。
現在、科学界では「健康的な神経症」という人が注目されています。
このタイプの人は、物事をマイナスに見る神経症傾向と、物事をコツコツと積み重ねる誠実性が強い傾向にあります。このタイプは、将来の健康を考えて不安になり、その対策として健康に備えるため、歳をとっても健康状態が非常によいそうです。
実際に、喫煙や薬物の使用率が低くなり、炎症やガンなどを引き起こす炎症性サイトカインの値も低く、人生を通して健康的に過ごせる傾向にあります。
また医者や弁護士も、ものすごく楽観的な人は成功しにくいそうです。
マイナス面ばかりを見ている人は、石橋をたたいて渡る人に見えるかもしれませんが、経営者でも長年にわたり着実に売上を伸ばし続ける人は、このタイプかもしれません。
「マイナスに見る力」は個性であって、長所としても見ることができるのです。
■プラスとマイナスが拮抗しているのが、よい視点
一方で、コミュニケーションでNGなのは、相手を責める思考です。
「なんでマイナスの視点を持っているんだ。なんでわかってくれないんだ」
「マイナスの視点を持っているからダメなんだ」
これは相手の頭の中を無視して、自分中心の思考になっている状態です。
こうなると、視点の違う人同士のコミュニケーションはうまくいきません。
ちなみに、プラスの視点とマイナスの視点は、同じ人でも年齢によって変化します。
小さい子どもは、もともとマイナス視点が強いと言われています。親とちょっとでもはぐれたら泣き出してしまったり、学校でちょっとしたことで不安を感じたり、子どものほうがよりその傾向が強いですよね。
これには明確な理由があります。
子どもが親と離ればなれになってしまったらどうでしょうか? 一人では生きていけません。そこで進化の過程で、子どもはマイナスの視点が強くなっていったと考えられています。生存本能なんですね。
小さいときは怖がりでよく泣いていたのに、大人になったらプラスの視点が強くなって、起業したり、登山家になったりするケースもあります。
このように、年齢や環境によっても、視点は変化していきます。
このプラスとマイナスの視点ですが、プラスの視点がいいことで、マイナスの視点が悪いことのように思えるかもしれないですが、実はどちらかに偏りすぎるのは危険です。
プラスのほうばかり見ている人は「ポジティブな人」と見られてよいイメージがありますが、ポジティブに偏りすぎている人のことを「ポリアンナ症候群」と呼びます。
「ポリアンナ症候群」の人は、マイナス面を見ない人、夢ばかり見ている人とも言えます。
地に足がついていないとか、現実に合っていないようなことばかりしている人、たまにいますよね。さらに、楽観的すぎると詐欺にまであってしまうかもしれません。
一方で、石橋をたたいても渡らないくらいにマイナス面ばかり見ている人も、うまくいきません。
大切なのはバランスです。私は「ダブル思考」と呼んでいるのですが、プラスの視点とマイナスの視点の両方をバランスよく持っているのが一番です。
言ってみれば、「現実的な楽観主義」という感じでしょうか。どちらの視点も持っている人が一番うまくいきやすいのです。
■日本人はマイナスに考えやすい遺伝子の持ち主?
「アメリカやヨーロッパの人は、なんとなくプラス思考の人が多い印象がある」
そんな話を知人がしていました。この印象、実は半分くらいは合っています。
正確な理由はわかっていないのですが、大きく分けると、アメリカやヨーロッパの人のほうがプラス思考が強く、アジアの人のほうがマイナス思考が強いと言われています。
アジア人には、心の安定を感じさせるセロトニンを運ぶ遺伝子に一部変異が入っており、欧米人と比べるとセロトニン量が少ないからという説もあります。
ただし、マイナスに考えてしまう性格は遺伝が半分くらいと言われていますので、そういった遺伝子を持っていたとしても、教育や環境によってプラス思考に育つことも十分ありえます。
ちなみに、アジア人でもアメリカやヨーロッパでの生活が長い人は、プラス思考が強くなると言われています。
バイリンガルが、英語を話しているときと、日本語を話しているときとで性格が変わるのは、周りの環境や脳の使っている部分が変わるからです。
そのような視点で見ると、東京と関西の人でも、話す言葉が違うことで視点の変化が生まれている可能性があるかもしれません。
大阪出身で東京在住の人に聞いてみたことがあるのですが、大阪弁で話すと、東京にいるときでも自分の性格が変わっていると感じることがあるそうです。
「大阪弁を使うと、人と仲良くなりやすい感じがするんですよね! 逆に、標準語を使っているときは、なんとなく人との間に距離を感じる気がします」
マイナス思考の人は、プラス思考になりやすい方言(地元の言葉)や、外国人になったつもりでしゃべってみると、気持ちが前向きになって、プラス思考の人とコミュニケーションがしやすくなるかもしれません。
☆ ☆ ☆
未来の自分のために、今日からできることを!
年齢に関係なく、脳も心も、日々の習慣で変えていけます。小さな一歩が、未来の自分を大きく変えるかもしれません。ぜひ、今日からできることをひとつ、始めてみませんか?
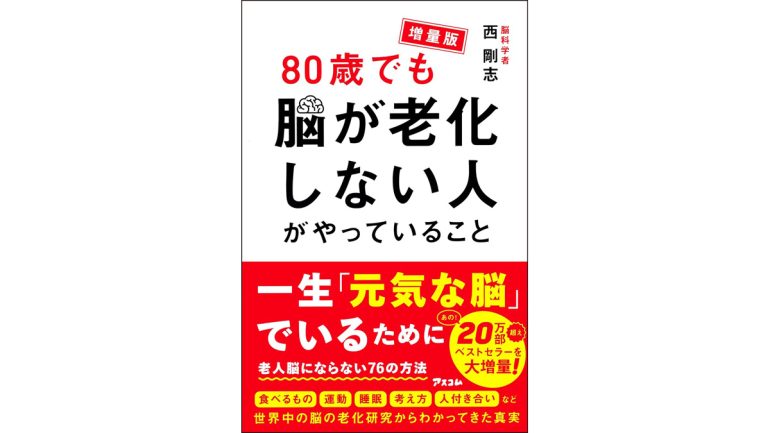
『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』
著者西 剛志
発売日2022年8月13日
価格1400円(税別)
【Amazonで購入する】
【楽天ブックスで購入する】
いくつになっても脳が若いままの人と、老化が進んでいく人の差はどこにあるのか?脳科学者が伝えたい「老人脳」にならないための方法を伝授!スーパーエイジャー(高齢になっても超人的な認知・身体能力を持つ人)たちの脳の使い方をひも解き、いつまでも若々しく幸せなシニアライフを送るコツを届ける一冊です。
(著者情報)
西剛志(にし・たけゆき)
脳科学者(工学博士)、分子生物学者。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。1975年、宮崎県高千穂生まれ。東京工業大学大学院非常講師や特許庁を経て、2008年に企業や個人のパフォーマンスをアップさせる会社を設立。 子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子どもまで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて1万人以上をサポート。テレビなどの各種メディア出演も多数。著作は『なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に伝わらないのか?』(アスコム)をはじめとして累計発行部数10万部を突破。
構成/DIME編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













