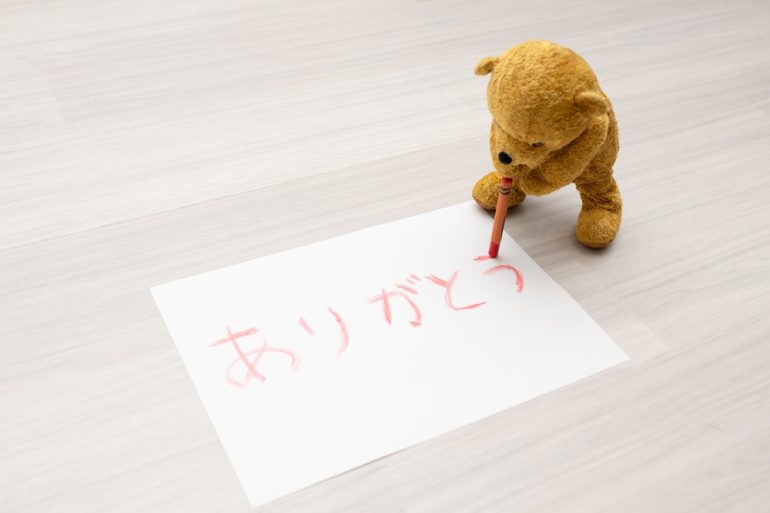
人生100年時代。年齢を重ねることは、経験と知恵が深まる素晴らしい旅です。でも、一方で記憶力や集中力の低下に不安を感じることがあるかもしれません。
そんな中、脳科学者・西剛志氏が提案するのは、「脳の若さ」を保つためのシンプルな習慣。実際に、80歳を過ぎても好奇心を持ち続け、学びを楽しむ人たちが実践していることとは?
この記事では、書籍『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』から、脳を元気に保つヒントを抜粋・再編集してわかりやすくご紹介します。
年齢に関係なく、今から始められる「脳のメンテナンス」を一緒に学びましょう。
「ありがとう」という言葉の持つすごいパワー
言葉の使い方が悪い人は、老人脳になるリスクが高くなります。
人は楽観的性格と悲観的性格の2つに大きく分けられるのですが、楽観的な人はポジティブな言葉を使い、悲観的な人は自分にも人にもネガティブな言葉を使う傾向があります。ネガティブな言葉を使うと脳はストレスを感じるため、老人性うつの原因にもなり、認知症のリスクも高まってしまいます。
一方で、ポジティブな言葉を使うような楽観性が高い人は、認知障害のリスクが低下することが2017年の研究でわかっています。
言葉の持つ力を実感した事例を、ここでもう少し紹介します。これはスポーツ選手の話です。
以前、Jリーグに所属するサッカー選手と話をしていたところ、彼から悩みがあると打ち明けられたことがありました。彼のポジションはフォワード、いわゆる得点することが大切なポジションだったのですが、試合の前半はいいのだけれど、後半になるとシュートの決定率が異常に下がるという悩みでした。
話を聞いてみると、後半になると脳が「疲れているというイメージ」を持っているようでした。「もうスタミナがもたないはずだ」「これ以上は走れないはずだ」とか、脳がそうイメージしていて、結果その通りになっていたのです。
そこで、「自分にはもっとスタミナがある」「最高のパフォーマンスを発揮できる」という言葉を心の内でつぶやいてもらい、イメージを変える努力をしてもらいました。そうしたら、驚くほど後半のシュートの決定率が上がったのです。これには私自身もびっくりしました。
同じように、マラソン選手でも最後にどうしてもタイムが落ちてしまう選手がいました。そこで、彼にある言葉を言ってもらったところ、後半のタイムが伸びたのです。
その言葉は「ありがとう」です。
意外に思うかもしれませんが、この言葉でタイムが大きく伸びました。「ありがとう」は他者に向ける言葉です。自分が走れるのはこれまでたくさんの人のサポートがあったから。そうした支えてくれた人に対して「ありがとう」と心の中でつぶやくだけで、どんどん力が出てきたそうです。
それまでは、後半になると「もつかな」「大丈夫かな」といった不安の声ばかりつぶやいていたそうです。それを「ありがとう」に変えただけでタイムが伸びた。たったひとつの言葉で、ここまでパフォーマンスが変わるのですね。スポーツの世界ではスコアやタイムが出るので、その成果が明確です。
言葉は他者とのコミュニケーションだけでなく、自分とのコミュニケーションにも日々使っています。実は、頭の中で自分自身と話している言葉は、他人と話す何倍もの時間になります。
ですから、自分との脳内トークを変えるだけで、さまざまなことを変えることができるのです。
☆ ☆ ☆
未来の自分のために、今日からできることを!
年齢に関係なく、脳も心も、日々の習慣で変えていけます。小さな一歩が、未来の自分を大きく変えるかもしれません。ぜひ、今日からできることをひとつ、始めてみませんか?
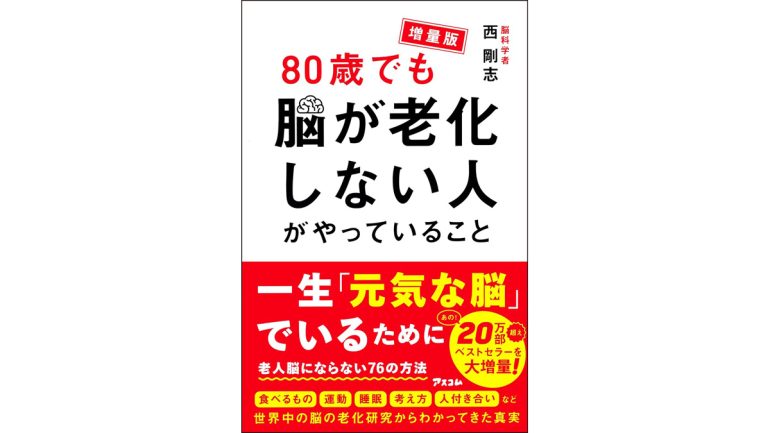
『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』
著者西 剛志
発売日2022年8月13日
価格1400円(税別)
【Amazonで購入する】
【楽天ブックスで購入する】
いくつになっても脳が若いままの人と、老化が進んでいく人の差はどこにあるのか?脳科学者が伝えたい「老人脳」にならないための方法を伝授!スーパーエイジャー(高齢になっても超人的な認知・身体能力を持つ人)たちの脳の使い方をひも解き、いつまでも若々しく幸せなシニアライフを送るコツを届ける一冊です。
(著者情報)
西剛志(にし・たけゆき)
脳科学者(工学博士)、分子生物学者。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。1975年、宮崎県高千穂生まれ。東京工業大学大学院非常講師や特許庁を経て、2008年に企業や個人のパフォーマンスをアップさせる会社を設立。 子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子どもまで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて1万人以上をサポート。テレビなどの各種メディア出演も多数。著作は『なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に伝わらないのか?』(アスコム)をはじめとして累計発行部数10万部を突破。
構成/DIME編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













