
人生100年時代。年齢を重ねることは、経験と知恵が深まる素晴らしい旅です。でも、一方で記憶力や集中力の低下に不安を感じることがあるかもしれません。
そんな中、脳科学者・西剛志氏が提案するのは、「脳の若さ」を保つためのシンプルな習慣。実際に、80歳を過ぎても好奇心を持ち続け、学びを楽しむ人たちが実践していることとは?
この記事では、書籍『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』から、脳を元気に保つヒントを抜粋・再編集してわかりやすくご紹介します。
年齢に関係なく、今から始められる「脳のメンテナンス」を一緒に学びましょう。
耳が悪くなるのは脳のキケン信号
ここまで老人脳に関していろいろ解説をしてきましたが、「この器官が悪くなると脳の老化がかなり進む」という、最も気にしないといけない器官があります。
それが「耳」です。
一見、耳と脳の関連性はそんなに高くないように思えますが、実は密接に関わっていて、老人脳のリスクナンバーワンは耳が悪くなることなのです。
なぜ耳が悪くなるとそんなにキケンなのか? その理由は、私たちは聴覚を通してたくさんの刺激を常に受けているからです。起きているときも寝ているときも、耳からたくさんの音声刺激が脳に入ってきます。これが脳への刺激となって老化を防ぐのです。また、失われた聴覚を視覚や触覚が補おうとすることで、認知機能も落ちやすくなると言われています。
世界保健機関(WHO)は2019年に世界の若者の半数(11億人)が将来難聴になる危険性を警告しています。実際に日本の研究でも、1万人をリサーチしたところ、4000ヘルツに相当する、ちょうど老人性難聴で聞こえにくい高い音が40代以下の男女でも聞こえにくくなっていると報告しています。
特に最近では20代の女性の聴力低下が深刻で、40歳くらいの聴力になっている人が多いそうです。対策としては若いときから、電車などの騒音のある場所では大音量でイヤフォンを使用しないこと。もしイヤフォンなどを使う場合は、余計な音が聞こえず音楽などだけに集中できるノイズキャンセリングという機能のあるイヤフォンをおすすめします。これだと普段聴いている音量で聴けるため、難聴のリスクを下げることが報告されています。
日本人の65歳以上で難聴になっている人(老人性難聴)は約1500万人いると言われています。65歳以上の人口が3625万人なので、40%以上の人が難聴になっているわけです。
老人性難聴の特徴は、
(1)高い音から聞こえなくなる
(2)男性のほうが聞こえなくなる率が高い
(3)片耳ではなく両耳ともなる
(4)50~55歳まではなだらかで、56歳以降は急速に低下する
この4つが特徴ですが、70歳を超すと聴力の悪化は鈍化する人が多いそうです。
高い音とは「小鳥のさえずり」や「子どもや女性の高い声」「飛行機のキーンという高音」などです。また、騒がしい場所での言葉の聞き取りや玄関の呼び鈴の音、電話で話すのも難しくなっていきます。
なぜ高い音ほど聞こえなくなるのか? 理由は、音が脳に伝わるプロセスにあります。耳の外耳から内耳に届いた音の振動は、蝸か牛ぎゅうという場所の中にある有毛細胞によって電気信号に変換されて、脳に伝わります。脳に伝わって初めて私たちは音として認知できるのです。
蝸牛の有毛細胞は、その入口に近いほど高周波(高い音)を処理し、奥に行けば行くほど低周波(低い音)を処理します。大きな音などに長年さらされていると、入口の有毛細胞がダメージを受けるため、高い音から聞こえにくくなってしまうのです。
老人性難聴への対策は、まず「大きな音を聞かない」ことです。それと、血管がつまると難聴のリスクが高まりますので「糖尿病や動脈硬化を予防する」ことも大切です。
また、聞こえにくくなっている場合は我慢せずに、早めに補聴器をつけることもひとつの選択です。補聴器をつけると、認知力が難聴になる前の元の状態に回復するという報告もあります。
一度衰えた聴覚を取り戻すことは難しいですが、もし聴覚が衰えたとしても、聴覚以外の刺激、たとえば体感覚や嗅覚、視覚、新しい体験などがあれば、老人脳を防ぐことができる可能性はあります。「聴覚が衰えたからスーパーエイジャーにはなれない」ということではありません。
私の祖母は50代から耳が聞こえづらくなり、60代では電話もできないほど、ほとんど聞こえない状態でした。90歳でこの世を去りましたが、最後までとても前向きで元気な人でした。祖母が大好きだったこと、それは踊りの教室に通うこと、俳句を詠むこと、そして手紙を書くことでした。
私が大学で東京に上京したときも、毎月手紙で励ましてくれました。後述しますが、手書きで文章を書くことは脳の認知機能を著しく高めます。
つまり、聴覚が衰えたとしても、ほかの刺激を最大限活用し、できる限り脳の元気を手にできるのです。
■認知症の最大の危険因子は「聴力低下」
難聴が認知症の危険因子になると話しましたが、2020年の国際アルツハイマー病協会国際会議で認知症には12の危険因子が報告されています。
この中でもっとも高い危険因子が難聴です。認知症は生活習慣を工夫すれば40%防ぐことができるのですが、そのうち難聴が関与する割合は8%もあります。
次が教育歴で7%を占めています。小さい頃の教育歴だけでなく高齢まで影響するので、大人になってからでも十分防ぐことができます。
スーパーエイジャーには新聞を読んだり、ニュースを見たり、読書や社会の情勢を知ることが好きな人が多いのですが、そういった習慣も脳に影響を与えていると思います。
次に危険因子として高いのが、喫煙とうつ、社会的孤立です。意外なのは、過剰な飲酒は因子の1%しかないことです。まだ認知症の研究は発展途上で、この因子は今後も増えることが予想できます。今後は第1章で紹介した睡眠習慣なども入ってくるかもしれません。
☆ ☆ ☆
未来の自分のために、今日からできることを!
年齢に関係なく、脳も心も、日々の習慣で変えていけます。小さな一歩が、未来の自分を大きく変えるかもしれません。ぜひ、今日からできることをひとつ、始めてみませんか?
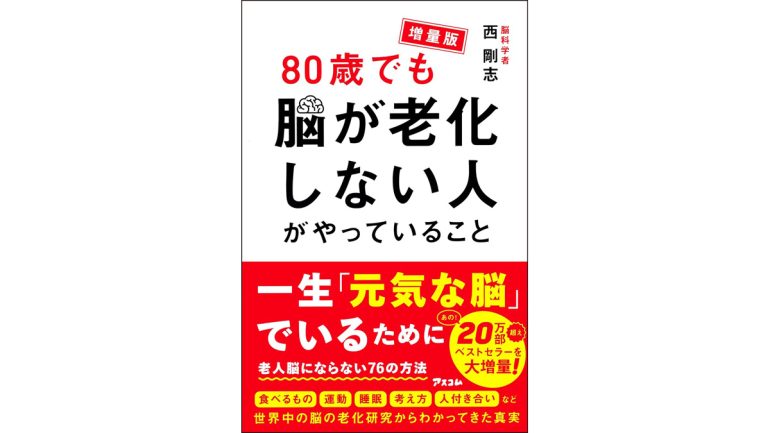
『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』
著者西 剛志
発売日2022年8月13日
価格1400円(税別)
【Amazonで購入する】
【楽天ブックスで購入する】
いくつになっても脳が若いままの人と、老化が進んでいく人の差はどこにあるのか?脳科学者が伝えたい「老人脳」にならないための方法を伝授!スーパーエイジャー(高齢になっても超人的な認知・身体能力を持つ人)たちの脳の使い方をひも解き、いつまでも若々しく幸せなシニアライフを送るコツを届ける一冊です。
(著者情報)
西剛志(にし・たけゆき)
脳科学者(工学博士)、分子生物学者。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。1975年、宮崎県高千穂生まれ。東京工業大学大学院非常講師や特許庁を経て、2008年に企業や個人のパフォーマンスをアップさせる会社を設立。 子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子どもまで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて1万人以上をサポート。テレビなどの各種メディア出演も多数。著作は『なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に伝わらないのか?』(アスコム)をはじめとして累計発行部数10万部を突破。
構成/DIME編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













