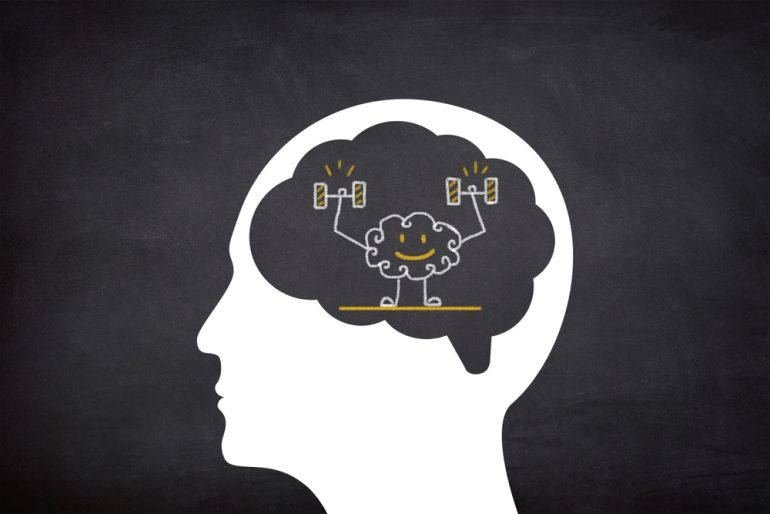
人生100年時代。年齢を重ねることは、経験と知恵が深まる素晴らしい旅です。でも、一方で記憶力や集中力の低下に不安を感じることがあるかもしれません。
そんな中、脳科学者・西剛志氏が提案するのは、「脳の若さ」を保つためのシンプルな習慣。実際に、80歳を過ぎても好奇心を持ち続け、学びを楽しむ人たちが実践していることとは?
この記事では、書籍『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』から、脳を元気に保つヒントを抜粋・再編集してわかりやすくご紹介します。
年齢に関係なく、今から始められる「脳のメンテナンス」を一緒に学びましょう。
脳のピークは何歳なのか?
70代の知人がこんなことを言っていました。
「もう歳なので最近、脳の働きがどんどん悪くなってきているように感じる」
そう感じるのは事実だと思いますが、脳の老化現象はずっと前から始まっています。脳の老化は高齢になってから起きるわけではないのです。
そこで、クイズです。左記の能力のピーク年齢をあててください。□の中に入るのは何歳でしょうか?
(1)情報処理能力のピーク □ 歳
(2)人の名前を覚える力のピーク □ 歳
(3)顔を覚える力のピーク □ 歳
(4)集中力のピーク □ 歳
(5)相手の気持ちを読む力のピーク □ 歳
(6)語彙力のピーク □ 歳
気になる答えは…
もちろん個人差があるので、皆が同じということではありませんが、ハーバード大学はじめさまざまな研究機関で調査したデータでは、答えはこうなります。
(1)情報処理能力のピーク 18歳
(2)人の名前を覚える力のピーク 22歳
(3)顔を覚える力のピーク 32歳
(4)集中力のピーク 43歳
(5)相手の気持ちを読む力のピーク 48歳
(6)語彙力のピーク 67歳
この数字を見て、どんな印象を持ったでしょうか。情報処理能力は18歳がピークで、以降はだんだん下がっていきます。なので、情報処理能力を発揮するような仕事は、脳科学的に見れば若い人のほうが向いているということになります。
この数値を見て、「人の名前を覚えられないのは年齢のせいだったのか」と思ったかもしれません。
「名前を覚える」「顔を覚える」は、脳の「短期記憶」に関わる部分です。短期記憶には「言語の短期記憶」と「視覚の短期記憶」があります。
たとえば電話番号をその場で覚えることは「言語の短期記憶」です。「若いときは電話番号を簡単に覚えられたのに、いまは覚えられない」という人も多いと思います。家族のスマホの番号を覚えている人は意外に少ないかもしれません。
一方で、人の顔を覚える記憶は「視覚の短期記憶」です。こちらは20代後半から32歳くらいまでは上がっていきますが、それ以降はだんだん落ちていきます。
大人数のアイドルグループのメンバーの顔が全く覚えられなくなった。これは30代半ば以降の人にとっては自然の流れです。ちなみに、こうした歳とともに能力が衰えていく知能を「流動性知能」と呼びます。
■50代以降でも伸びていく能力とは
一方で、50代以降の人たちに朗報もあります。50代以降も伸びる能力があるのです。それは「語彙力」です。語彙力のピークは、なんと67歳。昔は長老と呼ばれる人がいましたが、長老が周りの人から尊敬される存在だったのは、歳をとっても言葉の力は老いることがないからだと思います。
こうした言葉の力など、年齢とともに蓄積されていくものを「結晶性知能」と呼びます。その中でも語彙力は断トツで伸びていく能力です。
さらに面白いのが「相手の気持ちを読む力」です。この能力は10代以下の人が低いんです。そして20代になって急激に伸びていき、ピークは48歳です。それ以降はグンと落ちていきます。50代、60 代とどんどん下がっていきます。
この感覚、50代以降の人には実感できるかもしれません。10代は自我の確立をするために、意識の中心には自分がいる。それが社会人になり、「相手」という存在を意識せざるを得ないシーンが増えるのが20 代の頃です。その後いろいろな経験を積み、人の気持ちを考えるようになっていく。まさに結晶型知能が高まっていきます。
ところが50代くらいからは、だんだんと周りのことを気にしなくなる人がいます。別に悪気があってそうなるのではなく、脳の能力が落ちていくことで自然とそうなっていくのです。
こうした傾向は、着るものにも影響します。若いときは近所のコンビニに行くのにもちゃんとした外着で行っていたのが、50代、60代になると着替えるのもだんだん面倒になり、家着のままで外出したり、さらに進むと寝間着のままで行ってしまったり。どんどん人目が気にならなくなっていくのです。
「相手の気持ちを読む力」がさらに衰えていくと、いわゆる失礼な老人、キレる老人になっていくこともあります。家族に横柄な態度をとったり、お店で店員さんに乱暴な言葉を使ったり、自分の思い通りにならないことにキレたり……。48歳を超えたら「相手の気持ちを考えること」に意識を向けていくと覚えておいてください。
ただ、「人の気持ちを読む力」の調査でもうひとつわかったことがあります。それは、人によって振れ幅が大きいということです。たとえば40代でピークになる人もいれば、そのピークが70代、80代まで持続する人もいます。
この差は何か? ピークを長く保てる人は、老人脳にならないために、脳の老化をゆるやかにしたり(スローエイジング)、積極的に若返らせる工夫(ダウンエイジング)をしているのです。何もしないと自然に脳は老化しますが、うまく工夫すると、効果が出てきます。
脳を元気にすることは、人生を充実させるための大切な行為です。
☆ ☆ ☆
未来の自分のために、今日からできることを!
年齢に関係なく、脳も心も、日々の習慣で変えていけます。小さな一歩が、未来の自分を大きく変えるかもしれません。ぜひ、今日からできることをひとつ、始めてみませんか?
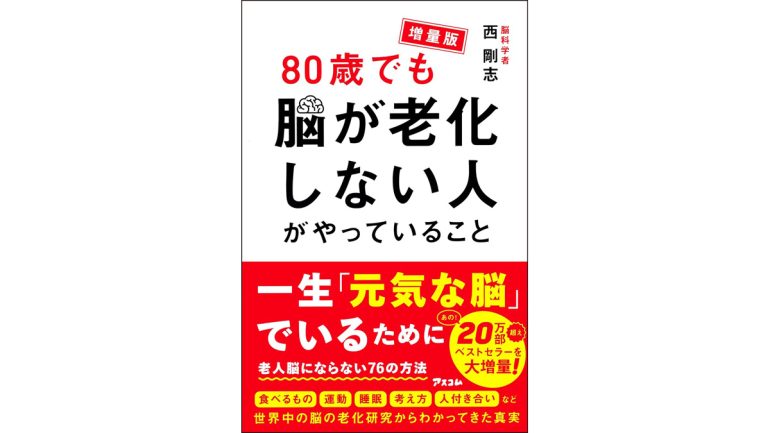
『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』
著者西 剛志
発売日2022年8月13日
価格1400円(税別)
【Amazonで購入する】
【楽天ブックスで購入する】
いくつになっても脳が若いままの人と、老化が進んでいく人の差はどこにあるのか?脳科学者が伝えたい「老人脳」にならないための方法を伝授!スーパーエイジャー(高齢になっても超人的な認知・身体能力を持つ人)たちの脳の使い方をひも解き、いつまでも若々しく幸せなシニアライフを送るコツを届ける一冊です。
(著者情報)
西剛志(にし・たけゆき)
脳科学者(工学博士)、分子生物学者。T&Rセルフイメージデザイン代表取締役。1975年、宮崎県高千穂生まれ。東京工業大学大学院非常講師や特許庁を経て、2008年に企業や個人のパフォーマンスをアップさせる会社を設立。 子育てからビジネス、スポーツまで世界的に成功している人たちの脳科学的なノウハウや、大人から子どもまで才能を引き出す方法を提供するサービスを展開し、企業から教育者、高齢者、主婦など含めて1万人以上をサポート。テレビなどの各種メディア出演も多数。著作は『なぜ、あなたの思っていることはなかなか相手に伝わらないのか?』(アスコム)をはじめとして累計発行部数10万部を突破。
構成/DIME編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













