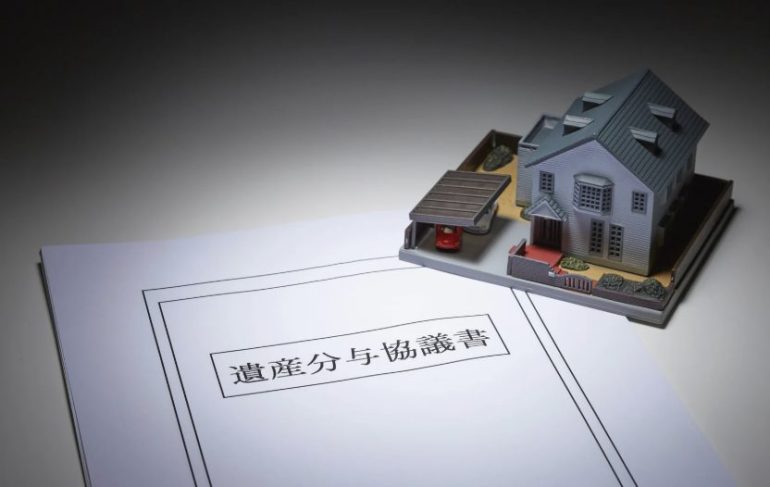
家族が亡くなった際、遺言書や生前贈与の内容が偏っているために、自分が相続できる遺産が少なすぎて納得できないという悩みをよく耳にします。
このような場合でも、「特別受益」の主張や「遺留分侵害額請求」を行えば、相続の結果を公平な形に近づけることができるかもしれません。
本記事では、不公平な相続に納得できない場合の解決策となり得る、特別受益と遺留分侵害額請求のポイントを解説します。
1.不公平な相続が生じてしまうケース
相続の結果が不公平となり、一部の相続人が不満を抱いてしまうケースとしては、特に以下の例がよく見られます。
(a)遺言書の内容が偏っている
亡くなった家族が遺言書を残していて、その中で「長男にすべての遺産を相続させる」などの偏った内容が記載されていると、遺産をもらえなかった相続人から不満が出てしまうことが多いです。
(b)一部の相続人だけが多額の生前贈与を受けた
亡くなった家族が生きている間に、一部の相続人だけが多額の生前贈与を受けていると、贈与を受けていない他の相続人から不満が出てしまうかもしれません。
お金の贈与のほか、留学費用などの高い学費を出してもらったことや、不動産を買ってもらったことなども、他の相続人の不満の原因となるケースがあります。
2.不公平な相続の解決策(1)|特別受益の主張
遺言書や生前贈与の偏りによる不公平を是正する方法の一つとして、遺産分割協議において「特別受益」を主張することが挙げられます。遺言書によって分け方が決められていない遺産がある場合に効果的な方法です。
2-1. 特別受益とは
「特別受益」とは、相続人が被相続人から受けた以下の遺贈または贈与をいいます(民法903条1項)。
・すべての遺贈(=遺言による贈与)
・婚姻のための贈与
・養子縁組のための贈与
・生計の資本としての贈与
一部の相続人が特別受益を得た場合は、その額をすでに取得したものと仮定して相続分を計算します。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
(例)
3000万円の遺産を、亡くなったXの相続人である配偶者A、子B、子Cの3人で分ける。Bには1000万円の特別受益がある。
上記の例では、Bの特別受益を含めた4000万円をA・B・Cの3人で分けるものと仮定します。
配偶者Aの相続分は2分の1なので2000万円、子の相続分は合計で2分の1(各4分の1)なので、B・Cそれぞれ1000万円ずつです。
しかし、Bはすでに1000万円の特別受益を得ているので、その金額を相続分から差し引きます。最終的な相続分は以下のとおりです。
A:2000万円
B:0円
C:1000万円
このように、特別受益のあるBの相続分は減り、他の相続人(A・C)の相続分は増えました。
特別受益を得られなかった相続人は、他の相続人の特別受益を主張することにより、自分の相続分を増やせる可能性があります。
2-2. 特別受益を主張する際の注意点
特別受益の持ち戻しは、被相続人(=亡くなった人)の意思によって免除表示することが認められています(民法903条3項)。
遺言書などによって持ち戻しが免除された場合は、特別受益の持ち戻しを主張することはできません。
また、家族が亡くなった時から10年が経過すると、原則として特別受益は主張できなくなってしまいます(民法904条の3)。
3.不公平な相続の解決策(2)|遺留分侵害額請求
亡くなった家族の財産の分け方が、遺言書や生前贈与によってほとんど決められてしまい、残りの遺産をもらうだけでは不公平を解消できないケースもあります。
その場合は「遺留分侵害額請求」を行いましょう。
3-1. 遺留分侵害額請求とは
「遺留分侵害額請求」とは、被相続人(=亡くなった人)から遺留分未満の財産しか譲り受けていない相続人が、財産を多く得た人に対して金銭の支払いを求める手続きです(民法1046条1項)。
被相続人の兄弟姉妹またはその代襲相続人以外の相続人には「遺留分」が認められています。遺留分とは、相続などによって取得できる財産の最低保障額です。
たとえば、相続人が被相続人の配偶者と子である場合、配偶者には4分の1の遺留分が認められています。つまり、相続財産(遺産)や相続人が10年以内に受けた生前贈与など(=基礎財産)の総額に対して、4分の1に相当する財産の取得が保障されます。
仮に基礎財産が4000万円だとすると、配偶者には1000万円の遺留分が認められます。配偶者が被相続人の財産を500万円しか得られなかったとすれば、財産を多く得た人に対して、不足分の500万円を請求することができます。
3-2. 遺留分侵害額請求を行う際の注意点
遺留分侵害額請求権は、相続の開始(=家族が亡くなったこと)および遺留分を侵害する遺贈・贈与があったことを知った時から1年間が経過すると、時効によって消滅します(民法1048条)。
時効の完成を阻止する方法としては、内容証明郵便による請求書の送付や、裁判所に対する調停の申立てなどが挙げられます。遺留分侵害額請求権の時効が完成する前に、速やかにこれらの対応を行いましょう。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













