
肉の生食や加熱不足が原因で、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌O157による食中毒を引き起こしたというケースを耳にしたことがある人は多いはず。これらの細菌はしっかり加熱調理をすれば死滅するため、「食中毒=加熱で対策ができる」と思っている人もいるのではないだろうか。
しかし、中には加熱しても死滅しない細菌も存在するという。いったいどのような細菌なのか、感染症専門医で藤崎メディカルクリニック副院長の佐藤留美先生に教えてもらおう。
加熱処理では死滅しない細菌がある?
高温多湿の環境は細菌が繁殖しやすく、食品の不適切な取扱いによって食中毒の発生リスクは非常に高くなる。一般的な細菌は熱に弱いとされるが、加熱処理をしても死滅しない代表的な細菌が「ウェルシュ菌」だ。
「食中毒の原因となるウェルシュ菌は、100℃で1時間ほど加熱しても生き残ると言われています。繁殖する最適な温度は43℃~45℃、増殖可能な温度域とすると12℃~50℃です。この温度域で放置する時間が長ければ長いほど細菌が繁殖しているといえます」
■カレーやシチューが要注意な理由
ウェルシュ菌は肉や魚介類、野菜などに付着しているという。これらの食材を使った煮込み料理などが要注意だそう。
「具体的なメニューでいうと、カレーやシチューなどです。これらのメニューは大量に作り、翌日も食べるためにしばらく室温で放置されがちです。今の時期は外気温も高く、冬場と違い、料理が冷めるための時間もかかる。まさにウェルシュ菌が爆発的に増殖しやすい環境が整って、2日目のカレーで食中毒を起こすということになりかねない。食中毒対策という意味では、本来は食べきれる量を作るのが理想的ではあります」
ウェルシュ菌を増殖させない方法

とはいえ2日目の美味しいカレーを食べたいという人も多いだろう。ウェルシュ菌を増殖させないために、どういう対策をすればよいのだろうか。
■加熱後、10℃以下に急冷する
「まずは、調理をする前に食材をしっかり洗い、ウェルシュ菌を洗い流しましょう。加熱調理後の増殖を防止するには、加熱調理後、10℃以下に急冷することです。大きなタッパーに入れると冷めにくいですし、全体の温度が不均一になりやすい。この不均一な状況というのも、細菌が繁殖しやすい環境と言えます。小分けにして室温で速やかに冷まし、冷めたらすぐに冷蔵庫に入れましょう」
■空気に触れさせることで死滅する
小分けにするのは、ウェルシュ菌の空気を嫌うという性質を考えても、いい対策だという。
「嫌気性菌と言いますが、ウェルシュ菌は空気に触れさせることで死滅し、増殖を防ぐことができます。小分けにして酸素に触れさせ、しっかり混ぜるということを意識してもらいたい。また、温めるときも、そのままレンジにかけるのではなく、鍋にうつして全体をかき混ぜながら、酸素に触れさせつつ、温度を均一にするようにしましょう」
■カレーやシチューは冷ましてから冷蔵庫に入れる
ちなみに、ウェルシュ菌が増えやすい温度帯から急いで冷やすために、すぐに冷蔵庫に入れたくなるが、「冷ましてから冷蔵庫に入れる」は徹底しよう。
「温かいカレーを冷蔵庫に入れることで、冷蔵庫内の温度があがります。その結果、ほかの食材に影響を及ぼしかねない。また、冷蔵庫で急速に冷ました場合、表面は冷めたものの、中心部分は生温かいままということになってしまいます。つまり、雑菌が繁殖しやすい環境になりますので、絶対にやめましょう」
少量の菌が体に入ったくらいでは大きな問題にならないが、爆発的に増えたものを摂取することで食中毒に繋がる。細菌ごとに特徴があり、加熱すればOKではない細菌が存在していることを知り、しっかり対策をしつつ、2日目の美味しいカレーを食べてもらいたい。
佐藤留美医師プロフィール
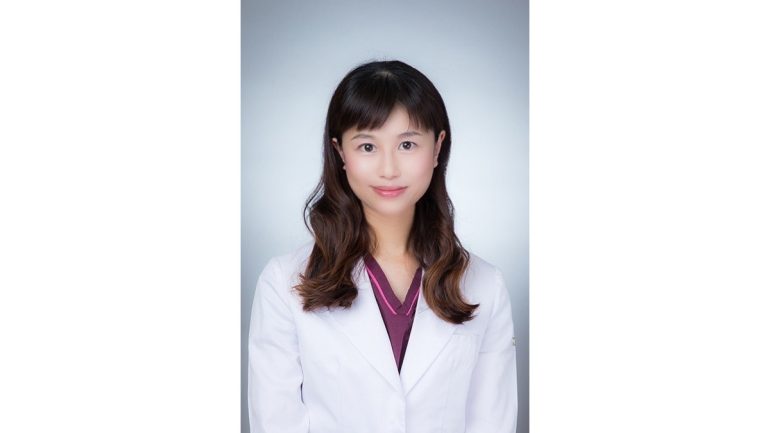
2002年久留米大学医学部卒業後、久留米大学病院で研修医として勤務。現在は同大学の関連病院で呼吸器科・感染症科・アレルギー科として勤務する傍ら、2023年10月より藤崎メディカルクリニック 副院長に就任。医学博士、日本内科学会認定医・総合内科専門医、日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医、日本感染症学会感染症専門医・指導医、日本化学療法学会抗菌化学療法認定医・指導医、日本結核・非結核性抗酸菌症学会結核・抗酸菌症認定医・指導医、日本アレルギー学会アレルギー専門医等を取得。
文/田村菜津季















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













