
私たちは日ごろ、「自分の意思で物事を決定して、最適な行動をしている」、「常にしっかり考えて選択をしている」、「自分の人生は自分でコントロールできている」と思いがちです。
でも実際は、そのときの状況や自らの感情、売り手側の巧妙な仕掛けなど、さまざまなバイアスに左右され、無意識のうちに誘導されています。
・「『限定』や『大人気』という言葉に弱い」
・「セール品に飛びついて後悔する」
・「ネット通販で買いすぎてしまう」
どれか1つでも当てはまるようなら、あなたの思考や行動はパターン化してしまっているかもしれません。
今回は、行動経済学コンサルタントの橋本 之克氏による著書『世界は行動経済学でできている』から一部を抜粋・編集し、行動経済学を「使えるツール」として日常に活かすヒントを紹介します。
【利用可能性ヒューリスティック】「どうして私ばっかり!」という不満はなぜ生まれるのか
■人は悪意なく、自分の印象や記憶をもとに評価する
以前の職場で、後輩のAくんから「自分は毎日たくさんの仕事をこなしているのに、同僚たちはあまり仕事をしていないようで不公平だ」という相談を受けました。
本人によく話を聞いてみると、自分がやっている仕事については雄弁に語るのですが、周囲の人の仕事については、あまりよくわかっていないようでした。
「自分は頑張っている」と思うときには、誰しも自己評価が高くなりがちです。相対的に他人への評価は低くなる傾向があります。その結果、自分では「仕事ができると思っている」のに、他人からは「あいつは使えないやつだ」と思われてしまうという状況は、しばしば起こりがちです。自身の自己評価と、他人からの評価に大きな差ができてしまうわけですね。
お互いが「私はしっかり(仕事を)やっているのに相手はそうではない」という不満を抱えるケースは、しばしば見られます。
自分ばかりが働いていると感じてしまうのは、職場だけではありません。地域の集まりや家族・夫婦間などにもあります。「町内会やPTAの仕事を私ばかりやらされている」、あるいは家庭内の家事分担で「自分はたくさん家事をしているのに、夫が(妻が)ちっともやってくれない」というパターンです。

こうした認識のもとになっていると考えられるのが、行動経済学で言う「利用可能性ヒューリスティック」です。
「利用可能性ヒューリスティック」とは、自分の記憶や印象に強く残っている事象、思い出しやすい事象ばかりを優先して、頻度や確率が高いと判断してしまう傾向を指します。
後輩Aくんの例で言えば、「自分が仕事をしている」という、自分にとって想起しやすい出来事を過大評価する一方、同僚たちの仕事ぶりはあまり見えていないため、印象に残りにくいわけです。
簡単に言ってしまえば、「(見えている)自分がしたこと」を「(見えていない)相手がしたこと」よりも過大評価する、ということですね。
先ほど述べた、家庭内での家事分担問題について、ダニエル・カーネマン教授が著作『ファスト&スロー』(早川書房)で紹介している実験があります。
夫と妻の両方に対して、自分の「家事への貢献度」を尋ねたところ、別々に答えたパーセンテージを合計すると、100%を超える結果になったのです。
これは、2人とも、自分が行っている家事の割合を、実際より多く見積もっていたためと考えられます。
ただし、この状況はお互いに悪意があるわけではない点にも注意が必要です。人が2人以上で作業をする状況では、誰もが自分に見えている貢献を多めに見積もり、他人の貢献は少なめに見積もってしまうのです。自分自身もこうした心理的バイアスに影響されると知っておくだけで謙虚になることができます。他人のことも理解できるようになり、人間関係もより良くなるのです。
■身のまわりの情報だけで不合理な判断をしているかも?
「利用可能性ヒューリスティック」は、いわゆる「思い込み」とも言い換えられます。
自分が見聞きしたことを大切な情報と考える一方で、自分の知らない情報を軽視した結果は、「思い込み」による誤った判断になりかねません。

例としては大震災直後に、あまりに被災の印象が強かったため、自宅に耐震シェルターを設置するケースが見られました。ところが、使う機会がないので結局物置になってしまったという話を聞きます。
その他にも、身のまわりの家族や同僚がインフルエンザにかかっただけで、今はインフルエンザが大流行中だと考えてしまった。1件の少年犯罪のニュースを見ただけで「今、日本は少年犯罪が増えている」と考えるようになった。
いずれも自分の記憶や印象だけに基づいて判断しているため、その認識の間違いに気づかないうえに、自分は正しいと思い込んでいるわけです。
企業も「利用可能性ヒューリスティック」を活用して、販売促進を行っています。
例えば、新商品のキャンペーンをSNSで行う場合、「アカウントをフォローしてハッシュタグを付けて投稿すると◯名様に△△をプレゼント!」というような施策を行うと、たくさんの人が投稿をしますよね。すると、消費者はその商品に対する投稿をよく見かけるようになります。
その結果、自分の印象に強く残るため、「この商品を最近よく見るな」「流行っているのかな」と多くの人が思うのです。
ネットやSNSの世界では、検索や閲覧の履歴をもとに個人が好きそうな情報や意見、広告を表示する仕組みになっています。注意や関心を引くことで、より頻繁に、より長く見てもらうように仕向けているのです。
ただし見る側はこうした操作が行われていることを、さほど強くは認識していません。その状態で毎日同じような情報を見聞きした結果、自分の知っていることが世界の中心であり、流行っていて、正しいものだと思い込んでしまうのです。このような思考や情報の偏りを避けるためには、「利用可能性ヒューリスティック」が働いているということを常に意識しておくことが大切ではないかと思います。
■お互いに「思い込み」があることを自覚、共有する
「利用可能性ヒューリスティック」が難しいのは、紹介した例のように、自分の記憶や印象と、現実の実態(時間や分量など)の違いを、必ずしも正確に比較できない点です。
意見の異なる両者が納得するためには、お互いに見えていない「過程」について伝える、お互いに確認し合う、そして認識をすり合わせることが大切です。
例えば、仕事で何時間も真剣に考えて提出したものを、上司から即NGにされてしまうと腹が立ちますよね。
この場合、部下側は「こんなに考えたのに、上司はろくに資料も見ずに結論を出したんじゃないか」と考えます。逆に上司側は「これまでたくさん教えてきたはずなのに、あまり理解せずに資料をつくったんじゃないか」と疑います。お互いに自分の労力を多大に見積り、相手の行動を軽視するのです。
そんな食い違いをなくすためには、部下側はどんな過程でどのように考えたのかを相手に伝えること、そして上司側も、なぜNGにしたのかという思考の過程を説明できると、お互いに不満な気持ちを持つことなく、相手を理解することにつながるのではないかと思います。
「お互いからは見えていないところ」を軽く考えてしまうのは仕方がないことですので、しっかりと話し合い、過程や考えを共有することが大切だということですね。
家庭内で揉めがちな家事の分担についても、重要なのはやはり「話し合い」、そして現状を正しく可視化することです。
仕事だったら、「いつ」「どこで」「誰が」「どのような仕事をしているか」といったことを報告し合って状況を共有できるようにしますよね。それと同じことを自然な形で家庭内でも行うといいでしょう。
なかなか難しいかもしれませんが、何気ない会話の中で、大変だったことなどを話し合えるといいですね。また、お互いが相手の労力に対して想像力を働かせて思いやることができるとさらにいいと思います。
家庭内では特に感情が先行してしまいやすいので、感情的にならず冷静に話し合うことが大切です。
揉めやすいポイントは、料理・洗濯・掃除などの大きな項目よりも、いわゆる「名もなき家事」と呼ばれる細かい作業かもしれません。これをできるだけ詳細に書き出しておくと、あとになって不満が噴き出すことが少なくなるはずです。
結局のところ、仕事でも家事でも、お互いの心に「利用可能性ヒューリスティック」が働いているということを認識し、自分や相手がどんな思い込みをしているのかを話し合うことが大切だということです。
■名もなき家事
●洗剤つめかえ
●クリーニングを取りに行く
●献立を考える
●ダンボールをつぶしてまとめる
●加湿器の水交換
●郵便物チェック
☆ ☆ ☆
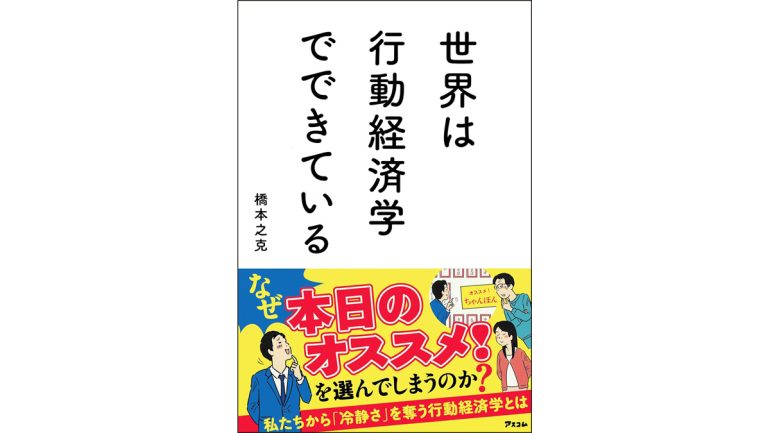
『世界は行動経済学でできている』
著者:橋本 之克
発行:アスコム
【Amazonで購入する】
【楽天ブックスで購入する】
●橋本 之克
行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター
東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。
2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。
構成/DIME編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













