■「あなたはどう思う?」と聞くことに大きな意味がある
当たり前のことですが、そもそもみんなが同じ意見ということはあり得ません。
また、わざわざ「私はあなたとは違う意見を持っています」と言ってくれる人ばかりでもありません。その状況で自分の考えばかりを強く述べると、相手から反感や抵抗を示されたり、否定的な反応をされたりする可能性があります。
誰もが「フォールスコンセンサス効果」に影響されているという前提で、どのようにコミュニケーションを取っていくのが最善なのでしょうか。
1つの方法として、相手がどんな意見を述べてこようと、たとえ自分の考えとは正反対だったとしても、いったんは「そうなんですね」と共感のクッションを置くのがいいと思います。
心からそう思っていなくてもかまいません。相手に「自分が受け入れられた、自分が正しいことを認めてもらえた」と思わせることが大事です。そうすれば、相手は、その後に反対意見を言われたとしても、極端にネガティブな反応はしないはずです。
実はこれは、営業や商談におけるテクニック「応酬話法」の1つである「YESBUT法」の応用です。顧客と反対の意見を述べるとき、提案に説得力を持たせたいときに使われる営業トークです。これは、相手の心理状態を捉えたコミュニケーション法ですから、日常会話でも有効です。 またここでは、行動経済学における「返報性の原理(恩恵を受けたらお返ししようとする心理)」も使われています。
相手の言葉に対して「共感のクッション」を置いて、受け入れられた感覚を持たせることにより、相手側からも「受け入れよう」という気持ちを引き出すのです。
このようにすれば、双方が「フォールスコンセンサス効果」によって自分の考えに固執する状態を避けられます。
上司と部下、あるいは親子などの関係で相手の行動を導く場面でも、この方法は役立ちます。
その前提として、自分の指示や依頼は相手の「常識」とは違うかもしれない、否定されるかもしれないという可能性を念頭に置いておくほうがいいでしょう。そのうえで、「フォールスコンセンサス効果」を和らげるような指示や依頼をするのです。
×「取引先A社の件は、△△でやっておいて」
〇「取引先A社の件だけど、どういうやり方がいいと思う?」
このように、いったん相手にとっての「正しい考え」を述べる機会を設けます。押しつけを避けて、部下なりの意見を聞くのです、そのあとで、次のように本当にお願いしたいことを伝えます。
「確かに、それもいい方法だね。今後のために検討したいけど、今回は△△でやってみるのはどうだろう?」
一度受け取って検討したというひと手間、数分のクッションを挟むことが「フォールスコンセンサス効果」の緩和につながるのです。
もちろん、部下の考えが素晴らしいこともあると思います。その場合は、しっかり褒めて部下の考えを採用すればいいでしょう。
他人の意見を受け入れることは、自分だけでは考えつかないような、新しい視点を得られるチャンスでもあります。
「自分の考え方が正しいのだ」と固執してしまうと、その機会を逃してしまい、自分自身の成長にとってもマイナスになってしまいます。
「正義の反対は正義」などと言われるように、世の中には、「誰にとっても絶対的に正しくて変わらない正義」などというものは存在しません。「自分と他人は違っていて当たり前」という認識を持ち、歩み寄って認め合うことが大事なのだと思います。
*25 Ross, L., Greene, D., House, P. The “false consensus effect”: An egocentric bias in social perception and attribution processes. Journal of Experimental Social Psychology, 1977, 13, 279-301.
☆ ☆ ☆
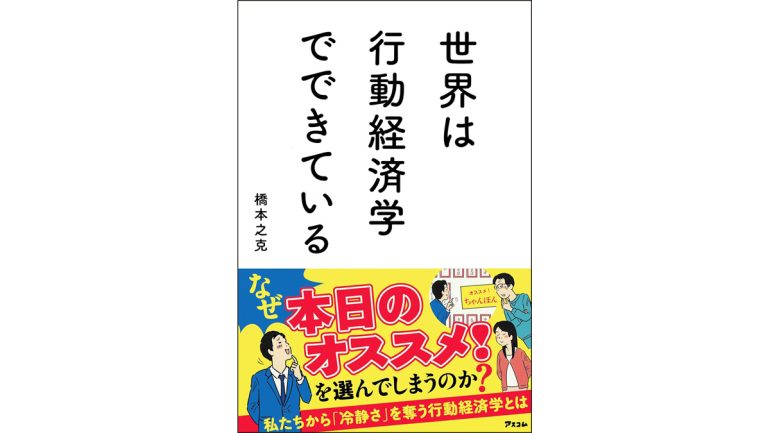
『世界は行動経済学でできている』
著者:橋本 之克
発行:アスコム
【Amazonで購入する】
【楽天ブックスで購入する】
●橋本 之克
行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター
東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。
2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。
構成/DIME編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













