■「もったいない」がさらなる浪費のもとになる
企業の立場で考えると、顧客にサンクコストを意識させると、より多くの支出を促せることになります。
例えば、オンラインゲームなどでキャラクターのレベルアップや、アイテムの強化などに少しずつ課金をさせていくと、ユーザーは「ここまでお金と時間をかけて育ててきたキャラクターを捨てるのは惜しい」という意識が働くようになり、なかなかゲームをやめられなくなります。
出版業界における、いわゆる「分冊百科」も「サンクコスト効果」を巧みに利用している例でしょう。1巻目、2巻目……と取り組んでいるうちに、実は思ったよりお金がかかりすぎる、想像以上に完成までが長いと感じても、いったん買い始めたのだから途中でやめるのはもったいない、という意識が働くのです。
売り手はこの点をよく知っているため、特に創刊号は大きく値引きしたりすることで、とにかく一度体験させる=始めさせるように努めるわけです。
何十巻も続いている漫画を途中でやめられずどこまでも読み続けてしまう、といったことも「サンクコスト効果」と言えます。

このような例は、枚挙にいとまがありません。
■食べ放題で払ったお金の元を取るために、おなかがいっぱいでも詰め込んでしまう。
■自分の足に合わなかった靴を「高かったから」と捨てられず取ってある。
■クレーンゲームで目当ての商品があと少しで取れそうだと感じると、取れるまでゲームを継続してしまう。
■勤めている会社に強い不満があるのに、なかなか辞める決心がつかない。
本項の冒頭の話は、自分にとってのやりがいが感じられなくなっても転職や起業ができないという例でした。それどころか会社に対して明らかな不満があるのに辞められないというケースも多いようです。
それほどまでに、その会社で積み重ねてきた人間関係、肩書き、あるいは職場に慣れるために費やしてきた時間や苦労(=サンクコスト)を無駄にしたくないという気持ちは強力です。客観的に見ると別の会社に早く移ったほうがいいのは明らかなのに、なかなか本人の重い腰は上がらないのです。
「サンクコスト効果」は、表現を変えると「一度始めた物事をやめられない」状態を生み出す心理的バイアスと言えそうです。
似たバイアスに、「オヴシアンキーナー効果(未完成で中断した作業を完了するまでやりたくなってしまう心理)」があります。これにより「途中でやめるのが気持ち悪くて、結局はやめない」といった状態になります。
また「現状維持バイアス(変化を避けて現状を保とうとする心理)」も似たバイアスです。その裏側には「変化することによる損失」を避けたいという心理があります。すでに始まっている物事に対して、「変化を避けて継続しよう」という判断になるわけです。
「エンダウド・プログレス効果」も近いバイアスです。こちらは、少しでも前進したと感じると、さらに進み続けたくなる心理です。「すでに始まっていることが継続意欲を生んでやめられない」状態になります。
このように、損得勘定やモチベーションに関するさまざまな心理が、過去のサンクコストを無駄にしたくない心理とあいまって、結果的にやめられない状態に陥るのです。

■過去ではなく未来に目を向けること
実は、「サンクコスト効果」は、時間が経過すればするほど消えていくとも言われています。時が経つと過去にこだわる気持ちが減り、未来に目を向ける合理的な考え方に変わっていくのです。
とはいえ時間の経過をただ待つのではなく、自ら未来を見る努力が必要なことは言うまでもありません。
「サンクコスト効果」に惑わされないためには、現在の「得」だけに注目せずに思考を将来に広げるのもいいでしょう。全体を俯瞰することによって、今は見落としている「得」が見つかるかもしれません。
「あと1500円で送料無料!」と言われたとしても、未来のことを考えると、送料を支払ったほうがいいかもしれません。大して欲しくもないのに買ってしまった1500円の商品は、未来においても不要だからです。
ここまで「サンクコスト効果」の悪影響について述べてきましたが、この心理的バイアスは必ずしも悪いものというわけではありません。
「捨てるのがもったいない」と感じるのは、自分がそれまでに積み重ねてきた時間や労力の価値に気がつくということでもあります。
冒頭の転職の話で言うと、その仕事を続けていくと覚悟を決めることも、やりたいことに挑戦すると決意することも、選択肢としてどちらもありでしょう。どちらかが間違っているというわけではないですよね。
踏み出したい気持ちと、それに伴うリスクをできるだけ冷静に天秤にかけて、その都度、自分にとって最適だと思う選択をすべきです。そうすれば、さまざまな場面での後悔を減らしていけると思います。
ちなみに、私自身も「サンクコスト効果」によって、過剰な「もったいない精神」を持て余してしまうことがあります。
過去にコストを払った結果、目の前にあるものは本当に価値があるのか。
今の状態や行動を今後も続けるべきか。
そんなときに考えるのは、「限られた物だけを持って無人島に行くとしたら、それを持っていくか」「もし明日人生が終わるとしても、それをやるか」です。
ちょっと極端ではありますが、参考にしてみてください。
☆ ☆ ☆
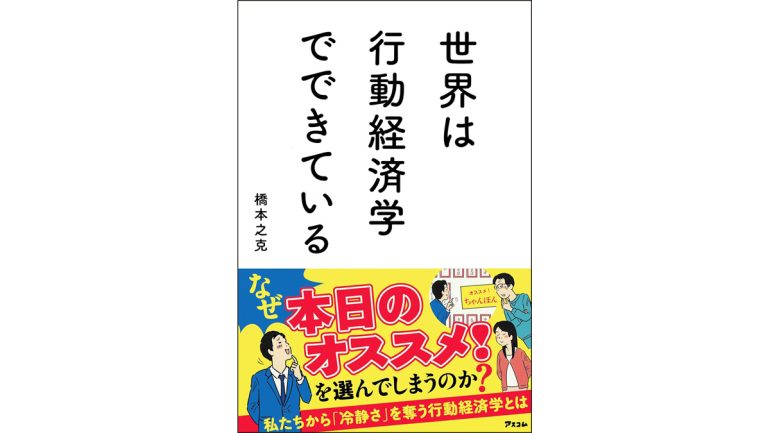
『世界は行動経済学でできている』
著者:橋本 之克
発行:アスコム
【Amazonで購入する】
【楽天ブックスで購入する】
●橋本 之克
行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター
東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。
2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。
構成/DIME編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













