■ディズニーランドが従業員を「キャスト」と呼ぶ理由
ラベリングによってポジティブな変化を促す取り組みは、多くの企業でも行われています。
例えば、東京ディズニーリゾートでは園内で働いている従業員を「キャスト(演劇などの配役、出演者)」と呼んでいます。会社側がそう呼ぶことで、あるいはお互いをそう認識させることで、「夢の国」を演出するための重要な役割を果たしていると自覚してもらい、それにふさわしい行動をさせるためのラベリングです。
マクドナルドが店舗で働く従業員を「クルー(船や飛行機などの乗組員や搭乗員)」と呼んだり、スターバックスコーヒーが全従業員をパートナーと呼んだりするのも、会社がそう決めることで、お互いに同じ船に乗っている乗組員、同じ立場の相棒として協力し合って働く意識を持たせようとラベリングしていると考えられます。
この手法はマーケティングにもよく使われていますし、逆に消費者が自らにラベルを貼ってしまうというケースもあります。
最近、○○女子、××男子のような呼称づくりが活発ですが、これには消費者や利用者にラベリングすることで、より積極的に消費、利用してもらおうという意図があります。「ワークマン女子」という言葉がつくられて、自分自身をそうだと認識した人は、よりワークマンで買い物をするでしょうし、自然と服装や趣味などがそっちの方向に寄っていきやすくなります。
ラベリングは、教育や指導でも活用されています。

「あなたは国語が得意だね」とラベリングすれば、国語の成績が上がる可能性が高くなりますし、上司が部下に「君は仕事が早いね」とラベリングすれば、部下はさらに早く仕事をこなそうと思うものです。
つまり、ポジティブなラベリングをすればポジティブな行動をさせることが期待できます。反面、自分の考えとは相反するラベリングをされれば、生きにくさ、あるいは呪縛のような存在にもなり得ることになります。
「医者の子どもなんだから医学部に行きなさい」など、子育てにおいて親が子どもの意思に反したラベリングをすると、その子のモチベーションを失わせる結果にもなりかねません。
他人からの評価や期待、声かけがその人の行動にじわじわ影響を及ぼす心理効果は他にもあります。
●バーナム効果…誰にでも該当するような一般的な性格や特徴などが、まさに自分に当てはまると思い込んでしまう傾向(例・血液型でA型は几帳面、B型はマイペースなどと言われると納得してしまう。ダイエット商品の広告で「なかなか、やせられないあなたに」などと書いてあると「まさに私のことだ」と思ってしまう)。
●ピグマリオン効果…他者から期待されると頑張れたり、やる気が出たりして成果を出せる傾向になる心理効果(例・「今後1年で成績が伸びる」という嘘の保証をされた生徒のIQが大きく伸びた[ハーバード大学・ロバート・ローゼンタールの実験より])。
●ゴーレム効果…相手に対して期待できない、見込みがないと思っていると、本当に悪い結果になる心理効果(例・成績が悪い生徒という先入観を持って指導すると生徒の成績が下がってしまう)。
このような心理効果があることを知ったうえで、ポジティブな方向に活用していくことが大切ですね。
■ポジティブラベルで人を育てる
「ラベリング効果」などを良い方向に使っていけば、本人の意識や振る舞いを前向きな方向に誘導できます。逆に、ネガティブなものは意識や振る舞いに悪影響を与えてしまうので、要注意です。
例えば、こんな使い方がおすすめです。
■「たくさん宿題ができたね」 → 「今日の宿題王だね」
■「メンバーをうまくまとめられたね」 → 「まさにリーダーだね」
■「自分で言ったことをきちんとやっているね」 → 「いつも有言実行だね」
上下で同じことを言っているように見えるかもしれませんが、相手の行動に焦点を当ててポジティブな言葉を使うのは前提として、「動詞ではなく名詞を使う」ところがポイントです。
「宿題ができた」ではなく「宿題王」と名詞にすると、明快なラベルになります。
相手を注意したいときも、その内容を「ポジティブ転換」して行動を促していく手法が使えます。
■「しつこい」 → 「粘り強いね」
■「仕事が遅い」 → 「仕事が丁寧だね」
■「結果が出るのが遅い」 → 「大器晩成だね」
こう呼びかければ、それとなく注意をしながらも、相手の良いところを褒めているように受け止められるのです。
「ラベリング効果」は多くのコミュニケーションシーンで応用できます。
会社の人間関係であれば、ちょっとした動きや特徴をポジティブに捉えて、例えば「アイディアマンだね」「資料づくり名人だね」「プレゼンのプロだね」などとポジティブなラベルを貼ってあげることで、良い関係を保ちながら、相手を育てていくことができるでしょう。
子育てならば、実験の例のように「あなたはお手伝いができる子だね」「算数が得意な子だね」「優しい子だね」などとラベリングしていくことで、子どもが自分自身をそういう人間だと思い、良い方向に成長できるよう影響を与えられる可能性があります。
「ラベリング効果」を用いて影響を与えようとする場合に、大事なポイントは2点です。
まずは、何度も同じ声かけをして、本人の意識の中に刷り込むこと。
そして、もし本人の反応が弱かったり、あまり変化が見られなかったりする場合は、そもそものラベルが間違っている可能性があるので、ラベル自体を見直すことです。
この2つの視点を持って、ラベルをうまく活用していけるといいでしょう。
人やモノにラベリングをする注意点として、一度貼りつけてしまうと「そういう人だ」「そういうものだ」というフィルターがかかってしまい、それ以外の要素が見えにくくなってしまうことがあります。
なかなか難しいことではありますが、常に「その評価は正しいのか?」という疑問を持ち、既存のラベルだけにとらわれず人やモノを見る意識を持つことも大切なのだと思います。
■「こう思われたい」というラベルを自分に貼る
さて、このラベリングは他人から一方的に影響を受けるものではありません。
自分で自分にラベリングをして、セルフブランディングや自己実現のツールとして利用することも可能です。
例えば、会社員時代に社内の飲み会は一次会で必ず帰るという同僚がいました。
「長時間の飲み会は時間の無駄」という考え方の人だったので、「一次会で帰る人」という共通認識(ラベリング)ができていました。その結果、本人もまわりも「誘う・誘わない」でストレスを感じることなく、付き合うことができていたようです。
「こう思われたい」、あるいは「こう思われたほうがラク」というラベルを自分に貼りつけて、まわりにそのキャラクターを認知させることができれば、ストレスのない人間関係を築くことにもつながると思います。
ただし、自分自身に対して自分で無意識にラベリングをしてしまい、それが悪く働く場合もあるので注意が必要です。例えば、うまくコミュニケーションが取れない失敗の経験が何度か続いただけで「自分は話下手だ」などと、自分自身で思い込んでしまうケースです。
自分に対するネガティブな決めつけをするのはやめて、ポジティブなラベリングをしていきましょう。
*12 Miller, R. L., Brickman, P., Bolen, D. Attribution versus persuasion as a means for modifying behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 1975, 31, 430-441.
☆ ☆ ☆
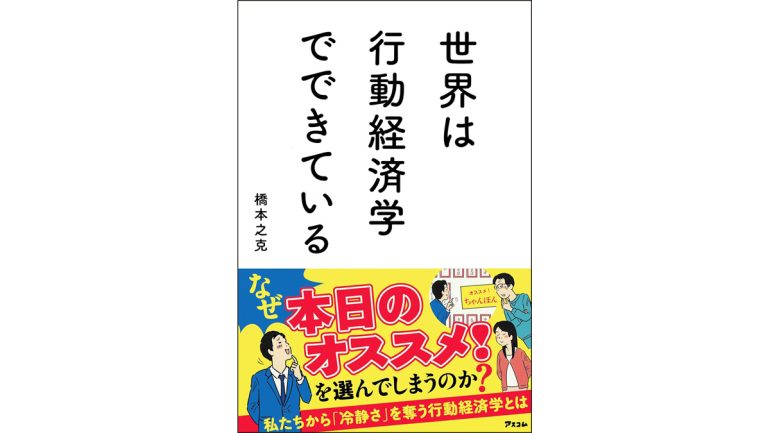
『世界は行動経済学でできている』
著者:橋本 之克
発行:アスコム
【Amazonで購入する】
【楽天ブックスで購入する】
●橋本 之克
行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター
東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。
2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。
構成/DIME編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













