■五感に刷り込まれることで好きになる
接触回数が増えるほど好意度が増すという「ザイオンス効果」の原則を利用しているのが広告です。
広告の露出を増やし、消費者と接触する回数を増やせば増やすほど、好意度は増加していくことになります。
広告業界には「セブンヒッツ理論」と呼ばれる法則があります。消費者がCMに7回接触すると、その商品やサービスに対する認知度が向上し、購入率が高くなるとされています。
もちろん、一人の消費者がテレビを見ている時間は限られているので、かなりの回数CMを流す必要があります。さらに最近はテレビを見ながらスマホを眺めたり、パソコンをいじったりする人も多いので、注目を集めるようなクリエイティブ上の工夫も必要です。
目で見てもらえなくとも、聞いてもらうことで意識してもらう方法もあります。
その1つが、テレビCMなどの「サウンドロゴ」です。
CMの最後に1~3秒くらいの長さで、企業や商品名、キャッチコピーなどをメロディーに乗せて流す音楽のことで、例えば「お、ねだん以上。ニトリ!」(ニトリ)、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」(ファミリーマート)、「インテル入ってる」(Intel)など。どれも聞いたことがあるのではないかと思います。
1つの企業が行うCMは通常、商品ごとに異なるため、さまざまなパターンがあります。しかし「サウンドロゴ」は共通してCMの最初や最後に入っているので、消費者は何度も耳にすることになります。テレビ以外にネットの動画や音声の広告で聞かせる、店頭のBGMとして聞かせるといった方法もあります。
このように「ザイオンス効果」を有効に活用して、企業や商品に対する好意度を高めているわけです。
院長の顔写真付き看板で関東圏ではおなじみの「きぬた歯科」も同じ戦略を取っていると思われます。
きぬた歯科は、東京都八王子市の歯科医院ですが、看板は北は栃木県から南は三重県まで、なんと300枚以上も設置されているそうです。そのためか、都外から訪れる患者さんも多いようです。看板を「よく見る」ことで、好意度を上げることに成功していると言えるでしょう。
他にも、容姿も実力も同じくらいのアイドルタレントなら、接触度が高いほうが人気者になる可能性が高くなります。会うことのできない高嶺の花のようなアイドルよりも、直接会えて握手ができるアイドルに親近感を覚えるものですよね。
さらにそこでは「利用可能性ヒューリスティック(印象に強く残っている事柄を優先して考える心理)」(278ページ)も働きます。メディアを通して見ているだけでなく、実際にそのタレントに会うことで強い印象が残るため、誰を「推し」にするかを考えたときには、真っ先に思い出します。アイドルの人気の裏側には、こうした心理効果も働いています。
「ザイオンス効果」は何度も見聞きすることで好意度が高まるものですが、その効果は視覚、聴覚だけに限りません。味覚、嗅覚などにおいても同様の働きがあります。何度も食べた味、何度も嗅いだ香りなどに対して好意度が高まることがあるのです。
典型例としては、いわゆる「おふくろの味」です。
子どものころに母親がつくってくれた、大好物の料理が忘れられないという人は多いのではないでしょうか。同じメニューを繰り返し食べていると、それが好物になっていきます。その結果、「おふくろの味」は、いくつになっても大好きな味として心に残っているのです。
味噌汁やカレーなど何気ない料理でも、家ごとに少しずつ違いがあるものですよね。「やっぱりウチの味が一番」と思う裏側にも「ザイオンス効果」が存在しているのです。
■接触を好意につなげるコツ
「ザイオンス効果」を利用して好意度を上げることができるならば、好きな相手との恋愛もうまくいくのでは、と思うかもしれません。
確かに人間の心理をふまえたアプローチは有効です。しかし注意すべきこともあります。ここでは「ザイオンス効果」に関する注意点を3つ紹介しましょう。
■その1 「ザイオンス効果」は無限ではなくピークが存在する
実際に、何度もしつこく会おうとしたばかりに逆に嫌われてしまう……なんてことがありますよね。
ピークが何回目に来るのかは、好意度を抱く本人や対象によって異なるので、正確な回数を定めることはできませんが、とにかく「限界がある」ということを理解しながら接触を繰り返すべきです。
ネット広告、メールなどで繰り返し送られてくる売り込みのメッセージを思い出してください。同じ業者から何度もPRメールが送られてきて、ウンザリしている人も多いのではないでしょうか。
このようなメールは、多くの人に同じ文章が機械的に送信されたものです。受け取る人のことを考えていないので、「ザイオンス効果」を理解していないのでしょう。「接触が多すぎると相手をうんざりさせる」という例ですね。
つまり、「ザイオンス効果」を活用する場合は、「押しの一手」ではなく、頻度についてもよく考えたほうがいいでしょう。
■その2 第一印象が良くない場合には効果を発揮しにくくなる
初対面の出会いで悪い印象を与えてしまった場合、単純に何度も会うだけで挽回するのは難しいかもしれません。
恋愛をテーマにしたコミックなどでは、最悪の出会いをした2人がめでたくカップルになるケースがあります。しかし、これはあくまでフィクションの世界のこと、現実には難しいと心得ておきましょう。
■その3 間を空けすぎてはいけない
人間は「忘れる」生き物ですので、複数回の出来事が一連のものと認識されないと効果は生まれません。
昔、上司から「常連の店をつくりたければ3日連続で通え」と言われたことがあります。1カ月に一度を3カ月続けるよりも、3日連続で通うほうが相手の印象に強く残りますよね。
覚えてもらうまでは、短期間で接触を増やすといいでしょう。
以上のような注意点に加えて、もう1つ付け加えるならば、「単に接触機会を増やす」だけでなく、「相手に関わりを持たせる」ことをおすすめします。
これは、「ザイオンス効果」と同時に「保有効果」や「イケア効果」を利用するためです。
それぞれの詳細は後ほど述べますが、「保有効果」は自分が所有するものを高く評価する心理です。また「イケア効果」は自分が手がけたものを高く評価する心理です。人は自分が関わったものに対して価値を、さらには愛着を感じるものなのです。
ですから恋愛を成就させたいならば、まずは単に会うことから始めて、徐々に(どんな小さなことでもいいので)一緒に同じ行動をする機会を持つといいでしょう。
例えば、共同で何かをつくる、同じ団体に所属して一緒に何かの役割をする、といったことです。相手が関わった物事に対して愛着を感じ始めてくれたなら、そこからあなた自身に対する関心も高まる可能性があります。
営業でも同じです。何度も訪問して話したり、お土産を渡したりするだけでなく、何らかの関わりを持ってもらうのです。
例えば、商談中に書類に記入するなどの作業をお願いする、複数案の中から1つ選んでもらい、その理由を教えてもらうなど、いろいろな方法があると思います。受け身でなく「書く」「考える」などの行動で関わってもらうことで、相手が前向きな意識になる可能性が生まれてきます。
苦手だけど、仕事で関わらないといけない人。なかなか話を聞いてくれない取引先。恋愛で仲良くなりたい、お付き合いしたいと思っている相手。PRしたい新商品やサービス……。
そういったものに「ザイオンス効果」をうまく活用してみてください。
*5 Zajonc, R. B. Attitudinal effects of mere exposure. Journal of Personality and Social Psychology, 1968, 9, 1-27.
☆ ☆ ☆
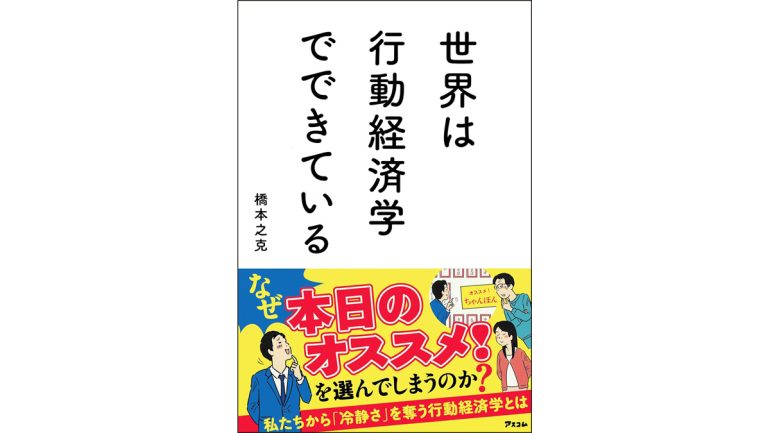
『世界は行動経済学でできている』
著者:橋本 之克
発行:アスコム
【Amazonで購入する】
【楽天ブックスで購入する】
●橋本 之克
行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター
東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。
2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。
構成/DIME編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













