■ケータイを乗り換える人が有利な理由
企業がマーケティングを考える際、消費者の「現状維持バイアス」は大きな壁になります。「変えることが面倒くさい、行動したくない」という障壁を突破してもらうためにも、顧客に「変わることのメリット」を強調した仕掛けやオファーを考える必要があります。
例えば、携帯電話会社の乗り換えは、「現状維持バイアス」が非常に強く働く典型例と言えます。
そのため、乗り換えてほしい側の携帯電話会社は、かなり大きなメリットを提供しないと、なかなか他社のユーザーの気持ちを動かせません。そこで、思い切った値引きや、データ量の優遇措置などを講じるわけです。

あれほど魅力的な乗り換えキャンペーンを実施できるのも、一度契約してもらえれば、また「現状維持バイアス」が働き、その後何年もお金を落としてくれることがわかっているからです。新規の顧客を獲得するためには、それなりの費用がかかりますが、既存の顧客を維持することには、それほど費用がかからないのです。
反対に顧客を抱えている側の携帯電話会社にしてみれば、一度契約した顧客がなかなか解約しないことは、自社の利益に直結しています。いいことではありませんが、解約の方法を面倒にしたり、わかりにくい手続き方法をあえて改善しないケースが見られたりするのも、そのためです。
顧客がせっかく「現状維持バイアス」から逃れて乗り換えをしようとしても、方法が面倒くさくてあきらめてしまうよう促しているのです。
しかし、悪意がないように見せかけて契約を続けさせるやり方は、長期的にはブランドイメージを悪化させる結果になります。いずれ顧客に逃げられてしまうので、あまり得策とは言えません。
むしろ、契約済みのユーザーに対しては、長期契約がお得になるプロモーションが効果的です。自発的に継続を選んでもらえれば、企業ブランドへの悪影響もありません。顧客側の立場ならば、新規契約メリットだけでなく、会社別の継続メリットを比較して選択するのが賢い方法かもしれませんね。
■転職の壁を乗り越える戦略
転職するかしないかを考えている際にも「現状維持バイアス」が働きやすいと述べましたが、これは転職情報企業にとって大きな壁になります。当たり前のことですが、転職したい人がいなければビジネスは成り立たないからです。
そういった観点で転職情報企業のプロモーションを見ていると、とても面白いことに気づきます。
例えば、リクルートエージェントやdoda(パーソルキャリア)などは、一般的な総合職の転職をターゲットにしています。そのための広告では、転職することの「恐怖」や「不安」を取り除くような内容が多いように感じます。
リクルートエージェントは「エージェントによる的確なアドバイス」を打ち出し、dodaは「エージェントとサイトの両方によるサポートが可能」と訴えます(「転職のホントが知りたい」篇)。両社とも、不安や疑問を解消してくれる人や情報といった「機能」を提供し、顧客に寄り添う姿勢で転職を促しています。
一方で、いわゆるハイクラス向け転職エージェント「アサイン」は、「自分の可能性にかけてみてもいいんじゃないか」というコピーで「情緒」的に、挑戦することがカッコいいと訴えています。
いずれのCMも「現状維持バイアス」を崩すための戦略であることは同じですが、ターゲットによってアプローチが異なる、というわけです。
また、「現状維持バイアス」は「損失回避」とも関係があります。
「損失回避」に影響されると、目先の、または表面的な損を避けようとします。その結果、より大きな損をするといった事態に陥ります。
一方、「現状維持バイアス」に影響されると、よく考えずに、とにかく現状を維持しようとします。その結果、変化することによって改善の可能性が高い物事にも取り組みません。ともに無意識のうちに、損につながるバイアスです。
■「変わること」はチャンスである
私たち人間はみな、無意識に変化を嫌い、現状を維持しようとします。だらだらと「今」を続けることには無頓着で、何の疑問も感じません。
わかってはいるけど変えられない、変わるのが面倒……という自分をどうにか奮い立たせるのは困難です。他人の行動を変えさせるのも、簡単ではありません。

なぜなら「現状維持バイアス」以外にも、慣れ親しんだものを好む「ザイオンス効果」が働きますし、これまでに使ったコストを惜しむ「サンクコスト効果」も影響します。
変化しようと思い切ったとしても、選択肢が多い場合は「決定麻痺」によって行動が止まることもあります。「変わること」に対するハードルはなかなか高いのです。
特に古くからある会社などでは、「現状維持バイアス」が働きやすい傾向があります。
これまでとは違う新しいやり方や、大きな組織改革が提案されても、古くからいる社員たちは反対しがちです。原因は「変えたくない」という気持ちです。変えるべきか、維持するべきか、本当はどうするべきかを考えず、とにかく「変化すること」を避けようとするのです。
この場合、現状を変えないだけではなく、「変えるべきではない」もっともらしい理由を見つけ出して、自分自身の考えに固執することもあります。さらに周囲を巻き込もうとするケースもあります。この心理的バイアスを「理由に基づく選択」と言います。これは、何かしらの理由やストーリーがあれば、矛盾があっても気にしないという傾向です。
典型例は、「自分へのご褒美」という理由で自分自身を納得させて、高いものを買ってしまったり、デザートをたくさん食べてしまったりするケースです。
よく考えれば、そんな理由づけなどせずとも、好きなものを買ったり食べたりすればいいはずですよね。ところが、こうした「理由」を付けることで、罪悪感が消えて行動しやすくなるわけです。
このように、「変わること」を邪魔する要因はたくさんあります。「従来のやり方や前例」を良しとし、「自分たちの世代の意識」を大事にする人々もたくさんいます。
こうした人々がいわゆる「老害」になってしまうと、企業や団体が全体的に時代の変化についていけず、落ち込んでいくことになりかねません。
もちろん、すべてにおいて新しいものが優れていて、古いものが劣っているというわけではありません。しかし、変化のスピードが目まぐるしい現代において、変わらないことはリスクでもあります。
新しいものを柔軟に試してみる、受け入れる姿勢を持つことは、さまざまな変化に対応していくためにも大切なことでしょう。
最近、同年代の友人たちと集まると「歳を取ると変化が減るね」「新しくやりたいこともなくなるね」という話題がよく出ます。
よく考えると、これも「現状維持バイアス」に他なりません。世界には新しいモノやコトがあふれているのに、「やったことがあること」しかしていないから、そのように感じてしまうわけです。
なじみの店ばかりではなく新しい店に行ってみる、通勤ルートをいつもと違う道に変えてみる、聴いたことがない音楽を聴いてみる、着たことがない服装に挑戦してみるなど、日常の中で「新しいこと」に取り組むチャンスは無数にあります。
毎日をつまらなくするか、面白くするかは自分次第ということを心に留めて、「現状維持バイアス」という枷を外し、新しいことにチャレンジしていきたいものですね。
*29 Hartman, Raymond S., Michael J. Doane, Chi-Keung Woo. Consumer Rationality and the Status Quo. The Quarterly Journal of Economics, 1991, 106, 141-162.
☆ ☆ ☆
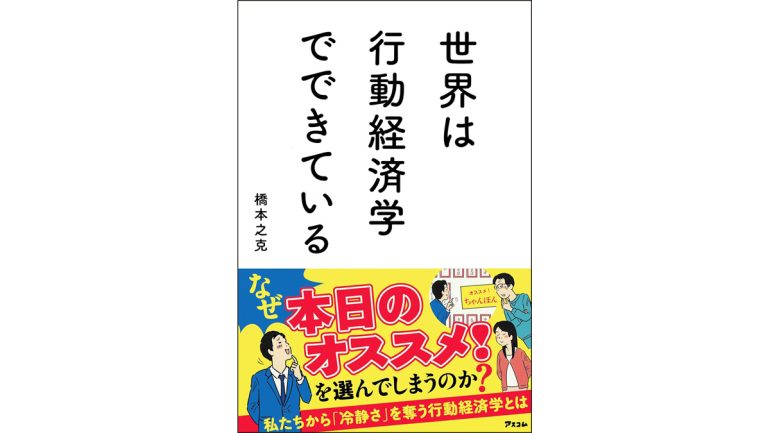
『世界は行動経済学でできている』
著者:橋本 之克
発行:アスコム
【Amazonで購入する】
【楽天ブックスで購入する】
●橋本 之克
行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター
東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。
2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。
構成/DIME編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













