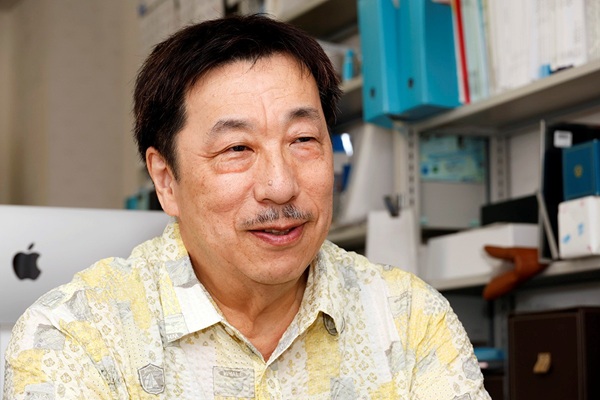
「One Health」の概念が浸透してきた。「動物の健康と良好なQOLは生態系の健全さや、生態系を共有する人の健康と良好なQOLに繋がり、アニマルウェルフェアの推進は直接的間接的に人の福祉増進に貢献する」と主張する中江教授に、主宰している「動物と人の予防医学研究会」の活動と、日本の動物福祉について聞いてみた。
人と動物が一緒になってQOLを向上させる
――中江先生は現在、帝京平成大学の健康医療スポーツ学部医療スポーツ学科の動物医療コースで、動物の看護師さんを目指す学生を指導しています。
中江先生 「愛玩動物看護師」が国家資格になったのを機にその養成コースを開設することになった帝京平成大学からのお誘いを受けました。私自身はもともと化学物質が原因となってがん化するメカニズムを解析するような研究を行ってきました。国の機関で化学物質のリスク評価や評価基準などの作成に関与させていただいたり、生活習慣病の発生と進展における活性酸素の影響とその制御などについて実験的に調べたりして、人間の予防医学を主に研究してきたのですが、研究を続けるうちに、近年、人とペットの関係が大きく変化し、伴侶動物が家族の一員となってきているのに気づいたのです。
動物と家族との関係は、親子や夫婦の関係性にも劣らない、深い愛情で結ばれています。そこで、人だけが健康になるのではなく、人と動物がいっしょになって、生活の質を上げられたらと、「動物と人の予防医学研究会(以下研究会に省略)」を2023年に発足しました。
動物と人の健康増進やQOL向上は、ワンヘルスの概念やSDGsとの関連から、科学的にも社会的にも重要な課題になっています。研究会では、各界多方面の方々の知識や技術を持ち寄っていただき、動物と人のインタラクションを介して、双方の健康増進、QOL向上を図る方法を探って行こうと考えています。
予防医学と動物用ウェルネスフードの確立を目指す
――もう少し具体的に研究会の活動について教えてください
中江先生 動物と人の予防医学研究会は発足して今年で3年目となりますが、活動には2つの目標があります。一つは「予防医学のプラットフォーム」の提供です。
動物と人のインタラクションをターゲットにして、新しい出会いのテーブルの様なものを作っていきたいと思っています。例えば、これまで人間を対象としていて新たにペット業界に参入する場合、どうしたら良いかわからない人は多いと聞いています。その逆に、これまでペットを対象としていて新たに人間の業界に参入する場合も同様だと思います。また、素材はあるけれどもその「加工」方法がわからない、逆に「加工」するのは得意だけれども素材を持っていない、という人もおられると聞いています。研究会ではそれらのリソースを持ち寄って、テーブルの上に広げて、いろいろな人に触れてもらい、新しいビジネスソースをつくる場にできたら良いと考えています。
もう一つは「動物用ウェルネスフード」の確立です。動物用の健康食品については、健康被害などの報道などもあり、飼主さん達が不安を感じています。特にSNSやネットで情報が氾濫していて、何をよすがとすれば良いかが全く分からない状態です。人間でも同様の「いわゆる健康食品」問題がありますが、人の場合、日本ではトクホや機能性表示食品などのように、公的機関が商品に対する信頼性を一定程度確保していますし、他の諸外国にも類似したシステムがあります。
しかし現在、動物に関して国内ではそういった公的な第三者認定に相当するものが何もないのです。せめて人と同じように、飼い主さんにも理解できるような一定のカテゴリーを作るべきだと思います。将来はもちろん国が関与するのが良いと考えますが、それに繋げるため、現在、研究会で「動物用ウェルネスフード」という概念を提唱し、その具体化を段階的に積み重ねて行っている最中です。
私自身は、ペットのウェルネスフードは人も食べられるものにできたらと考えていて、例えば人の機能性食品の中で、ペットも一緒に食べられるものができたら理想的です。カテゴリーを作る提案は動物のものだけれど、商品については人もペットも一緒に食べて、両方が健康で生活の質が上がるようなものが良いなと思っています。
個人的な意見ですが、食べ物に次いで、知育玩具やゲームなど、人とペットが一緒になってできる楽しい遊びの提案、さらに芸術・生活環境などに拡大していくことも期待しています。「ウェルネスフード」から発展して「ウェルネスプロダクト」までに行けば良いなと。
――7月26日に第二回学術集会が開催されます。今回の見どころについて教えてください。
中江先生 どの先生のご講演も期待できるものばかりですが、前回とは趣を変えて、招待講演として麻布大学の菊水健史先生に「イヌとヒトの互恵的関係」、また、特別講演として一般社団法人 人とペットの幸せ創造協会の越村義雄先生に「動物が人に与える恩恵と、共生社会の実現に向けて」と題した講演を予定しています。
さらに今回はシンポジウム・パネルディスカッションとして動物用ウェルネスフードの確立に関する現状と展望について、農林水産省 消費・安全局 蓄水産安全管理課の担当者様のほか、日本獣医生命科学大学や日本ペット栄養学会など産官学さらに臨床現場の先生方に自由闊達な討論をしていただきます。
講演も大変充実していて、公益財団法人実中研の大西保行先生には「再現性向上を目指したヒト肝実験細胞の開発」、帝京平成大学の福島亮治先生には「外科・集中治療における免疫栄養法」、同大学の小原道子先生には「健康支援と地域資源のつながり」、北海道文教大学教授で北海道大学名誉教授の宮下和夫先生には「生物資源の有効活用について」の演題を予定しています。
第二回学術集会は、7月26日(土)10時から、帝京平成大学池袋キャンパス、冲永記念ホールで開催いたします。興味を持っていただいたら、ぜひ参加していただければありがたく思います。末尾に御参加に関する情報を載せていただきますので、よろしくお願いします。
日本の動物福祉を担う動物看護師の活躍に期待
――講演では帝京平成大学の先生方の講演もあり、動物看護を学ぶ環境として、総合大学である点はとても優位だと感じました。
中江先生 動物医療コースでは単なる動物の看護だけでなく、社会全体の福祉にも貢献して欲しいという期待をもって指導しています。愛玩動物看護師は農水省と環境省のダブル所管なので、免許証には二つの大臣の名前が入っているのも、特徴のひとつです。
帝京平成大学では、一般的な動物看護に上乗せできる技術を身につけ、できれば信頼性があり、実質的な意味のある資格の習得を視野に入れることを奨励する体制が整っています。看護の枠を超えて、例えばペットと飼い主さんの両方のリハビリやマッサージが可能だったり、ペットと人の栄養指導ができるといった、一歩進んだ提案ができるような環境が整っています。
また、帝京大学グループでは関連事業として高齢者施設を運営しており、アニマルセラピーが行われています。学生はこうした場にも参加して、実践的な経験を積むことができます。こうした点は、帝京平成大学ならではの特徴かもしれません。
――最後に、日本の動物福祉に関する課題と現状について教えてください。
中江先生 よく、日本は欧米に比べると動物福祉に関して遅れていると言われますし、そういう側面があることも事実ですが、私自身の個人的な感覚では、欧米でも日本でも、動物が好きな人は福祉について正しく考え実行していますし、いろいろな面で、逆に日本の方が進歩的であるようなシーンも見てきました。もちろん、私自身が知らないだけで、日本だけがとても遅れている部分があるかもしれませんが、動物好きな人の意識は世界共通で、健康で幸せな生活が一日でも長く続くことを願っています。
一方で、日本では実際にペットを飼っている人の数が、欧米に比べて圧倒的に少ない。大雑把に言えば、日本では3割ぐらいの家庭でしかペットを飼っていません。欧米ではそれが倍の約6割いる。6割いたら、街を歩けば普通にペットと散歩をしているし、たとえばカフェに犬がいても当たり前の社会になるでしょう。3割だと少数派ですが、6割だと多数派です。
さらに「動物が好きな人」以外のカテゴリーには、1)嫌いな人(アレルギーなどがある場合を含む)と2)無関心な人、があげられるでしょう。日本では飼っている人が3割で、残りの7割が1)と2)。欧米では6割が飼っている人で、あとの4割が1)と2)です。日本人が特別、動物嫌いが多い国民性であるとは考えられないので、どちらも嫌いな人は同じぐらいの割合だとすると、差が出るのが無関心な人の割合です。
日本の動物福祉の課題はこの「ペット無関心層」の厚い壁を、どう乗り越えていくかにあると、私は考えています。動物に関して無関心で、興味が全くない。子どもの頃から動物を飼ったことが無く、仕事や子育てで忙しく、ペットを飼育する機会を失ってきた人に対して、動物福祉や動物愛護活動を説くのはとても難しいのです。
欧米ではペット同伴可能なレストランが稀でなく、ペットのメニューがある場合も多いのに、日本では公的に、また、客感情的に衛生面が問われてしまうなどのため、ペット同伴可能なレストランが限られ、その中でも店内に同伴できるのは稀で、さらにペットメニューを提供するためには高いハードルがあります。直ちに欧米並みにとは言いませんが、せめて「伴侶動物がいて普通」の社会を目指すべきだと、私は思います。
なぜペットを飼わなかったのかを聞くと、ペットがいる生活が普通ではなかったり、飼育コストが高くて飼えなかったり、また、核家族化・単身居住の増加などで飼育が難しかったり、高齢化で飼育できないと言う意見が多かったのです。こうした問題が課題としてあるならば、それをクリアしていくよう、努力していくことは可能です。
さらに、嫌いな人に飼育を促すことは難しいし、アレルギーの場合を含めてそうした人への配慮は必要だけれど、無関心層に呼びかけるためには、ペットと暮らすことで大きなメリットがある点を理解してもらうことだと思います。動物がいる状態が人にとっても健康で、とってもハッピーだということを、科学的根拠を示して言い続ける。ペットがあなたやあなたの家族の幸せや気分を良くしてくれる素晴らしい存在であることを、もっと声を大きくして言うべきだと思います。
――ありがとうございました。
医学博士 中江 大先生
日本毒性病理学会認定 毒性病理学専門家
Fellow of International Academy of Toxicologic Pathology
日本病理学会認定 病理専門医・病理専門医研修指導医
日本医師会認定 産業医
社会医学系専門医協会認定 指導医・専門医
内閣府食品安全委員会・厚生労働省・医薬品医療機器総合機構 専門委員
国際生命科学研究機構(ILSI Japan)・レギュラトリーサイエンス学会 理事
日本食品化学研究振興財団 評議員
日本癌学会・日本毒性病理学会 名誉会員、日本病理学会・日本毒性学会・日本がん予防学会功労会員
American Association for Cancer Research・Society of Toxicologic Pathology Emeritus Member
動物と人の予防医学研究会入会サイトはこちらまで

動物と人の予防医学研究会 第二回学術集会
学術集会参加申込ページ
情報交換会参加申込ページ
「動物用ウェルネスフード確立に向けたキックオフ」
[期日] 2025年7月26日(土)9時受付開始、10時開会 (予定)
[会場] 帝京平成大学 池袋キャンパス 冲永記念ホール
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2丁目51−4
文/柿川鮎子















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE

















