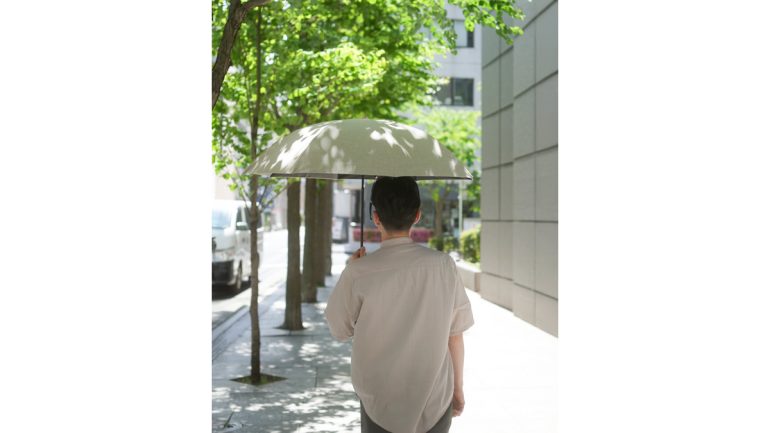筆者自身、「日傘はちょっと…」と説明できない感情で手に取らずにいた。しかし、さすがにここ数年の夏は暑すぎる。また、にわかに“日傘男子”が一般化し、周囲の目を気にせず日傘を使える環境になってきたと思う。
そんなわけで筆者も日傘の購入を検討し始めたわけだが、生まれてこの方30年と少し、日傘について調べたことがない。雨傘と何が違うのか、性能や機能、注目すべきポイントに皆目見当がつかなかった。
そんなわけで、1930年創業の日本の傘メーカー「小宮商店」の力を借りることにした。本記事では、小宮商店への取材をもとに、日傘の基礎からおすすめモデルまでを解説していく。

日傘の中にも種類がある? 特徴をチェック!
まず、雨傘と日傘で何が違うのか。なんとなく生地の素材が違うということは見当がつくが…? その予想のとおり、雨傘はポリエステルやビニール、高密度ナイロンなどといった化学繊維が多く使われている。一方、日傘は綿や麻などを採用することが多い。
そして、昨今人気を高めている「晴雨兼用傘」というハイブリッドなアイテムは、ポリエステル素材を使っていることが多いようだ。興味深いのは、小宮商店ではさらに細かくジャンル分けをしているところ。
「小宮商店の日傘には3つの種類があります。まずは晴雨兼用傘。こちらは天然素材の日傘に防水加工をしています。少しの雨であれば使用可能です。続いて雨晴兼用傘。こちらはポリエステル素材にUV加工をしています。普通の雨傘として利用しつつ、日傘としても使えるシリーズです。そして最後が日傘。コットンやリネン、シルクなどの天然繊維の生地を使用しています。記事の素材感を楽しんでいただけるシリーズです。アイテムによって、遮熱加工やUVカット加工を施したものや、生地の風合いを出すために加工を施していないものがあります」
ズボラな筆者は、使い分けの手間を考えると雨晴兼用傘を選びたい。しかし、小宮商店のWebサイトを見ていると、確かに晴雨兼用傘の生地は質がかなり良さそうだ。ファッションに合わせて選ぶ楽しみもありそうで迷う。
“日傘男子”は当たり前の光景に。そのきっかけは?
筆者の実感として、日傘を使う男性をよく見るようになってきた。では、傘メーカーとしてはこの潮流をどのように捉えているのだろうか。
「日傘は強い日差しから身を守り、体感温度を下げる効果があるため、熱中症対策に非常に有効です。以前は『男性が日傘なんて…』というネガティブなイメージがありましたが、最近では「熱中症対策を積極的に行っている意識の高い行動」として、ポジティブに捉えられるようになっています。年齢層も20代から高齢の方まで幅広いですよ」
最初のきっかけとなったのは、2019年に環境省が「日傘による暑さ対策」を推奨するポスターを百貨店などに配布しはじめたこと。
そして、2020年にはコロナ禍で「日傘でソーシャルディスタンスの確保」というニュースが話題になり、それも後押しになったという。それから約5年が経過し、ジワジワとムーブメントが広がってきたわけだ。
日傘を買う前に知っておきたい3つのこと
では、実際に日傘を購入するにあたり知っておくべきことはあるのだろうか。
まずは遮光率。遮光率は、主に可視光線をどれくらい遮るかを表す数値だ。数値が高いほど眩しさを軽減してくれる。眩しさは暑さにもつながるため、個人的にはこの数値に特に注目したいところだ。
ちなみに日本洋傘振興協議会(JUPA)の基準では、遮光率が99.99%以上の生地を使用した傘は「一級遮光」の表示が可能となる。各メーカーが独自に遮光率の高さを謳っているが、「一級遮光」の表示ができるのは上記の条件をクリアした製品のみ。商品購入の際はチェックしたい。
続いて紫外線遮蔽率(UVカット)。日焼けやシミなどの対策に関連する数値だ。個人的にあまり気にしてはいないが、高いに越したことはない。なお、小宮商店の晴雨兼用傘(一級遮光)の紫外線遮蔽率は、99.9%以上と超ハイレベルだ。
最後に遮熱性。これは赤外線をどれくらい通すかを表す数値で、JUPAは遮熱率が35%以上の生地を「遮熱効果あり」としているそうだ。これもまた暑さ対策に直結する数値なので、筆者としては赤丸チェック。ちなみに、小宮商店の一級遮光の傘はすべて遮熱率が50%以上だという。すばらしい品質だ。
小宮商店のこだわり。男性におすすめのモデルは?
上記の特徴に加え、生地の素材を理解しておくと、日々の扱いやメンテナンスにも役立つ。
「たとえば綿や麻、シルクといった素材の日傘は、夏以外の季節はクローゼットなどで洋服などと一緒に保管することをおすすめします。雨傘と一緒に保管しておくと、雨の湿気によってカビが発生してしまう可能性があるからです。また、生地の日焼けを避けるためにも屋内で保管してください」

では最後に、小宮商店の傘についてもまとめておこう。小宮商店は、手仕事ならではのつくりの良い傘を追求するメーカーだ。生地、骨、差したときの形、そして使い手の立場に立った差しやすい傘になるよう、細部までこだわって製造している。
職人が社内に在籍する点もユニークだ。師匠から弟子へ、さらにそのまた弟子へ。1930年から受け継がれてきた技と想いは、次世代へと確実に受け継がれている。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE