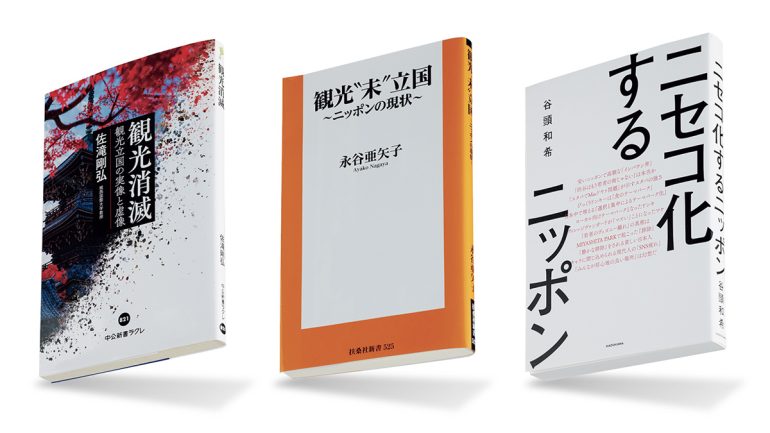
そもそもインバウンドは必要なのか
『観光消滅 観光立国の実像と虚像』
著/佐滝剛弘 中央公論新社 990円
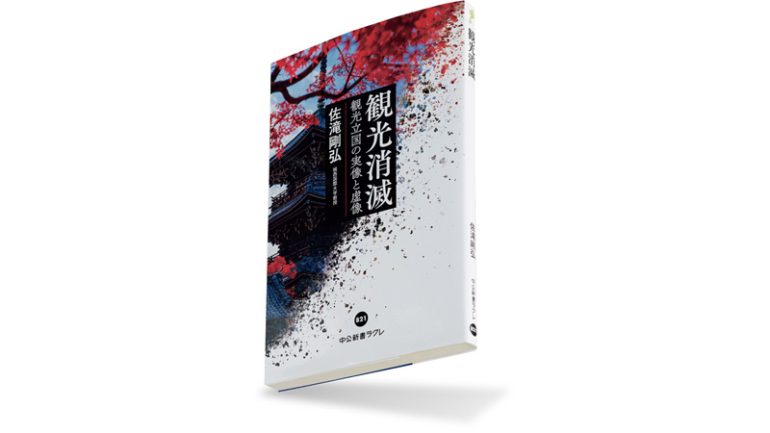
2024年の訪日外国人旅行者数は3687万人と過去最高を記録し、2025年は4000万人を超えると言われている。そして、政府のインバウンドの目標は6000万人だ。
人気の観光地では、電車やバスが大混雑、ホテル代は高騰、近隣住民とのトラブルも発生している。インバウンドの経済効果だけを目当てとした現在の「観光立国」のあり方を問い直すのが本書である。
外国人旅行客に埋め尽くされ、日本人観光客や地域住民が締め出されてしまう現状は、豊かな国と言えるのか。しかも、日本が旅行先に選ばれる最大の理由は「円安」であり、逆に日本人の海外旅行離れが進んでいる。
「観光立国という言葉は、先進国という呼称に疑問符がつき始めた日本の姿を覆い隠す魔法のベールに過ぎないのではないだろうか?」という著者の言葉に、改めて日本全体の問題に気付かされる。
インバウンドの波に乗れない地方の課題
『観光”未”立国 ~ニッポンの現状~』
著/永谷亜矢子 扶桑社 990円
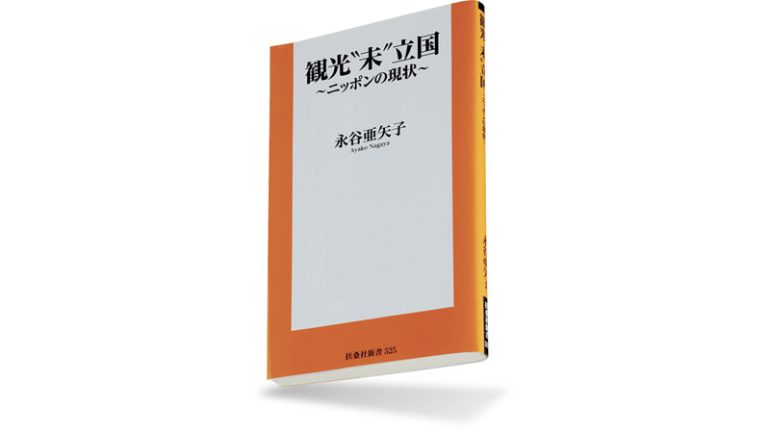
「インバウンドが増えているから、観光業界は儲かっているでしょ」と思うところだが、そうでもないらしい。首都圏や一部の地域は収益化できているが、特に地方は儲かっていないというのが現実だ。つまり、インバウンド格差である。
その根本的な原因は「マーケティング目線がない」ことだという。外国人旅行者のほとんどが、訪日前にネットで情報を収集する時代にSNSや公式サイトの情報が乏しく、いまだに観光案内所のパンフレットが情報発信の主体というのが地方の実態だ。問題は情報発信だけにとどまらない。お土産の包装デザインから、価格設定、外国人観光客が求めるコンテンツの理解まで、一言で言うと「センスが足りていない」ということになるだろう。
観光にまつわる様々な成功事例や課題から、観光に関わっていない人にも、マーケティングを学ぶ上で参考になりそうだ。
インバウンドによって排除される人たち
『ニセコ化するニッポン』
著/谷頭和希 KADOKAWA 1650円

人口約5000人の町に年間160万人の外国人観光客が押し寄せている北海道ニセコ町。牛丼2000円、ホテル1泊15万円、英語だらけの看板。「日本であって日本でない」ニセコと似た現象が、日本の至る所で起きているというのがテーマだ。
著者は「ニセコ化」を、「選択と集中」によってその場所が「テーマパーク」のようになっていく現象だと言う。特定の顧客層に刺さるサービスを集中することで、その場所には日常と切り離された「別世界」が作られる。その代表例が、東急歌舞伎町タワー、豊洲千客万来、大阪の黒門市場である。
こうしたニセコ化の負の影響が、顧客層以外の排除である。ニセコ化が公共という場で生じた場合、地域住民はなすすべなく排除される。観光客向けのサービスだと言えば、それまでだが、これからの日本のあり方を考えさせる一冊だ。
〈選者〉

bookvinegar
坂本 海さん
ビジネス書の書評メディア『bookvinegar』編集長。大学卒業後、半導体商社、ベンチャーキャピタルを経て、2011年bookvinegarを設立。これまで2500冊以上のビジネス書を紹介している。
撮影/黒石あみ(書籍) 編集/寺田剛治















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













