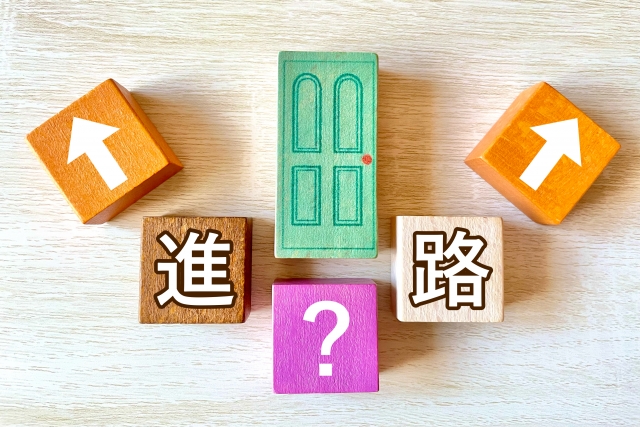
少子化が進み、定員割れする大学が増え、一般選抜以外の選択肢も充実してきた昨今、高校生の進路選択の状況はどのように変化してきているのだろうか。
リクルートが運営する『リクルート進学総研』では、高校生の進路選択を明らかにするため、進路選択行動の時期やプロセスを中心に、進路選択に際しての情報源、学校主催イベント、出願状況についての調査を実施したので、結果の概要を紹介しよう。
出願校数は引き続き減少傾向、オープンキャンパスは「第一志望群から“最終決定”への一歩を踏み出す場」に
「年内入試」(総合型選抜・学校推薦型選抜)での入学者が53.4%と過半数を占め、本調査では初めて「年明け入試」(一般選抜・共通テスト利用入試)の44.2%を上回る結果となった。
特に年内入試利用者のうち、第一志望校への進学率は67.1%(前回比で+7.6pt)と進学先の“早期決定”がより一般化している中で、合わせて進路選択の納得度も9 割以上と非常に高い結果となっている。
出願校数は2 回連続 で減少し、平均は2.4校(前回2022 年から0.3 校減)。一方で、今年の入学者は高校2 年生の5月にコロナ禍が収束した。
3 学年の累計では、オープンキャンパス参加率が90.3%と、2022年比10.4ポイント上昇。コロナ禍以前の2019 年(93.9%)とほぼ同水準まで戻った。
オープンキャンパスの位置づけも徐々に変化し、2019 年は「多くの候補から絞り込みの場」、2022 年はコロナ禍において「絞り込んだ第一志望の学校の中身を確認する場」、そして2025 年は「第一志望群から“最終決定”への一歩を踏み出す場」と移り変わっているようだ。
まとめ
18歳人口の減少が進み、特に2030 年代には全国的に一段と大きな減少が見込まれている中、2024 年度の私立大学全体の定員充足率は98.19%(日本私立学校振興・共済事業団)と過去最低。定員割れの大学が約6割と過去最多となった。
大学にとっては、早期における学生確保の重要性が増している。大学の年内入試枠拡大の動きもあり、進路選択の早期化が一層進んでいるようだ。こうした状況の中で、高校生側も進学先の決定を前倒しにする傾向が続いている。
進学先の決定の前倒しは進んでいるが、第一志望比率、進路選択の納得度が共に高いことから、安易に決めているというより、志望校に入りやすい状況になっていると言えるのではないだろうか。
また、コロナ禍収束後の高校2 ・3 年時のオープンキャンパス参加率は2019 年並みに戻っている。
出願校数は減少しているものの、2022 年と比較してオープンキャンパス参加時の第一志望率は減少し、参加校数は増えていることから、オープンキャンパスでの新たな志望校との出会いも期待しているようだ。
コロナ禍前・中・後でオープンキャンパスの位置づけは変化していると言えるだろう。
調査概要
調査目的:高校生の進路選択プロセス(行動・意識)の現状を把握する
調査期間:2025年3月1日~4月1日・インターネット回答締め切り
調査方法:インターネット調査
※アンケート依頼を郵送、記載のURLからインターネット回答
調査対象:調査開始時点で2025年に高校を卒業見込みの全国の男女22万9999人
令和6年度学校基本調査の「全日制・本科3年生生徒数(県別)」、「中等教育学校・後期課程3年
(県別)」を基に、リクルートが保有するリスト(※)より調査対象とする数を抽出
(※)リクルートが保有するリストとは、リクルートが運営する『スタディサプリ』会員リスト
有効回答数:3万9066人(回答率17.0%)うち、本プレスリリースでは大学進学者2万7362人が対象
※各年の調査はそれぞれ調査方法が異なるため、厳密には時系列比較できない点に注意を
※引用元:「進学センサス調査2025 」リクルート進学総研調べ
関連情報
https://souken.shingakunet.com/research/2010/07/post-e53f.html
構成/Ara















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE














