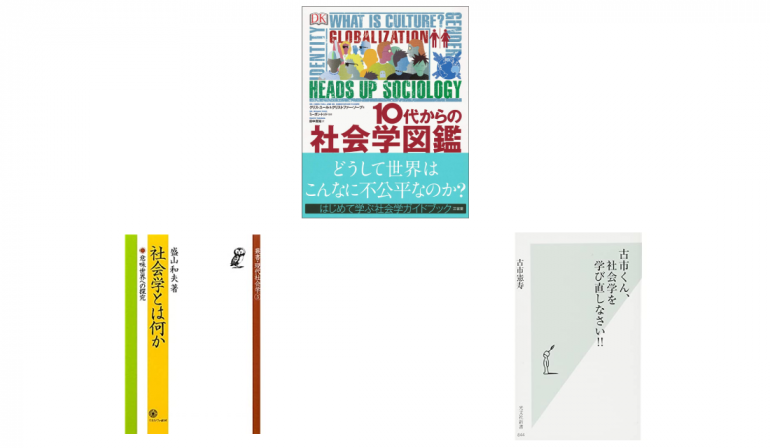「あなたが取り引きに応じなければ、われわれは手を引く」
「あなたはすべてを失う前に取引するべきだ」
トランプ大統領は、このように国際舞台でたびたび「ディール(取引)しよう!」と要求する。
確かに取引は理にかなった問題解決の手段かもしれない。とはいえ、何でもかんでも取引で割り切れるのか? と疑問を感じた方は少なくないはずだ。
人文科学の視点から解き明かすべく、社会学者の出口剛司先生に取材を行った。
出口先生は「ディールの実態には、相手によって内容が替わる『個別主義=ご都合主義的』なところがみられる。しかも、本来無条件に守られるべき正義も吹っ飛んでしまう危うさがある」と指摘する。はたして、その真意とは?
<取材協力>

出口剛司先生
社会学者。東京大学大学院人文社会系研究科教授。理論社会学、社会学史研究、現代社会の理論的分析に取り組む。戦後日本の社会学の遺産を再評価し、海外にも発信する。趣味はねこ(茶トラ5匹、キジトラ白1匹)。著書『大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる 』(角川文庫)、共著『猫社会学、はじめます』(筑摩書房)
「社会学」ってどんな学問?これから学びたい人におすすめの入門書6選
大学には「社会学部」「社会科学部」がある。しかし、これが一体どんな学問なのか、その疑問に明確に答えられる社会人は少ないかもしれない。曖昧で難しそうな印象の社会学…
「ディールしよう!」になぜ抗えないのか?

出口先生:興味深いのは、トランプ大統領が「ディールするべきだ」と口にすると、彼の支持者はもちろん、攻撃を仕掛けられている側も、そこに「正義」があると思わされてしまう点です。
筆者:そこなんです。破天荒なキャラのトランプ大統領ですが、決して滅茶苦茶なことを言っているわけではない。
ディール=取引って「相互の利益になるような交換条件で事を処理すること」(広辞苑第七版)ですよね。私たちの生活でも、ごく当たり前に行っていることです。
出口先生:資本主義社会は、多くの人が自由で平等な立場で取引することで、市場が広がり、生産力が高まり、みんなが豊かになるという仕組みです。
資本主義には、多くの人が正義だと信じる民主主義も、強く結びついています。
「ディールしよう!」は、そんな社会の基盤を表現しています。少なくとも表面上は、一方的に何かを押し付けたり、服従しろと言っているわけではない。
筆者:当事者間の自由意志に基づいて、平等な条件の下で行われるのが、ディールですよね。でなければ、「奉仕」とか「支援」とか、別の言葉になるはず。
出口先生:そう。「自由と平等」という、私たちが共有する基本的な価値観に結びついています。だから、「ディールしよう!」には抗いがたい力があるんです。
世界共通の資本主義と1対1のディールの違い
筆者:でも、何でもディールで解決!と言われると、モヤモヤが残ります。
他国から攻撃されて困っている国や、環境から貧しい暮らしを送る人たちを助けるのは、利益とは別に、みんなが考えるべきことではないかと…。
出口先生:そういう他者のための行動が、むしろ自分たちの自由と平等を侵害している、と考える人が増えています。格差社会や経済停滞が進み、自分たちも困っているのに、支援や奉仕をしている場合ではないと。
気持ちはわかりますが、私たちが大切にしてきた自由と平等の意味を考えてみるべきでしょう。ヒントは、「ディールしよう!」が説得力を持つ根拠である資本主義の成り立ちにあります。

ドイツの社会学者マックス・ヴェーバーは、「ユダヤ人が、どうして近代資本主義の中心にならなかったのか?」を論じました。ヨーロッパではユダヤの人たちは、古くから金融も商売も上手で、お金持ちが多かったんです。しかし、資本主義はキリスト教のプロテスタントの文化の中で発達しました。
ウェーバーが注目したのは、古代ユダヤ教の二元的な経済倫理です。彼らは仲間や家族、同じ宗教の人との間では、借金の利息を取らないなど、仲間同士の結束や連帯を大切にします。
一方で異邦人、知らない人や違う宗教の人とは、とてもシビアに取引すると言います。
筆者:「身内に優しく」は人情味があって良いと思う反面、外部の人は納得がいかないかも。宗教や関係性に影響される不平等なやり方が、世界共通のルールにならないのもわかります。
出口先生:そうなんです。資本主義は内と外をあからさまに区別するような倫理観とは相性が悪かった、というのがウェーバーの考え方です。
筆者:1対1で行われるディールは、共通のルールではなく、個別的な交渉で、近代資本主義より、ウェーバーのいうユダヤの考え方に近いですね。当事者が置かれている状況や関係性が、取引の条件を左右してしまうわけですから…。
出口先生:はい。力を持つ人や国が立場を利用して、不均衡な関係の中で利益を取ろうしても、不思議ではありません。これは当事者間では受け入れざるを得ないかもしれませんが、資本主義全体にとっては非常に都合が悪いことです。
自由と平等は、個別的に見るか、全体的、普遍的に見るかで、まったく性質が変わります。
筆者:なるほど。ディールの個別的な自由と平等は、私たちが大切にしてきた価値観とは、合致しない点があるとわかりました。資本主義の原理は、後者の普遍的な自由と平等ですね。
実はそこにズレがあるのだけれど、個別と普遍の自由・平等を区別できないから、明確に認識も指摘もできません。何でもディールで解決しようとすることに、モヤモヤする原因はそこですね。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE