
技術や社会構造などが激変し続けている現代社会において、新しい知識やスキルを習得するリスキリングはもはや必要不可欠。また世界有数の長寿社会を迎える中、セカンドライフをより豊かにするため、そして新たなキャリアをスタートさせるために、“学び直し”をしたいと考える人が増えている。
一方で「学び直しをしたいが、学校に通う経済的なゆとりや時間がない」という人や「何から始めればいいかわからない」「そもそも自分がどんなことに興味があるのかはっきりわからない」という人も多そうだ。そんな人に朗報。実はあの東京大学が、大学の正規の講義資料や講義映像を無償で公開しているというのだ。
東京大学の講義を、いつでもどこでも、無料で視聴できる⁉
高等教育機関における講義資料や関連情報をインターネット上で無償公開する活動を「オープンコースウェア(Open Course Ware、以下「OCW」)」と言う。東京大学は2005年に「知の開放」事業の一環としてOCWをスタートし、設立からの20年間に、1,900を超える講義を公開している。
いったいどんな人たちが、どのように活用しているのか、そしてなぜ東大がこのような取り組みをしているのか、東京大学のOCW活動団体「UTokyo OCW」について、東京大学 大学総合教育研究センター TL推進部門 OPユニットの石黒千晶准教授、蒋妍助教、学術専門職員・湯浅肇氏に話を聞いた。
視聴できるコンテンツは、大きく2種類
UTokyo OCWが一般に提供しているコンテンツは、大きく以下の2つ。
1)東京大学の学生が実際に受講している授業を収録し、講義資料とともに公開するUTokyo OCW
…講義資料と合わせてしっかりと学びたい人向き
…最近の人気コンテンツは、数理情報系の基礎・理論に関する講義、歴史・社会学・心理学などの教養・人文系の講義など

2)東京大学の学内で数多く開催されているシンポジウムや講演会の模様を動画で公開している東大TV
…興味のある分野を探したり、最新の動向についての識者の見解を視聴したりしたい人向き
…最近の人気コンテンツは、哲学・思想・倫理など人間の生き方や社会のあり方に関わる動画、歴史や文化理解に関わる動画、数学や科学の動画など

視聴者は誰?どれくらい見られている?人気のコンテンツは?
2024年度のデータによるとUTokyo OCWへのアクセス数は約203万人で、前年比35%増。東大TVの年間アクセス数は約38万人で、前年比33%増。東大TV YouTubeチャンネル登録者数は約165万人で前年比8%増だという。
利用者の多さにも驚きだが、特筆すべきはその視聴者層の多様性。UTokyo OCWでは18~34歳の若年層が約半数を占める一方、YouTubeでは45歳以上の社会人やシニア層が多数であり、学生だけでなく、自己研鑽を目的とする大人の学び直しのニーズにも応えていることがうかがえる。YouTubeやXのコメント欄で「とても興味深い」「面白い」「東大ではこんな面白い研究をしているのか」「学び直しができるのが嬉しい」などのコメントが多く寄せられているとのこと。
数理・情報系の人気講義は多いが、中でも公開当初から現在まで、長期間閲覧されている「情報数理科学VI」、「数理手法VII」。また、「数理・データサイエンス e-learning教材」も人気が高いそうだ。


また人文系では、各分野でよく知られている著書の著者や識者による講義も継続して閲覧されている。以下はその一例。
・近代以降体系化された世界史(ヨーロッパ中心主義)を捉え直す視点が注目されている「『世界史』の世界史」の著者である羽田正氏の講義
・「経済学者は冷静な頭脳と暖かい心を持たねばならない」の名言で有名なケンブリッジ学派の祖・アルフレッド・マーシャルの論文集「クールヘッド・ウォームハート-みえない社会をみるために」を翻訳した伊藤宣広氏の講義
・哲学・宗教・文芸等において「生と死の思想」がどのように展開してきたか、主として西洋を素材として考察する熊野純彦氏の講義「死すべきものとしての人間-生と死の思想」
「SNSでも『〇〇先生の講義をきっかけに新しい視点を得られた』などの声をお見かけします。とくに数学の基礎的な講義は、数式を実際に書き、解説してくれるということ、高いレベルの内容までカバーしていることが理由にあるかもしれません。また近年、『教養』の重要性が高まっており、哲学や人文系の講義を専門家ならではの分かりやすい語り口で聞いてみたいという需要もあるようです。東大TVでは『民主主義』『ロシア」』『ギリシア哲学』『数学』など、より現代社会や教養に直結するテーマが多くなっています」(学術専門職員・湯浅肇氏)
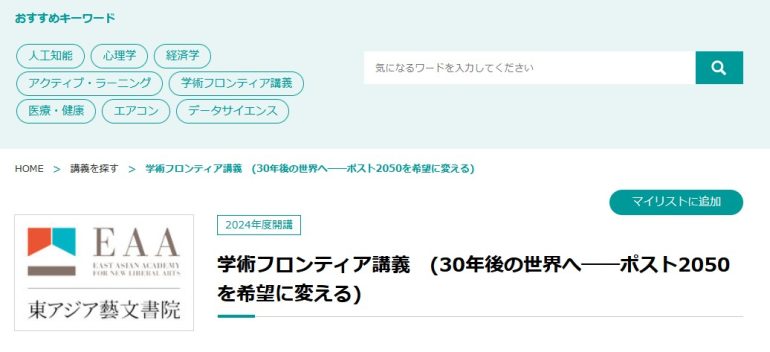


「高校生・大学生のための金曜特別講座」や「東京大学公開講座」、オープンキャンパスの模擬授業なども、知的好奇心を惹起するようなテーマや内容が多く、人気が高いとのこと。「これらの授業は、各分野の第一人者の先生方が分かりやすく噛み砕いて講演してくれるため、多くの人にご好評いただいています。またYouTubeからも視聴できるため、別の作業をしたり、隙間時間にも新しい分野に触れたり、興味ある分野の学びを深めたりすることが可能なのかもしれません」(学術専門職員・湯浅肇氏)
なぜ、授業料を払っていない人にも講義資料を公開するの?
だがそもそも、大学の講義は、授業料を払っている学生のためにあるはず。その貴重なコンテンツをなぜ、学生以外にも無料で公開しているのか。
「確かに大学は授業料を支払う学生に高度な教育を提供し、社会に送り出すことを使命とする教育機関です。しかしそれに加えて大学は、資料・人材の豊富な研究機関でもあり、高度な知を機関の外に開放・共有するという新しい形で、社会に貢献することも重要な使命です。私たちは東京大学に結集されている高度な知を学外に開放し、社会に還元することで、『学び』の機会を多くの人にもたらすことを目指しています」(石黒准教授)。
こうした活動の始まりは2001年、米マサチューセッツ工科大学(MIT)が講義の映像や資料をウェブ上で無償公開し、知識の共有という新たな価値観を大学教育に持ち込んだこと。MITの教授で、MITと東大、双方のOCW事業に関わった言語学者の宮川繁教授は、以下のように語っている。「MITでは社会に役立つことを目的として研究開発を行っている。教育活動を世界で役立たせる活動もMITの使命であり、その役割 をOCWは担う」。この理念が東京大学のOCWに大きな影響を与えているという。
「この取り組みは瞬く間に世界中へと広がり、日本でも東京大学を含む6つの主要大学(大阪大学、京都大学、慶應義塾大学、東京工業大学、早稲田大学)がOCWの理念に賛同しました。以降、国内外の誰もが質の高い大学教育に触れられる環境が整備されるようになりました。東大は日本のトップ大学の一つとして、知識公開による社会貢献が使命であると認識して、取り組んでいます」(蒋妍 助教)
この取材をするまで知らず驚いたが、確かに現在では講義の内容などを無料公開している大学は、東京大学以外でもかなり多い。「OCW」で検索するとわかるが、日本でもトップクラスの多くの大学がOCW活動をしてくれている。
もうひとつ驚いたのが、こうした取り組みは非営利で運営されていることがほとんどだということ。東京大学の場合は、10名ほどのスタッフで講義・講演動画の撮影、講義資料に含まれる著作物の権利の確認作業などを行っている。膨大な作業量なので各メンバーが何役もこなし、日々知恵を出し合いながら、小回りを効かせて動画や教材配信を行っているという。
正直、「非営利なのにどうしてそこまで」と思うが「東京大学という素晴らしい環境に恵まれ、コンテンツ公開にご理解とご協力をいただける教員の方々が多いことが大きな支えです。特に、私たちが嬉しい気持ちで振り返ることの一つは、長年ご協力いただいている教員の先生から、私たちのことを“プロ”として認めていただいたこと。また、東大TVやOCWの視聴者の方から、ご利用いただいているというお声をいただくこと、皆様の学びに役立てていただいたというお話を伺うのも大きな励みになります」(石黒准教授)
「知りたい」に年齢や場所は関係ない
現在、新規の講義シリーズや講演会の収録も企画しており、AIやデータサイエンス、STEAM、DEIなど、注目の集まっている分野の動画も公開を考えているとのこと。また、大学生や社会人の学びだけでなく、学校段階の子どもたちの学びに資するコンテンツ開発も目指しており、全国の中学校・高校や東京大学学校教育高度化・効果検証センターと連携した取り組みも計画中だ。
「大学で学ぶのは、若者だけではありません。今の時代、『学び直し』は当たり前になりつつあります。UTokyo OCWや東大TVは、そんなすべての『知りたい』という気持ちに応えるための扉です。いつでも、どこでも、誰でもアクセスできる知のライブラリー。それが、東京大学が目指す『知の開放』の未来です」(石黒准教授)
ネット環境さえあればいつでもどこでも視聴可能で、お金もかけずに一流大学の講義を受講できるのだから、大学教育が高嶺の花だった昔の人々から見たら、夢のような時代だ。「学び直しをする時間もお金もない」という言い訳は、もはや通用しない。
取材・文/桑原恵美子
取材協力/東京大学大学総合教育研究センター 准教授 石黒 千晶、助教 蒋妍、 学術専門職員・湯浅 肇















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













