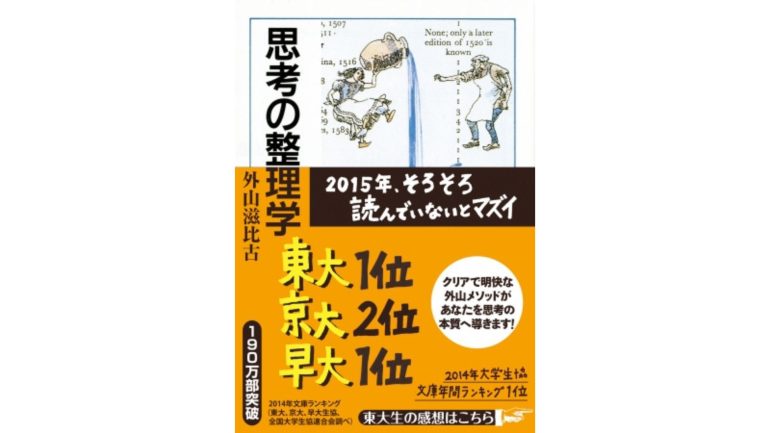
春になると日本中の大学で飛ぶように売れる本がある。それは、お茶の水女子大学名誉教授で英文学者の故・外山滋比古氏が著した『思考の整理学』だ。
はじめて筑摩書房から刊行されたのは1983年。今から40年以上も前の一冊にもかかわらず、令和の時代にも大学生を中心に読み継がれている名著である。一体なぜこの本は注目を受け続けているのだろうか?
『思考の整理学』とは
通称「東大・京大で一番読まれた本」として知られる『思考の整理学』は、お茶の水女子大学名誉教授で英文学者の外山滋比古による学術エッセー集だ。その人気は、40年以上経った現在でも衰えない。
特に近年における人気の火付け役となったのが2007年、岩手県盛岡市さわや書店での「もっと若い時に読んでいれば…」という店内ポップだ。この印象的なポップをきっかけに注目を受けた本書は、その後、2008年東大·京大生協年間書籍販売ランキングで1位を獲得。さらに、大学生協文庫年間ランキングで2018年、2019年、2020年と3年連続1位を獲得するなど、全国の大学生活から切り離せない一冊となっていった。そして現在(2025年5月時点)では295万部を超える大ベスト·ロングセラーとなっている。
慶應義塾大学生協でも大人気
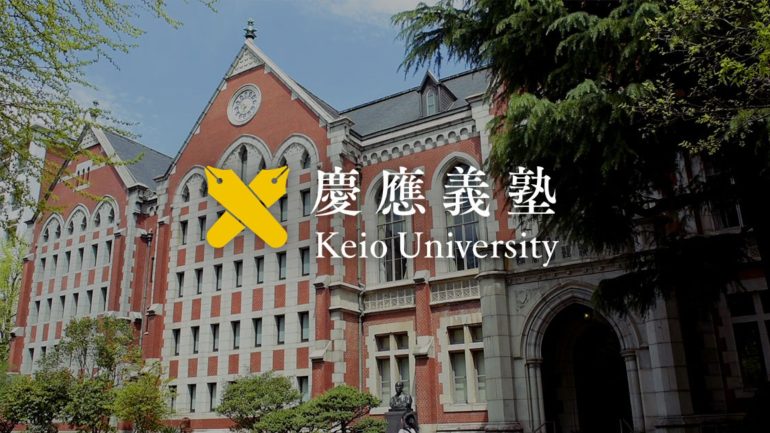
東京の名門私立·慶應義塾大学の生協でも『思考の整理学』は大人気のようだ。実際にブックコーナーに足を運んでみると、多くの学生がこの本を手に取っている様子がうかがえた。実際に『思考の整理学』を購入した学生に、なぜこの本を読もうと思ったのか話を聞いたところ、「今までの勉強とは違う本格的な学問の方法を学ぶため」という意見や、「レポートの執筆に行き詰ってしまいヒントを得るため」という意見が集まった。
さらには、『思考の整理学』が参考書として指定されている1,2年生向けのアカデミックスキル入門講座も開講されていた。講義の目標として「①学術的な手順を踏んだ情報収集の方法を学ぶこと、②各人が自身の研究テーマを見つけ、これまでどういう研究·調査がなされてきたかを確認すること」が示されており、その参考書として本書が指定されていることは注目すべきだろう。
実際に『思考の整理学』を愛読している私も、はじめてこの本と出会ったのは大学生協のブックコーナーだった。入学当初、受験の解放感に耽る暇もなく、履修登録やサークル選び、バイトなど、大量の情報に混乱している私の目を引いたのがこのタイトルだったのだ。
思考の整理学が教えてくれること
なぜ『思考の整理学』は私を含め多くの大学生を、特に難関とされる大学の学生たちを惹きつけるのだろうか。現役大学生でもある筆者は、この本が「学びの常識を根本的に突き崩す一冊」であることが理由だと考える。
本書で最も衝撃的なのは第一章だろう。それは、私たちが当たり前だと思ってきた「学びに対する価値観」が塗り替えられるからだ。
一般的な学校教育で評価される人物像を想像してみてほしい。教科書をしっかりと暗記しテストでは毎回高得点。しっかりと規律を守り、周囲から信頼される「優秀な人物」である。外山氏は優秀な彼らを「グライダー人間」と呼ぶ。先生や教科書に引っ張られて風に乗るように勉強するタイプの人間だ。
もちろんグライダー能力は大切な基礎である。しかし、グライダーの力だけでは空へと飛び立つことができない。つまり、自力で知識を得ることができない。だからこそ、自分自身の力で空へと飛び立つ「飛行機能力」を鍛え、クリエイティブで主体的な学び方を習得していかなくてはならない。これが本書の核となる主張だ。
小·中·高の一般的な学校教育では、むしろ良いグライダー人間となることが求められる。しかし、大学や社会生活で本当に求められるのは飛行機能力であり、ここに大きなギャップがある。このギャップこそが、大学生という学校と社会の狭間に生きる存在から『思考の整理学』が注目を集める所以なのである。この本は具体的な飛行機能力の鍛え方をたくさん教えてくれる。
外山氏によると、アイデアとはひねり出すものではなく、寝かせることによって、まるで素材が醗酵していくかのように生まれるものである。「見つめる鍋は煮えない」という諺が示しているように、一つのことをひたすら考えあぐねても良い結果は望めないのだ。むしろ、考えるべきことを一旦寝かせて、他のことを考える。すると、頭がリフレッシュされてクリエイティブな発想が生まれやすいという。
さらに外山氏は、アイデアが生まれやすい場所として、中国の偉人·欧陽脩が挙げた「三上」を紹介している。三上とはすなわち、馬上(交通機関)、枕上(ベッド)、厠上(トイレ)のことだ。これはつまり、考えるべきことを考えていない、少し気を抜いているときにこそアイデアが生まれやすいと言っているのだ。
本書では他にもたくさん思考のテクニックが紹介されている。いずれも大学生活において非常に有用なテクニックで、課題やレポートに躓いた時、私を助けてくれるヒントになった。40年前の学生も私と同じように本書から学びを得たと思うと非常に感慨深い。そして、これまでの時代でそうであったように、本書はこれからの時代も多くの大学生にとっての”必修科目”として読まれ続けることだろう。
取材・文/宮沢敬太















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













