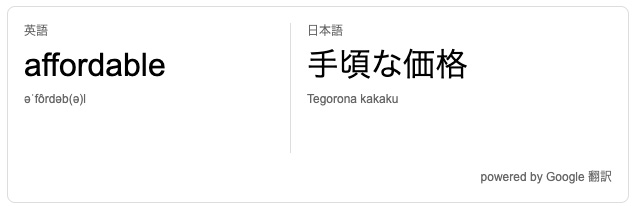「引っ越したいのにどこも家賃が高すぎて詰む」
「更新に合わせて家賃値上げのお知らせがキター!」
去年の年末頃から春にかけて、東京の友人たちの間でこんな悲鳴がよく聞こえてくるようになりました。
去年の夏、この連載のために書いた『理想の住まい探しはラクじゃない!過酷すぎる海外の住宅事情』というコラムで、各国で不足する住居問題と、住まい探しに奮闘する各国の人々の話を紹介しました。リサーチをしていた当時から対岸の火事とは思えませんでしたが、とうとう日本にも家賃高騰化の波がじわじわと広がっているようです。
【NIKKIのKINIなる世界】理想の住まい探しはラクじゃない!過酷すぎる海外の住宅事情
ロンドン市内の平均家賃は何と40万円台! インスタやピンタレストでつい眺めてしまう、海外のすてきな住宅コンテンツ。私が特に憧れるのは築古でも歴史の趣が残るガッ...
東京23区では平均家賃が過去最高値を更新しており、ワンルームマンションですら平均10万円近くもする事態に。建築材や維持管理費の高騰や、ファミリー層による賃貸物件へのシフトなどが争奪戦の主な原因のようですが、一体どこまで昇り続けるのか…?
世界は「住居不安定時代」に突入している
Z~ミレニアル世代が不安定な住居事情に追いやられている問題は今に始まったことではなく、2000年代後半の世界金融危機の頃から深刻化している問題です。EUでは2015年から2023年にかけて住宅の価格が平均48.1%も上昇し、世界の主要都市の多くでごく一般的な住宅で暮らすためには収入のおよそ半分(あるいはそれ以上!)を家賃やローン支払いに充てなければならない人が増えています。
アメリカでは手頃な価格の住居が不足するあまり、車中生活や友人の家を転々とするような仮住まいを送る若者は珍しくなくなっているようです。持ち家はおろか、就職のチャンスを得ても、車通勤のガソリンやスーツなどの必要出費を捻出できないという理由で辞退したり、収入を全額家賃に注ぎ込みながらカードローンで食料や日用品を買ったりするような人々のケースも報道されています。
家賃値上げに応じられずに退去を強いられる状態は“priced out”と表現されますが、家賃値上げによって安定した暮らしから突然放り出されかねない問題は世界各地で喫緊の課題となっています。そんな事情を背景に、ここ数年でよく話題になることが増えた単語が『affordable housing』。日本ではまだ「アフォーダブル」と聞いてピンと来る人は多くないかもしれませんが、今後おそらく注目と需要が高まる分野になるかもしれないので、今のうちに抑えておきたい用語です。
afford は何かをするための能力や余裕がある状態を意味する英単語で、アフォーダブル(affordable)は主に金銭的な文脈で「手頃な・手が届く」という意味を持ちます。身の丈に合った暮らしというのはもちろん人によりけりですが、主に低所得者や中所得者層にとって手頃な価格で居住できるように設計された住宅をaffordable housingと呼ばれています。
アフォーダブルハウジングの具体的な定義は地域の制度によって異なりますが、ただ家賃が安いだけでなく、託児所の併設や、住民によるコミュニティ運営など、多様な生活ニーズに合わせて設計されている事例も多数存在します。そんななか、注目が高まるアフォーダブル住宅の一つのモデルとして、ヨーロッパのある都市が注目の的になっています。
家賃に悩むことなく暮らせる『楽園』都市とは?
キャプション:ウィーン市街地に立つカラフルな公共住宅、フンデルトヴァッサーハウス。住民には外壁やバルコニーを自由にデザインする権利が認められている。
世界的な『住居不安定時代』にも関わらず、文化的で健康的な暮らしをアフォーダブルに送れることが当たり前の権利とされ、世界中から羨望の眼差しが向けられているのがオーストリアの首都、ウィーンです。
古くから音楽と芸術の都として知られるウィーンのもう一つの通称は『Renter’s Utopia(借用人のユートピア)』。市民の6割が公営住宅や市の補助制度の対象となっている住居に住んでいて、家賃の収入割合がたった2割ほどでありながらも広くて快適そうな公共住宅で暮らしを送る人がほとんどだそうです。マイホームとして購入しなくても家族内で部屋を譲渡できるという制度も、20世紀初頭の社会主義時代から続いているようです。
イギリスの新聞『ザ・ガーディアン』の取材に応じた26歳の修士課程の学生はウィーン中心部で596ユーロ(約96,484円)の家賃を払いながら太陽が明るく降り注ぐ建物の54平方mの部屋で一人暮らしをしている26歳の修士課程の学生のインタビューが印象的でした。一部の国や地域では公共住宅というと設備や治安の面でネガティブなイメージを持たれますが、個人的にはウィーンの公共住宅は最新のタワーマンションにも劣らない魅力が感じられます。(っていうか今すぐ引っ越したい)
ただ、うまい話には裏があるというわけではありませんが、従来の公共住宅には築古の建物が多く、ロマンチックな外観を誇る一方で設備の修理やメンテナンスにとても時間がかかるなどといったデメリットもあるみたいです。さらに抽選に参加するためには、ウィーンで最低2年間の生活実績があることが必要なので、今すぐウィーンに移住してこんな暮らしがしたい!と思っていた方はちょっとガッカリするかもしれませんね。(これを書いている私が一番ガッカリしている説)
オーストリアのGDPは世界28位ですが、最新の幸福度ランキングでは14位、そしてウィーンは『世界で最も住みやすい都市』に3年連続でランクインしています。暮らしの基盤となる住居供給の安定が充実した生活の大きな秘訣なのかもしれません。
ただ、ウィーンの公営住宅のシステムがこのようになるまで100年以上もの間、何度も制度の見直しや改善が行なれてきた歴史があります。日本でも東京都が民間企業と連携して「アフォーダブル住宅」の普及を促進する動きが始まっていますが、一朝一夕で叶うような事業ではないでしょう。生活の不安に苛まれることなく文化的で健康的な最低限の暮らしが一部の幸運な人の特権ではなく、誰もが当たり前のように享受できる社会を願うばかりです。
プロフィール
キニマンス塚本ニキ
東京都生まれ、ニュージーランド育ち。英語通訳・翻訳や執筆のほか、ラジオパーソナリティーやコメンテーターとして活躍中。近著に『世界をちょっとよくするために知っておきたい英語100』(Gakken)がある。
取材・文/キニマンス塚本ニキ
■関連情報
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2024/jan/10/the-social-housing-secret-how-vienna-became-the-worlds-most-livable-city
https://www.cbsnews.com/news/rent-homelessness-harvard-report-center-for-housing-studies/
https://ja.wikipedia.org/wiki/赤いウィーン
https://www.tokyo-np.co.jp/article/396624
https://www.npr.org/2025/04/06/nx-s1-5332142/doge-hud-affordable-housing-funding-air-conditioning-seniors















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE