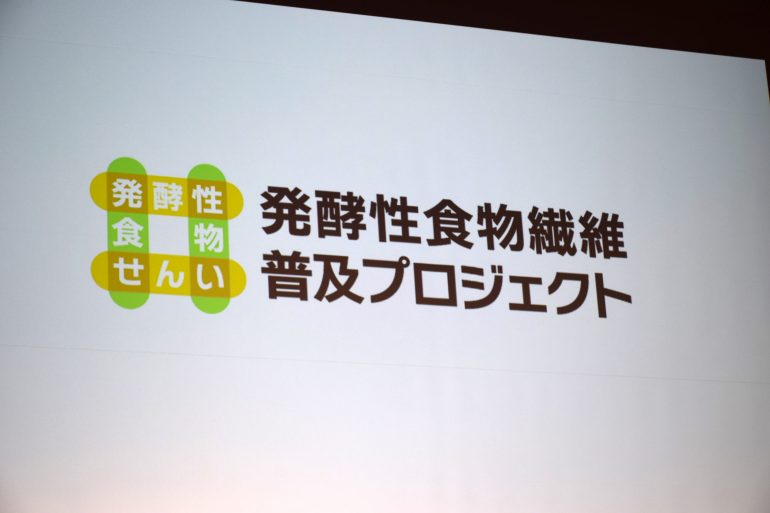人々がイキイキとした生活を送るウェルビーイング社会を目指すためには、個人が健康に過ごせることが重要になる。日々の生活の中で手軽に健康維持ができれば、より良い社会が実現できるかもしれない。
食物繊維には種類がある―腸内細菌のエサになる“発酵性食物繊維”とは?
株式会社Mizkan、日本ケロッグ合同会社、株式会社ドール、ナガセヴィータ株式会社、日清製粉株式会社、株式会社はくばく、フジ日本株式会社、ホクト株式会社の8社が、「一般社団法人 発酵性食物繊維普及プロジェクト」の発表会に出席した。同プロジェクトは、業界や企業の垣根をこえて発酵性食物繊維を普及していく取り組み。
昨今の腸活ブームもあり、「食物繊維」という言葉はヘルスケアの分野だけでなく一般的にすでに馴染みのある言葉になっている。食物繊維は食べ物の中に含まれ、ヒトの消化酵素では消化することのできない物質で、整腸作用など身体の中で有用な働きをする。玄米やトウモロコシなどの穀類、ゴボウやキャベツなどの野菜、サツマイモなどの芋類、大豆や納豆などの豆類、ワカメや寒天などの海藻類など、さまざま食品に含まれている。
食物繊維は水に溶ける「水溶性食物繊維」と、水に溶けない「不溶性食物繊維」に分けられ、水溶性食物繊維は食後の急激な血糖値の上昇を抑えたり、血中コレステロール濃度を低下させたり、腸内細菌を改善したりといった作用が期待できる。一方の不溶性食物繊維は便の量を増やしたり腸を刺激したりする便秘予防や、発がんリスクの軽減、水溶性と同じく腸内細菌を改善する作用も期待されている。こうしたさまざまな働きから、食物繊維は「第6の栄養素」とも言われている。
では、この「食物繊維」に「発酵するもの」と「発酵しないもの」があることをご存じだろうか。食物繊維の中には「発酵するタイプの食物繊維」が存在し、この発酵性食物繊維は腸内の細菌のエサになる。腸に関する研究が進む中で、腸内細菌が生み出す「腸内代謝物」がヒトの身体にもたらすさまざまな効果が明らかになっており、この「腸内代謝物」を作り出す要となるのが発酵性食物繊維だ。
「発酵」というワード聞くと、ヨーグルトやチーズやキムチなどの発酵食品を思い浮かべるが、発酵性食物繊維はこうした「発酵食品」とは別物だ。発酵性食物繊維は腸内に届いてから腸内細菌のエサとなり、腸内細菌に分解されることで短鎖脂肪酸などの有益な物質が作り出される。今回立ち上がった「一般社団法人 発酵性食物繊維普及プロジェクト」は、食物繊維の中でも「発酵性食物繊維」を普及していくプロジェクト。「食物繊維は、発酵性」をスローガンに、発酵性食物繊維を周知していく。発酵性食物繊維を取り入れた食生活を推進するため、「発酵性食物繊維+3グラム生活」を掲げる。
日本人の食物繊維目標量は25グラム「質を意識して『新しい腸活』を」
事務局長の西沢邦浩氏は同プロジェクトについて、「各企業さまや学術系の団体、この両者が連携し、業界企業の垣根をこえて、発酵性食物繊維を普及していくプロジェクトです」と説明。「食物繊維はまだまだ認識が不足なところがあります。特に今回取り上げる発酵性食物繊維は、腸の中の菌たちが食べることで発酵活動を行う代謝物質です。これが私たちの健康に寄与するため、発酵性食物繊維は(代謝の)プロセス非常に重要なエサという事になります。“腸内細菌のエサ”としての発酵性食物繊維の普及と摂取につながる商品や現場を作ることで、ウェルビーイングな生活に結び付けようというプロジェクトです」と語った。
2025年版の「日本人の食事摂取基準」では、WHOが提唱する食物繊維の目標量は25グラム。しかし日本では平均18.4グラムしか摂取できていない(※令和元年『国民健康・栄養調査』より)。そのため、プロジェクトでは食物繊維の摂取を増やすことを目指す。また「食物繊維=野菜」というイメージも定着していることから、豆類や果物、海藻、キノコ類など、幅広く水溶性食物繊維・不溶性食物繊維の発酵性食物繊維を摂取することを呼びかける。西沢氏は「これからは“食物繊維摂取の量”だけでなく、質を意識して、『新しい腸活』をやっていこうという考えで、今回のプロジェクトを始めました」と語った。
発起人のMizkan「発酵性食物繊維を広めていくことが“本当に良い社会”につながる」
この日はプロジェクトに参画した8社のうち、日本ケロッグ、ドール、日清製粉、フジ日本、ホクト、Mizkanの6社が、自社の取り組みについてトークセッションした。
同業他社にプロジェクトを呼びかけたMizkanの執行役員で日本+アジア事業CINOの石垣浩司氏は、「発酵性食物繊維をもっと広めたい、世の中に社会実装したいという事で、今回いろいろな方々にお声がけしてご協力いただく形になりました」と経緯を語った。
「我々ミツカンは昔から、『“そこに在るウェルビーイングな暮らし”をどう提供していくか』ということを、食を通して考えていく中で、1つテーマがありました。それは、『人は何を食べたら健康でいられるのか』ということ。そこを考えた『食の開発』がテーマでした」
石垣氏は各地域で“長寿のエリア”と呼ばれるエリアの食生活を調べ、「そのエリアが何を食べているかを見ていくと、私の当時の感覚では『ポリフェノールと食物繊維』でした」と、共通点を発見。食物繊維を調べていく中で、発酵性食物繊維にたどり着いたという。
「これが広まったら、本当にいい社会になるんじゃないかと思いました。そこから私の発酵性食物繊維生活が始まり、もう3年ぐらいになりますが、始めてから実感がありました。おそらくこれまで、100人以上の方に発酵性食物繊維を紹介してきましたが、これほど反響のあったものはないです。そこでこの発酵性食物繊維を、企業やメーカーの枠をこえて、一緒に広めていくことが、“本当に良い社会”を作っていくことにつながると思いました」
Mizkanでは、発酵性食物繊維を手軽に摂取できるブランド『Fibee』を展開。ワッフルやビスキュイ、ルイボスティーやカレーなど、さまざまなメニュー展開している。
 日本ケロッグの『オールブラン』とMizkanの『Fibee』
日本ケロッグの『オールブラン』とMizkanの『Fibee』
従来から発酵性食物繊維に注目していたという日本ケロッグは、1食あたり4.4グラムの発酵性食物繊維を摂取できる『オールブラン』を長年販売している。2024年からは発酵性食物繊維の発信により力を入れ、テレビCMでの「発酵性食物繊維」というキーワードの発信や、オールブランを使用した“ちょい足し”の食べ方を提案している。
 ヨーグルトにちょい足しした『オールブラン』と発酵性食物繊維がとれるバナナ、パン、ベーグル
ヨーグルトにちょい足しした『オールブラン』と発酵性食物繊維がとれるバナナ、パン、ベーグル
バナナを販売するドールは、バナナに含まれる発酵性食物繊維「レジスタントスターチ」の認知を広めるため、商品ラベルに「レジスタントスターチ」を表記。毎月7日を「Doleバナ活(R)の日」に制定し、店頭での施策も行っている。またMizkanのリンゴ酢や日本ケロッグのオールブランとコラボしたレシピや食べ方なども店頭で展開している。
業務用の小麦粉を製造している日清製粉は、多様な発酵性食物繊維を含む『高食物繊維小麦粉(アミュリア)』を開発。「レジスタントスターチ」の他、「フルクタン」や「アラビノキシラン」「アラビノガラクタン」「β-グルカン」が含まれている。
 日清製粉の『高食物繊維小麦粉(アミュリア)』とホクトのキノコ
日清製粉の『高食物繊維小麦粉(アミュリア)』とホクトのキノコ
その他にも、フジ日本は20年にわたって発酵性食物繊維の「イヌリン」を製造販売・研究開発。またエリンギやマイタケ、ブナシメジなど食物繊維が豊富なキノコを扱い、キノコの研究から販売まで行うホクトは、キノコに含まれる発酵性食物繊維の発信を店頭で強化していく。
西沢事務局長は「同じ発酵性食物繊維でも、訴求ポイントは違います。いろいろな発酵性食物繊維を多様な形で生活に取り入れることで、ウェルビーイングな社会が実現されていくと思います」と語った。
「私たちの身体の腸内細菌の数は、約30兆から100兆。私たちの細胞数以上の数があります。でも長い間、この腸内細菌たちがやっていることは分かりませんでした。最近のいろいろな研究により、腸内細菌たちの活動で私たちの健康が維持されているということが分かってきました。ずっと“ブラックボックス”と言われていたところを開けていく。その鍵こそが、この発酵性食物繊維だと思います。身体の中の未知だった腸内細菌に対して、どんなエサを与えて、どんな発酵活動をさせるか。そこが私たちの健康維持につながっていく。そうした新しい時代の鍵・健康の鍵として、この発酵性食物繊維を一緒に広げていきたいと思っています」
ウェルビーイング社会の鍵となる可能性を持つ発酵性食物繊維。食卓の中にちょっと意識して取り入れてみるといいかもしれない。
取材・文/コティマム















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE