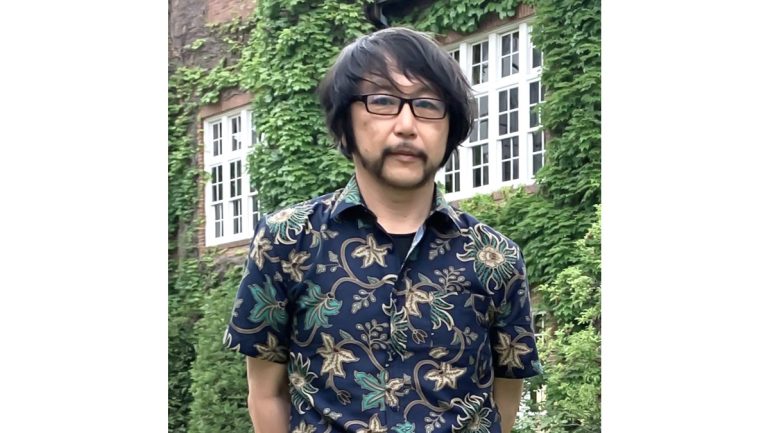スマホはもはや、私たちの生活の一部だ。あまりにも身近で、ふだん意識することはないけれど、私たちの振る舞いや考え方を左右している可能性は高い。
実際、スマホは人間にどんな影響を与えるのか? 人類学者の奥野克巳先生は、東南アジアの先住民プナンの現在に、そのヒントがあるという。今まさに、その社会にスマホが浸透し、人々の生き方をドラスティックに変えつつあるからだ。この3月に実施したフィールドワークのレポートも含め、詳しく話を聞いた。
奥野克巳(人類学者・立教大学教授)
1962年生まれ。北・中米から東南・南・西・北アジア,メラネシア,ヨーロッパを旅し,東南アジア・ボルネオ島で、焼畑稲作民カリスと狩猟民プナンのフィールドワークに従事。主な著書に、『何も持ってないのに、なんで幸せなんですか?』(吉田尚記との共著, 2025年), 『ひっくり返す人類学 ――生きづらさの「そもそも」を問う』(ちくまプリマー新書, 2024年) ,『はじめての人類学』(講談社現代新書, 2023年), 『モノも石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと』(亜紀書房,2020年),『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』(亜紀書房,2018年、のちに新潮文庫,2023年),主な訳書にティム・インゴルド『人類学とは何か』(共訳,亜紀書房,2020年)など。
1万年前の人類の生き方が現代に!?
奥野先生:プナンは、ボルネオ島(マレーシア領)の熱帯雨林に住む狩猟採集民です。半定住の生活で、居住地と狩猟キャンプを行き来しています。
彼らは農耕をせず、ほとんど野菜は食べません。イノシシやシカを獲って暮らしていますが、肉は保存できませんから、基本的には蓄財もしません。そのため、格差や身分の差がありません。
プナンの社会は「平等」が絶対的な原理です。個人所有の概念はなく、食べ物や道具はもちろん、感情や能力も共有するシェアリング・エコノミー。私は20年にわたって通っていますが、時計をあげても、バイクを壊されたときも「ありがとう」「ごめんなさい」という言葉を聞いたことがありません。というより、プナン語にはそれらの言葉がないのです。
感謝や謝罪を表明すると、貸し借りや上下関係がうまれます。彼らにとっては私の物もお金も、自分の物のように使って当たり前なんです。
他の地域でも、狩猟採集民は平等的な社会を築いています。農耕がはじまる1万年くらい前は、どの集団も似たような生き方をしていたのだと推測できます。
ただ、プナンも一部では近代の資本主義社会と接続していて、時々街へ出かけて、食糧や衣類、猟の道具を買ったりもしています。政府の支援策で、学校も無料で通えます。まあ、ほとんどの人が馴染めずに辞めてしまうのですが…。
スマホはどうやってプナンを虜にしたのか?
──そんなプナンの社会にも、とうとうスマホがやってきたわけですね。
はい。2021年にマレーシア政府が、プナンの居留地に、電力とWi-Fiを無料で開放しました。私はその時、コロナ禍で渡航ができなかったのですが、2022年の夏に行くと、プナンにスマホが普及しはじめていました。どんどん広がって、今では一家に一台程度に定着しています。
──彼らはスマホをどのように使っているのですか?
ほぼエンタメですね。使っているアプリは、YouTube、TikTok、いくつかのゲーム、そしてFacebookやチャットアプリのWhatsAppなどです。
元気な若者は、明け方まで大音量で音楽を聴いています。狩猟キャンプに出かけても、ダンスの動画を撮って遊んでいますよ。TikTokにアップするのだと言います。
文字が読めないので、インターネットで検索して、何かを調べるようなことはしません。また、そもそも電話や電気がありませんでしたから、通話もほとんどしません。最近はFacebookやWhatsAppで、東京にいてもつながれるようになりましたが、コミュニケーションはもっぱらボイスメモですね。
──私はSNSが登場した際、概念を理解するのも難しかったのですが、彼らは使いこなしているんですね。 でも、これまでプナンの人たちは、一部交流はあるにせよ、外部の社会に染まることなく、彼らの生き方を貫いてきたわけですよね。奥野先生と出会ったり、学校に行ったりして、経済的に豊かな人を見ても、その社会を全面的に受け入れようとはしなかったと。
そうですね。行くたびに、私の中にある資本主義的な常識を、粉々に壊してくれる。だからおもしろいんです。
──そんな彼らが、限定的にせよ、スマホを受け入れ、使いこなしているのはなぜなのでしょうか?
奥野先生:プナンの社会に埋め込まれた構造が強固なだけで、外部の文化を拒絶しているわけではないんです。基本的には新しいもの好きですから、スマホに興味を示すのもわかります。Facebookの使い方などは、学校や近隣の農耕民から吸収したのでしょう。
あとは、きっかけとしてエロは大きかったですね。2023年に行ったとき、男たちはエロ動画ばかりみていました。「カケ・スギオノを知っているか?近くに住んでいるのか?」など、聞かれたものです。
──カケ・スギオノ??
奥野先生:80歳を超えて現役のAV男優徳田重男さんのことです。
──それは、、、かなりの玄人ですね。エロには、文化やテクノロジーを超えて、人を突き動かすパワーがあるんですねえ。私にも覚えがあります…。
奥野先生:スマホが一家に一台になった最近では、さすがにそれはなくなりましたけどね。女性からクレームが入ったのだと思います。
ただ、動画やゲームなどで、手軽に労力をかけず快楽が得られるのは同じです。相当な中毒性があることを感じています。
スマホはプナンをどのように変えたか?
──でも、そんなにスマホにハマってしまうと問題がありそうですね。ウチの子みたいに、夜ふかしして翌朝起きられなくなりそうだし…
奥野先生:確かに、生活のリズムは変わりました。電気もスマホもない時代は、日が暮れるとやることがなくなり、8時半くらいには寝て、朝6時ごろ起きるような生活でした。
今では、夜スマホで遊んで、朝9時くらいまで寝ている人が増えました。
ただ、それは大きな問題ではありません。そもそも、彼らは学校や会社のスケジュールに従って生きているわけではなく、労働とそうではない時間の境界もはっきりしません。
好きなときに寝て、お腹が空けば食べる。そんな暮らしですから、寝坊くらいでは、誰も何も言いません。
──では、スマホが入ってきても、プナンに大きな問題は起こらないのでしょうか?
奥野先生:いえ、起こるでしょうね。前述の通り、プナンは共有の経済=シェアリング・エコノミーなんです。ごちそうのヒゲイノシシが取れれば、猟での働きや貢献度など関係なく、みんな均等に分けます。
私が日本から、自分の食糧を持ち込んだときも、断りもなく当たり前のようにみんなで分けてしまいました。それなのに、スマホだけは一家に一台で、近隣の家族と共有しようとはしない。つまり家族所有になっています。
──所有の概念が浸透して、共有の原則が崩れたわけですね。
奥野先生:そうなんです。そして、スマホはお金を出して買わなければ手に入れられません。1台4万円くらいなので、手が届かないこともない。
彼らは、そのお金を得るために、外へ出て賃労働をするようになりました。2024年夏に行ったときは、みんな忙しくなって、狩猟キャンプに連れて行ってもらえなかったくらいです。
──えーっ!? スマホのために、長く続いた狩猟採集の生活をやめてしまったということですか?
奥野先生:一部でそうなっています。そして、これこそ政府や企業の狙いだったのではないかと、私は考えています。
スマホをきっかけに「支配」が生まれる
奥野先生:ボルネオには巨大なアブラヤシの農場があるのですが、企業は国境を越えてインドネシアから労働者を連れてきています。近くに住むプナンが働いてくれれば、もっと効率よくビジネスができる。政府も潤うわけです。
そのために、学校へ無料で通えるようにしたり、医療サービスを提供したり、さまざまな形でプナンを支援してきました。しかし、それだけでは何十年かけても、肝心なところは変わりませんでした。スマホという手軽な快楽によって、ようやくプナンの社会が動きつつあります。
──ひとつの貴重な文化が、崩れてしまうのは残念に感じます。でも、それは当事者ではない外野の見方なんだと思います。政府も企業も、悪気があってやっているとは限らないですよね。
奥野先生:そうでしょうね。あくまでもプナンの人たちの意志で、資本主義経済に参加してもらい、ともに豊かな未来をつくろうとしています。政府や企業は、それがプナンにとっても良いことだと信じているはずです。
弊害としては、心の病が問題になると、私は見ています。20年プナンと交流して、心の病にかかった人をひとりも知らないのですが、社会が変容すれば、私たちと同じような問題が起こってくると。他の先住民社会が資本主義に組み込まれる過程で、数多く報告された事象です。
ただ、プナンがこれまでの社会と、どちらを選ぶかと言えば…
──物質的に豊かな資本主義社会ではないでしょうか。食べ物は手に入れやすくなりますし、病気や事故で亡くなる子どもや弱者は減り、集団はより繁栄するでしょう。そのことを実感すれば、心の病があったとしても、元の社会を選ぶのは難しいのではないかと。
奥野先生:最近の彼らをみていると、私もそう思います。そのこと自体に善/悪、正解/不正解はありません。
ただ、資本主義を主導する側(政府、企業)と、そこに参加するプナンの間に、「支配」と「服従」の関係が生まれることは確かです。好きなときに起きて食べるプナン流の生活はできなくなりますし、あれほど強固だった平等の原理もなくなるでしょう。
──お金の仕組みや仕事のルール、ヒエラルキーなど、彼らからすれば外部の価値観に従わなければなりませんよね。これまで絶対に入りこまなかった「支配/服従」という権力構造を受け入れることになる。
きっかけがスマホだとすれば、影響力は猛烈ですね。そんなものが自分の手元にあるという事実に、少し怖さを感じるほど…。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE