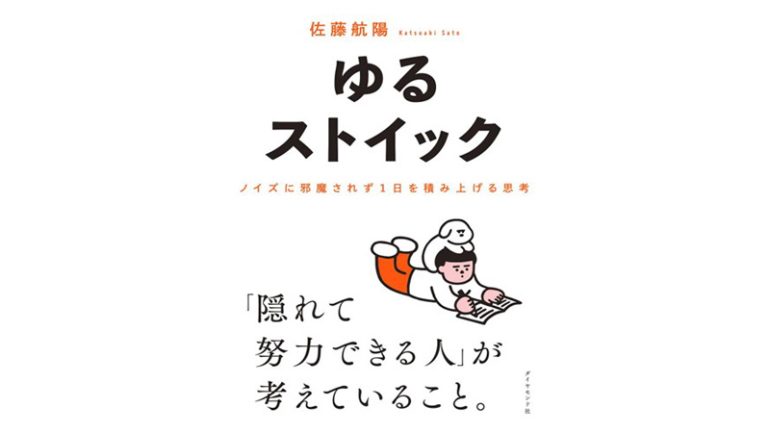実業家の佐藤航陽氏が上梓した『ゆるストイック ── ノイズに邪魔されず1日を積み上げる思考』(ダイヤモンド社、2025年)が売れている。
発売1カ月で5万部を突破する勢いで、読者からは「奥が深い」「今読むべき」と共感の声が集まる。「ゆる」「ストイック」という正反対のことばを合わせたタイトルが、日本語としてなんだかおもしろい!
本記事では、ライター・小越が国語学者の小野正弘先生に取材し、ことばの面から「ゆるストイック」現象を考察してみた。すると、意外な秘密が明らかに―――。
●小野 正弘
国語学者。明治大学文学部教授。専門は国語史。日本語の歴史、語彙、意味の変化を研究する。「三省堂現代新国語辞典 第七版」の編集主幹。著書に『オノマトペがあるから日本語は楽しい』(平凡社)、『日本語 オノマトペ辞典』(小学館)、『ケーススタディ 日本語の歴史』(おうふう) 、『感じる言葉オノマトペ』(角川学芸出版)、『くらべてわかるオノマトペ』(東洋館出版)など。
ホリエモンでもひろゆきでもない生き方
小越:「ゆるストイック」っておもしろいコンセプトだと思いました。
平成には「ホリエモン」こと堀江貴文さんに代表される、意識を高く持って、勝利と成長を追求する生き方がもてはやされました。「就職氷河期世代」の私は、そのど真ん中だと思います。
そこから競争社会が進むと、勝者と敗者が明確になり全体の経済成長も停滞する中で、競争から脱落する人が増えます。令和になるとコロナ禍も重なって、「ひろゆき」こと西村博之さんに代表される「がんばらなくていい」風潮が広がりました。がむしゃらにがんばるだけでもなく、がんばらずに休むだけでもない、新しい生き方の羅針盤が必要だ、というのが著者の主張です。
具体的なモデルとして、野球の大谷翔平さん、ボクシングの井上尚弥さん、将棋の藤井聡太さんなどを挙げています。彼らは勝負の世界に生きていますが、他者というより自分との戦いを突き詰めているように見えます。
自分のペースを極めて「ストイック」に守りますが、それを他人に押し付けたり、マウントを取ったりはしません。むしろ他人を尊重し、協調しながら、時として助けを受け入れる柔軟さも持っている。そうした余裕が「ゆるさ」だというわけです。
小野先生:自分の中では「ストイック」だけれど、他者との関係においてはある種の「ゆるさ」がある。そういう意味ですね。でもそれ、新しいですかね?
“自分に厳しく人に優しい。けれども、目標や仕事に対して妥協するわけではない”。こういう人物像は、古くから尊敬されていたんじゃないでしょうか。
小越:そう思います。ただ、前述の3人のように、そういう人が時代を象徴するような存在になっている、というのは、現代をうまく言い当てている視点のように思います。
小野先生:なるほど、確かにそうですね。ある有名俳優が、他の出演者を厳しく叱るスタッフをたしなめたエピソードを聞いたことがあります。一方、叱られたほうには、どのように演じればいいのかを、理解できるように伝えたとのことです。 この人は、「理想の上司」に何度も挙げられるような俳優です。まさに「ゆるストイック」なイメージが、評価されたのでしょう。
ことばのズレと組み合わせが絶妙のタイトルに
小越:私が商業ライターとして「うまいな」と思ったのは、「ゆる」「ストイック」といった対象的なことばの取り合わせです。私も記事のタイトルやキャッチコピーによく使う手なのですが、およそ結びつかないことば同士を結びつけると、新しい面白みがうまれるんです。「ギンギラギンにさりげなく」「うんこドリル」などですね。
小野先生:その効果はありますね。わかりやすい表現では「痛気持ちいい」のように、快感を表すことばをつけると、ふつう受け入れがたいことを受け入れられるようになります。むしろ、「痛い」ことで「気持ちいい」が、より強調されることもあるでしょう。
小越:まさに、おっしゃるとおりだと思います。
率直に言って、書籍の内容は「ゆるストイック」のタイトルからイメージしていたものとは違いました。
はじめは「自分に厳しくしすぎず、ほどほどにストイックに行こう」くらいのニュアンスかな、と思って手に取りました。前述のとおり、厳しい競争にさらされて「ストイックでなければならない」と、どこかで感じている私には救いが感じられたのだと思うのです。
小野先生:でも、本書の「ゆるさ」は自分に対するというより、他人に対しての「ゆるさ」なんですよね。だとすれば、微妙に意味がズレています。
小越:そうなんです。内容はとても参考になる話だったので、満足していますが、「思っていたのと違う」感はありました。「あ、ストイックにはやらなきゃダメなのね」と。
はじめから「令和のストイックな生き方術」とかだったら、内容には近いかもしれませんが、手に取ってはいなかったかも。内容がおもしろいことは大前提として、このちょっとした勘違いに、ヒットの秘密があるのかもしれません。
「ゆるい」と「ヤバい」の共通点
小野先生:国語学者としては「ゆるい」が、日常的で基本的なことばのひとつであり、それだけに日本人に深く根ざした感覚であることに、注目しています。「ゆるい」には、「ベルトがゆるい」「ゆるいカーブ」、といった物理的な意味(具体)と、「この会社の雰囲気はゆるい」「あの人は締切の意識がゆるい」など概念的な意味(抽象)があります。
小越:「ゆるストイック」は後者の概念的、抽象的な「ゆるい」ですね。
小野先生:はい。一般的に、ことばというのは具体から、抽象的な意味が派生していきます。例えば「煮詰まる」は、具体的には「何かを長時間煮て、水分がなくなる」状態を指します。転じて、「議論が熟して結論が出る状態に近づく」や、反対に「これ以上の展開が見込めなくなる」と、抽象的な概念を示すようになりました。
具体を指すことばが生まれてから、抽象の意味ができるまで、場合によっては数百年かかることも珍しくないんです。しかし、「ゆるい」(古語では「ゆるし」)は、具体的/抽象的な意味が、ほぼ同時に現れているようなのです。語源は「許す」と共通していて、奈良時代から平安初期にはみられることばなのですが、むしろ抽象的な意味のほうが早いくらいかもしれない。
小越:抽象的な「ゆるい」は、一定の基準に対して「余白」がある状態ですよね。良く言えば「余裕がある」となるし、悪く言えば「厳しさがない、甘い」となります。それが、昔から日本に定着していた概念だったということでしょうか?
小野先生:そうです。まさしく、良し悪し両方の意味(両義性)があるのだけれど、メタレベル(一段高いレベル、俯瞰的な視点)では意味は共通しています。
最近、よく似た形で進化したことばが「ヤバい」です。そもそもは、危機的な状況を表していたわけですが、最近ではおいしいものや、かわいいものに出会った時、ポジティブな意味で「ヤバい」と言うことがありますよね。
小越:俗語ですよね。年輩の方は、「喜んでいるのになんでヤバいんだ?」と混乱すると…。
小野先生:日本語の乱れ、のように思われがちですが、すごく高度で知的なことばの発展なんですよ。ネガ/ポジどちらの用法も、メタレベルでは「自分でコントロールできない」という意味で共通しています。
小越:確かに! ぼくも美味しそうなラーメンを見ると、自分で自分がコントロールできないほど興奮します! そう考えると「ヤバい」がぴったり。すごくうまいし、伝わる表現です。
小野先生:一見全然違う意味なのに、新しい「ヤバい」は説明不要で受け入れられていきましたよね。みんなが奥底で共有していた感覚を、言い当てたからです。古くは「ゆるい」もそういうことばで、現代まで1000年を超えて受け継がれています。
小越:私たちは良くも悪くも、すごく「余白」を大切にしているんですね。思えば、「ゆるキャラ」が広がったのも、「余白」がかわいらしさや、親しみやすさにつながったからかも。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE