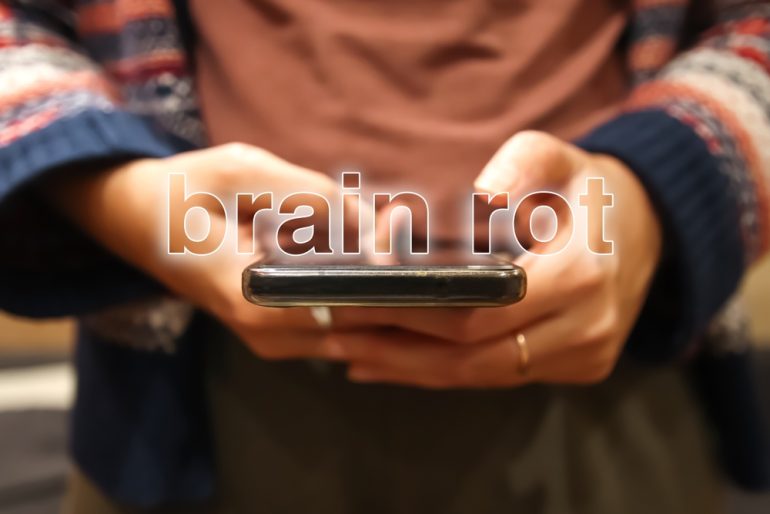
ネットによる影響が顕著な現代人を揶揄する「脳腐れ」という言葉が、世界中で注目されている。本記事では「脳腐れ」がどういう状態なのか、具体例やその対策も含めて解説する。
目次
「脳腐れ」という言葉を見聞きしたことはあるだろうか。字面のインパクトが強いこのワードは、2024年に世界中で注目を集めた言葉だ。脳腐れとは、ネットに没入するあまりに日常生活に支障をきたしている現代人の状態を表す。
本記事では、脳腐れの意味や話題となった経緯、具体的にどのような状態を指すのかを解説する。脳腐れを回避する対処法も紹介するので、ネットとの関わり方を見直して充実した日常生活を送るきっかけにしてほしい。
脳腐れとは?意味や話題になった背景
脳腐れは、ネットの世界に多大な時間を割いている現代人を揶揄するネットスラング。もちろん実際に脳が腐っているわけではないのだが、脳の本来の機能が低下していることを表現した言葉だ。
まずは、脳腐れについて、言葉の意味や注目を集めた経緯を解説する。
■脳腐れの意味は、精神や知能が低下している状態
脳腐れという言葉がはじめに使われたのは1854年。アメリカの作家ヘンリー・デイヴィッド・ソローの著書「ウォールデン」内だ。その際には、複雑な思想が軽視される当時の風潮を批判する文章で用いられた。
現在では「人の精神や知的状態の悪化、主にオンラインコンテンツの過剰消費の結果として見られること」と定義されている。また、そのような劣化につながる可能性の高いと特徴づけられるものも含む。
つまり、ネットばかり見ていて頭が働いていない状態と、人をそうさせる原因を表す。アニメや漫画で的外れな言動に対して「脳みそ腐ってるのか」なんてセリフが出ることがあるが、今や多くの現代人にそのような知能低下の可能性があると問題視されている。
■オックスフォード大学が「今年の言葉」に選んだことで話題に
脳腐れは、2024年12月にオックスフォード大学出版局が毎年発表する「Word of the Year(今年の言葉)」に選ばれた。今年の言葉はオックスフォード英語辞典の編集者たちによって選出されており、その年の世相や風潮をもっとも反映している英単語が選ばれる。日本でいう「新語・流行語大賞」のようなものだ。出版局によると、脳腐れという言葉の使用頻度は2023年から2024年の間に230%増加しており、注目度が高まっていることがわかる。
参照:オックスフォード大学 「脳の腐敗」が2024年のオックスフォード年間最優秀単語に
2024年、オーストラリアで16歳未満のSNS利用を禁止する法律が成立したことや、アメリカではTikTokが若者のメンタルに悪影響を与えていると訴訟問題になったことは記憶に新しい。SNSを始めとするネットとの関わり方については、長年多くの専門家が警鐘を鳴らしてきた。今や社会問題にまで発展し、2024年は各国で規制や対策の動きが見られた。
■脳腐れの読み方は「のうぐされ」
脳腐れは「のうぐされ」と読む。英語表記はBrain rotであり、読みはブレインロット。そもそも、脳腐れという言葉は英語圏で生まれたBrain rotを直訳したものだ。
脳腐れの原因と具体的な特徴
脳腐れは、主にオンラインコンテンツの過剰消費によるものだと定義されている。では、現代人は一体どのようなコンテンツを、どう消費しているのか。また、脳腐れとは、具体的にどんな状態を表すのか。脳腐れの原因と具体的な特徴について、詳しく解説する。
■脳腐れの原因は低品質なコンテンツの大量消費
脳腐れの原因はインターネットに多くの時間を費やすこと、特に低品質なコンテンツを大量に消費していることだといわれている。低品質なコンテンツとは、具体的に以下のようなものを指す。
- 意味のない短尺動画
- 取るに足らない情報
- フェイクニュース
- 炎上や釣りを狙った投稿
昨今の短尺動画の流行と誰でも簡単に情報発信できるSNSの浸透により、ネット上には低品質なコンテンツが蔓延している。これらのコンテンツは目を引く演出や万人受けする音楽で見る者を楽しませるが、知識や知恵として残る有益な情報はなく、刹那的だ。
さらに似たようなコンテンツが次々と表示されるため、何も考えずに無限スクロールしてしまい、気が付けば多くの時間を費やしている……。そんな経験がある人は少なくないだろう。
■低品質なコンテンツが脳に与える影響
深い思考を必要とせず簡単に消費できるコンテンツ、それらが次々と流れてくるSNSのシステムは、人をネットに依存させる。
そして、デジタルデバイスの長時間の利用により強いストレスにさらされることで、人は生物として高度な能力である「思考」を避けるようになる。原始的な状態に退行してしまい、論理的な判断や社会的に緻密な行動ができなくなってしまうのだ。さらに、ストレス状態が続くと精神状態の悪化も招く。
その結果、集中力や記憶力、想像力などあらゆる能力の低下が起こると懸念されている。
■脳腐れが疑われる人の具体的な特徴
脳腐れが疑われる人には、以下のような特徴が見られる。当てはまる要素が多い人は、知らず知らずのうちに日常生活に影響が出ているかもしれない。
- 社会活動の主軸がネットになっている
- 日常会話でもネットスラングやミームを多用する
- 集中力・記憶力・判断力が低下している
- フェイクニュースや陰謀論を信じやすい
- 精神状態が不安定
SNSでの発信やオンラインでの交流など、社会活動の場がネットに偏っている人は要注意だ。友人とのつながりや娯楽もすべてネットに頼っていると、より依存度を高めることになるだろう。
また、ネットの世界が中心になってしまい、日常会話での話題や語彙までもネットスラングやミームで構成されるようになると、SNSを利用しない人や世代が異なる人とのコミュニケーションが困難になる恐れがある。
集中力や記憶力、判断力の低下も脳腐れの特徴として挙げられる。その他に情報処理能力の停滞や注意力が散漫になるという指摘もあり、それ故に情報の正しい判断や取捨選択ができずフェイクニュースなどを信じやすい。
また、精神的な疲労や孤独を感じやすく、精神が不安定になりがちだ。
脳腐れを防ぐには?具体的な対策方法を紹介
 インターネットがあることが当たり前の生活を送っている現代人は、誰しもが脳腐れに陥る可能性を秘めている。脳腐れを防ぐには、デジタルデバイスとの付き合い方を含めた生活習慣の見直しが不可欠だ。具体的な対策方法を紹介するので、ぜひ参考にしてほしい。
インターネットがあることが当たり前の生活を送っている現代人は、誰しもが脳腐れに陥る可能性を秘めている。脳腐れを防ぐには、デジタルデバイスとの付き合い方を含めた生活習慣の見直しが不可欠だ。具体的な対策方法を紹介するので、ぜひ参考にしてほしい。
■日常的にネットの視聴時間を制限する
ネット、主にSNSの利用時間を制限し、だらだらと無限スクロールしてしまうような使い方を改めよう。そのためには、まず自分がどのくらいデジタルデバイスに触れているかを確認する。
スマホであれば本体の機能やアプリを用いて、自分の利用状況を知ることが大切だ。
また、現代人は時計の代わりにスマホを確認、スケジュールもスマホに入力と、あらゆることをスマホで代用している。スマホの画面を見る機会が増えると、ついでにSNSも開いてしまいがち。スマホでなくてもいい機能はスマホを使わないことも、対策方法の一つ。
■定期的にデジタルデトックスをする
週に1日はスマホを使わない、休日の午後はスマホの電源をオフにするなど、定期的にデジタルデトックスをすることも有効だ。
あらゆる情報や連絡の通知によるストレスから解放され、心身がリフレッシュする。急に生活習慣を変えることは難しいため、1日数時間の短い時間から始めるのもいいだろう。
■質の高いコンテンツを視聴する
脳腐れの主な原因は思考を必要としない低品質なコンテンツの消費であるため、情報を厳選し、有益で質の高いコンテンツを視聴すると良い。
自身のスキルアップにつながるもの、視野を広げてくれるものなど、情報としての価値が高いものを選ぼう。
■良質な睡眠をとる
睡眠中、脳は日中の活動による記憶の整理や傷ついた細胞の修復など、重要な働きを行っている。デジタルデバイスによる心身疲労の回復のためには、良質な睡眠をとることが重要だ。
寝床でもスマホを見ていてそのまま寝落ち……。こんな習慣がある人も多いかもしれないが、スマホから発せられるブルーライトは脳を目覚めさせ、睡眠導入を妨げてしまう。
そのため、寝る前1時間はスマホを使用しないことが望ましい。枕元に置いておくとつい手に取ってしまうので、寝室に持ち込まないようにするのもいいだろう。
■読書をする
読書は教養や知識が得られ、論理的思考力や読解力が養われる。他にも、記憶力や想像力の向上にもつながり、語彙が増えることで文章力や表現力アップも期待できるだろう。
脳がしっかりと働く活動の一つだ。脳腐れ回避のためには、脳を休めることと同じくらい、脳を働かせることが重要といえるだろう。
■他の趣味を持つ
ネットやスマホに依存しない趣味を持つことも推奨される。自然と触れる時間を増やしたり、友人とは実際に会う時間を作ったり、有意義な時間を過ごそう。
特に運動は、筋力や体力などの身体的な能力だけでなく記憶力や集中力の向上、認知症の予防などさまざまな効果が見られる。身体を動かす習慣がない人は、散歩から始めてみるのもおすすめだ。
※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。
文/編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













