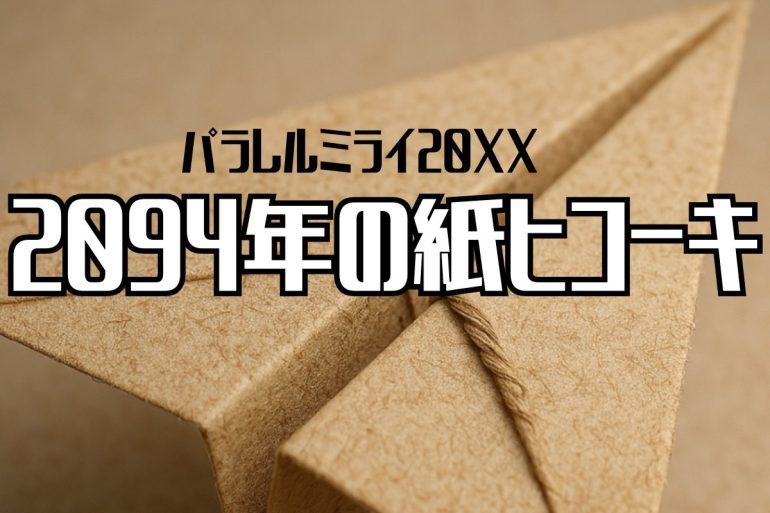
未来を予見するSFの世界を描く「パラレルミライ20XX」は、技術進化と人間社会の融合や衝突をテーマにした連載小説です。シリーズでは、テクノロジーによる新たな現実やデジタルとアナログが交錯する未来像を描きます。
パラレルミライ20XX『2094年の紙ヒコーキ』
ひとつ息を吸い込んでから、静かに吐き出す。この仕草が落ち着くのは昔からだ。私はこの街に暮らす高校生。名前はアオイ。どこにでもいる少年少女のひとりであり、どこか特殊な時代を生きる存在でもある。

西暦2094年、正確には「環境制御都市東京モデル区」と呼ばれるエリアに私はいる。21世紀半ばのAI大戦後に訪れた戦後復興とは別種の「先端技術と環境思想を取り入れた再生」を遂げ、新鮮な空気と緑と光に溢れている。高層ビルは外壁を覆うように植物が植えられ、街路樹には人工的に交配された花々が咲き、厳密な管理のもとで一見、自然と都市が共存しているように見える。
でも、本当は誰もが知っている。あらゆる緑や花々が、膨大なAI制御システムと人間のメンテナンスに支えられていること。制御がわずかに狂えば、すぐに枯れるか過剰繁茂して都市機能を脅かすかもしれないということ。外見上は華々しく美しいけれど、その裏側には無数のケーブルやセンサーが地中や壁面を這っているのだ。
けれど、不思議と不快感はない。暮らすうえではむしろ快適だ。ただ、その境界が曖昧だからこそ、ふとしたときに不思議な感覚がこみ上げる。この街に生まれ、この街で育った私は、はたして自然とは何かを本当に知っているのだろうか、と。
そんな街を歩くと、誰もが当然のように空間に指で何かを描いている。「空間書き」――私たちの世代にとっては、呼吸と同じくらい当たり前の脳波インターフェースとジェスチャーAIを組み合わせたテクノロジーだ。空中に文字を描けば宙に浮かび、指先で擦るとすぐに消える。検索だって全て空間のみで完結する。授業のノートも、友人同士の伝言も、あるいはアート作品すら、すべては空間書きによって描かれ共有される。
SkyCanvas(スカイキャンバス)というSNSは、空間書きを通じて投稿されたメッセージやイラストを瞬時にアップロードし、世界中のだれかに見せてくれる。いま描いたばかりの絵や文字が一瞬で共有され、「いいね」に相当するリアクションがホログラム状のアイコンで周囲を飛び回る。そんな景色が日常の至る所を賑わせ、色とりどりに染めている。
けれど私はときどき思う。これだけデジタルが充満しているはずなのに、どこか人々は息苦しく見える。自然と都市を統合した社会は確かに豊かだけれど、どこまでも繊細なバランスの上に成り立ち、常に微妙な制御が要求される。だから小さな綻びも許されない。誰もが、お互いを監視するつもりはなくても、どこか他人の足元ばかり気にしているように思えるのだ。
そんな私にも、毎日を普通に過ごす中での小さな楽しみがある。それは学園区の裏庭で午後のひとときを過ごすこと。表向きは「自然観察スペース」と呼ばれるそこは、AIによる最先端の風と水分量の制御システムが導入されていて、花々が咲き乱れ、ときには小さな昆虫や野鳥まで姿を見せる。いわば完璧にデザインされた庭園だ。でも私は、そこに一抹のほころびを探すことを密かに楽しんでいる。偶然交配された雑草が隅のほうで咲いていないかなとか、少しばかり過剰繁殖した苔が石畳の下で這っていないかなとか、そんなプログラムの網目を掻い潜った「生」の証を探すのだ。
ある日、いつものように裏庭でランチ代わりのサンドウィッチを頬張ろうとした瞬間、ふと視界の端に白いものが踊るのが見えた。はじめは空間書きのホログラムがバグを起こして、明度の低いゴーストになって漂っているのだろうと思った。けれど次の瞬間、それがホログラムでも電子ペーパーでもない本物の紙だと気づいた。
紙? 私たちがテキストや絵を実際に筆記具で記す機会はほとんどない。学校で配られる教科書や資料も、特殊な電子ペーパーが大半だ。博物館や歴史科目で見せてもらう機会はあるけれど、わざわざ紙を使うなんて芸術や伝統行事くらいなものだろう。それがこんな裏庭を舞っているはずがない。
私は慌てて芝生を横切り、その物体を拾い上げた。紙紐のような繊維でしっかり折り目を固定した、やや色褪せた紙ヒコーキ。

空間書きや電子ペーパーでは再現しきれない、独特のザラつきとやわらかい感触がある。その紙ヒコーキの先端の内側、折り込んだ部分に小さな文字があった。
「未来の友達へ。紙は、緑は、まだ残っていますか? これを飛ばしてくれたら、きっと届くはず……。2043年 ツジイ・ヨシト」
2043年? 今から51年前、21世紀半ば。私たちが子どもたちの頃から学校で学んできたAIを発端とした激動の時代のひとつ。まさか、その当時の手紙のはずがない、でも本当だと思わせるような紙の存在に私は思わず息を呑んだ。ホログラムでも、デジタルでもなく、私の手のひらには確かに本物の紙があった。本当に51年前の空気を吸い込み、誰かの手によって折られ、誰かの祈りや希望を抱えたまま2094年にたどり着いたのだろうか、そう考えると胸が騒ぐ。どうやって時間を超えたのかはわからない。でも実際にここにある以上、「そんなはずはない」で片付けることはできない。何より、あのメッセージが小さくも確かな声で呼びかけているように感じたのだ。もしまだ紙や緑が残っているなら、飛ばしてほしい、と。
私はその足でラボ棟へ向かおうとしたところ、ちょうど廊下でクラスメイトのネモとばったり出くわした。私が持っている紙ヒコーキに目をとめ、「それ、何?」と不思議そうな顔をする。
ネモとは普段、同じ教室で顔を合わせる間柄だが、こういう突拍子もない出来事には目がないタイプだ。私が「裏庭で拾ったら、51年前からのメッセージが書いてあって…」と説明すると、案の定、興味津々な様子で「一緒に見たい!」とついてくる。

そうして私たちは連れ立ってラボ棟へ向かった。そこには空間書きの先端技術やAIスキャナーが整備された部屋がある。ホログラムや3Dモデルのチェックだけでなく、リアルな物質を解析する機材も備わっていた。全校生徒が部活や課外活動で共同利用する場所で、少なくとも学校の機材としては最高レベルの研究設備といえる。紙ヒコーキを持ち込むなんて前代未聞だと思いつつも、なぜか胸の内が熱くなるのを感じる。まるで宝物を発見した冒険者みたいだ。
スキャナーを操作していたのは、科学部と工学部を兼部する上級生のサイ。ホロパネルに映るスペクトル解析の画面を見つめながら、サイが息を呑んだ。
「これは……普通の紙には存在しえない相関パターンを検知してる。局所的な量子エンタングルメントの反応があるなんて、どうやって埋め込まれたんだ……」
私とネモは顔を見合わせた。量子エンタングルメント、かつて理論上で議論されたものが、ここまで明瞭に観測されるなんて。でも確かに紙の繊維と何らかのナノ粒子が不自然に絡み合うような解析映像が映し出されている。
「まさか本当に過去に投げられた紙ヒコーキがもつれ合って、ここにあるってこと?」ネモが興奮を抑えた声で呟く。
私は不思議な胸の高鳴りを覚えていた。物理的には説明しにくくても、どうやら過去と未来を繋ぐ鍵になっているという確信のようなものが生まれてくる。
「わからないけど……それなら、これがどんな形で通信を媒介してもおかしくない気がする」私はそっと紙ヒコーキに触れる。
サイやネモ、そして周りにいた数名の仲間が手分けしてさらにデータを採取してくれたが、確たる結論はまだ出ない。ただ一つ言えるのは、この紙ヒコーキが時空を超えたメッセージを運んできた。そうとしか思えない根拠を秘めているということだった。
スキャナーに紙ヒコーキをセットすると、特殊な光が何層にもわたって走査を始める。インクの組成、紙の繊維構造、ナノ粒子の付着状況。スキャンするたびにモニター上のグラフが揺れ、そして見たこともない警告表示が出た。
「不明な電磁波パターン検出……解析不能」
居合わせた生徒たちも、これはただの紙じゃないと一様に顔色を変える。51年前にこんな高度なテクノロジーがあったとは思えないし、単なる手品や悪戯とは考えにくい。何か特別な物質が埋め込まれている? あるいは、時間を超えるための鍵が仕掛けられている?
私の頭にはいくつもの疑問が渦巻いていた。
「アオイ、これどうするの?」
ネモが、不安と好奇心が入り混じった声で問いかける。
「……わからない。でも、ここにこう書いてある。『これを飛ばしてくれたら、きっと届くはず』って」
私は紙ヒコーキの先端の内側に書かれた文字を読み上げ、どこか確信めいた気持ちを抱いた。ツジイ・ヨシトの呼びかけに応えるために、何かしなきゃ――そう思ったとき、私はたまらず紙ヒコーキにメッセージを綴った。
「西暦2094年、紙はまだ残っています。緑も、東京の街に溢れるほどあります。でも、そのほとんどはAIが管理する自然です。あなたの時代には、きっと誰かがこうして紙ヒコーキを折り、想いを託していたのですか?」
翌日、放課後の裏庭には私を含めて数名が集まった。紙ヒコーキは持参している。昼頃までは少し風が強かったけれど、AI気象制御システムからのデータによると、今の時間帯は風が最も穏やかで、気流の乱れが少ないらしい。
私はラボで解析した結果をふまえ、紙ヒコーキの翼を折り直して空力特性を可能な限り向上させた。しかし問題はどこに向けて飛ばせばいいのか。51年前に送られてきたものを、元の世界へ返すように飛ばすなんて、いったいどうすれば?
「もしかして、高い場所がいいんじゃない? 上昇気流とか、磁気嵐とか、いろいろ混ざるかもしれないし」
ネモの提案に従い、私たちは学園区の屋上へ移動した。まさにビルの外壁を埋め尽くす緑と花々の向こうに、太陽光が反射している。どこまでも整然とした都市風景を見下ろしながら、私はそっと構える。
「飛べ……!」
祈るように力を込めて投げると、紙ヒコーキはゆるやかに高度を落としながら、ふわりふわりと滑空を始めた。通常の紙であれば短時間で失速して落ちてしまうかもしれないが、この紙ヒコーキはまるで自律した意志を持つかのように、風を捉えてくれる。ビル壁面をかすめながら、ゆっくりと旋回し、さらなる上昇気流に乗る。そして私たちの視界の端を超え、白い軌跡を描くように遠ざかっていった。

私たちは長い間、それを見送った。雲の合間に消え、もう見えなくなっても、まだ空のどこかを飛んでいるような気がしてならない。どうか、そのままどこか向こうの時代まで届いてほしいと願った。
次の日も、その次の日も、世界は変わらないように思えた。いつも通り友人たちが空間書きで落書きを投稿し、バーチャルペットが走り回っている動画が拡散され、企業の宣伝がホログラム広告で流れている。
「やっぱり、ただの不思議な出来事で終わっちゃうのかな……」
そんな疑問を抱きつつも、私はどうしても諦めきれず、当時(2043年)のインターネットアーカイブを調べることにした。2094年のいまなら、数十年前のフォーラムやSNSの断片まで一気に洗い出せる。半信半疑のまま“ツジイ・ヨシト”と入力すると、意外な結果が表示されたのだ。
そこに記録されていたのは、2043年当時に運営されていた全く別のコミュニティサイトの書き込み。今ではすっかり閉鎖されて、名前を聞いてもピンとこないインスタグラムと呼ばれた古いサービスだ。
「紙ヒコーキが未来まで届くなんて、ありえないと思われるかもしれない。でも、きっと誰かが見つけてくれるはずだ。僕の時代にも緑はあるけれど、すべてが曇り空の下にある。だから、未来の澄んだ空気を信じたいんだ」
日付は間違いなく2043年。更新日時も不明なまま。でも、投稿文はまるで昨日のことのように生々しい。私はモニターを凝視しながら、胸の奥がざわつくのを感じる。
ツジイ・ヨシトはあの曇り空の下で、ただ願いを込めて書き込みを残したんだ。なのに、この2094年に届いた紙ヒコーキが、その声をリアルタイムで運んできたみたいだ。
「アオイ、見て……!」
隣で画面を覗き込んでいたネモが、さらに古い投稿をスクロールして指し示す。
「もし紙ヒコーキを見つけてくれたなら、ぜひ飛ばしてほしい。いつか必ず、僕のメッセージもそちらへ届くから……」
やっぱり過去と未来が繋がっているのだろうか。紙ヒコーキ自体は何らかの形で時空を往来し、そして2043年のツジイ・ヨシトは、このSNSに想いを綴り続けている。もちろん、普通の理屈じゃ説明できない。だけど、あの紙ヒコーキが存在する以上、「そんなはずない」とは言い切れない気がする。
さらに数日後。私はいつものように裏庭にいた。そこには最近、新しい花が咲いている。どこか荒野を思わせる白い花。遺伝子交配のカタログにも載っていない種らしい。教師たちはAI制御システムがバグを起こして新種を生み出した可能性を指摘していたが、私は心のどこかで、「ツジイ・ヨシト」から届いた贈り物なのではないかと思ってしまう。何の根拠もないただの妄想だけれど、それでもいい。
その夜、私は思いついてまた当時のSNSを開いてみた。すると、いまさら信じられないことに、新たな投稿が一件だけ増えているではないか。
「飛ばしてくれてありがとう。君たちが無事で、本当によかった。僕の時代にも緑はあるけれど、すべてが曇り空の下にある。きれいに見えるかもしれないけど、本当は心配や不安が絶えない。だけど、紙ヒコーキは未来に届くと信じてたんだ」
そこまで読んだとき、目が潤んでしまう。私たちが抱える不安も同じなんだと思った。どれだけAI制御や技術が進んでも、いつまた灰色の街に戻ってしまうかわからない。かつての2043年の人々も、同じように心を痛めながら、それでも前を向こうとしていたのだろう。
その後、いくら待っても再び書き込みは増えなかった。もしかしたらこれで最後かもしれない。それでも十分だ。51年前の人から時空を超えて届いた声があったと確かに感じた。その事実が、私の心の奥であたたかく燃えている。
私たちの都市は、これからも変化を続けるだろう。きっと簡単ではない。
でも私は、あの紙ヒコーキを手にした瞬間から少しだけ信じられるようになった。未来はすでにここにあって、過去と繋がっているのだ。小さな綻びの向こうに、私たち人間の持つ可能性と願いが隠されている。

ビル群の上空では、今日もたくさんのホログラムが踊り、情報が瞬時に更新されていく。電子の海に飲み込まれそうな洪水の中で、誰かがまた紙ヒコーキを折るかもしれない。もう二度と起こらないと思われた奇跡が、実はそう遠くない場所に潜んでいるのだ。
私にできることは、そこに宿る無数の思いを感じ取ること。たとえそれが儚くて脆いものでも、こうして言葉と記憶とが紡がれていく限り、きっと私たちは未来に手を伸ばせるはずだ。
2094年の空は、いま私たちの頭上に広がっている。けれど私たちが見上げているのは、もしかすると51年前の誰かが思い描いた未来の空そのものなのかもしれない。
私は大きく息を吸い込んで、ゆっくりと吐き出す。この街のテクノロジーも自然も、意外と悪くない。そんなふうに思えるようになったいま、私はしっかりと空を見上げている。
文/鈴森太郎(作家)
【アイデア資料】
https://www.riken.jp/press/2024/20240329_2/index.html















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













