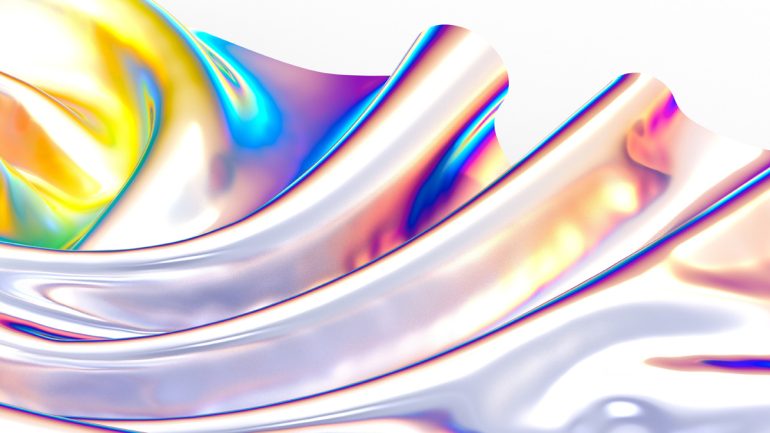
丸みのあるシルエットやデザインはどこか親しみがあり好感を覚えるものだろう。人が曲線を好む傾向は何に起因しているのか。新たな研究では我々の脳は審美眼を働かせている時に曲線に敏感になることが報告されている。
顔に対する審美眼が我々の曲線好きのルーツ
“曲線美”という言葉は主に女性の肉体のもつ曲線の美しさのことをたとえているが、特にボディラインではなくとも、これまでの研究や調査で人は直線的デザインのものよりも、丸みのあるデザインのほうを好む傾向があることが示唆されている。
また自然界には直線は存在しないともいわれ、美に敏感な者の多くは100年以上前から、自然の形態、絵画、室内空間に至るまで、人々のほとんどが直線的で角張ったものよりも、曲線的なものを好むことに気づいていたともいわれている。曲線を好む傾向はさまざまな文化からはもちろん、乳児や類人猿からさえも観察されているのだ。しかしこの曲線に対する我々の認識のどのような要素が、この普遍的ともいえる曲線の好みに繋がっているのかはこれまで明らかになっていなかった。
「今や脳を調べてこのプロセスを実際に動かしているメカニズムを観察できるという利点が私たちにはあります」とカナダ・トロント大学心理学部の准教授、オシン・ヴァルタニアン氏は表明し、脳画像データと曲率の計算測定値を使用してこの謎にに挑んだ。
ヴァルタニアン氏らの研究チームが2024年11月に「Scientific Reports」で発表した研究では、参加者の脳活動をfMRI(磁気共鳴機能画像法)で詳しくモニターした状態で実験を行っている。
実験では参加者に曲線と角張った室内空間の画像が提示され、参加者はそれぞれを「美しい」か「美しくない」かの美的判断を行い、その空間に「入る」か「立ち去る」かを選択した。
研究チームは、参加者が曲線的であると認識する際に敏感な活動を見せる脳の領域があることを発見したが、その活動はそのシルエットの美しさを判断しているときだけであった。
参加者がその空間に入るか立ち去るかを決めるよう求められた際には、その脳の領域は敏感な活動は見せなかったのだ。
この様相は我々が曲線を認識する状況によって、脳が曲線に反応する方法が異なることを示唆している。
参加者が曲線を知覚する際に反応する脳の領域である紡錘状回(fusiform gyrus)は、物体認識のような高次視覚処理に関与しており、顔の知覚にも敏感であるといわれている。
言い換えれば顔を認識することに特化した脳の領域が、建築空間を見るなどのほかの状況における曲線の認識においても敏感である可能性があることを示唆している。つまり我々の曲線への好みは顔の美的評価にそのルーツがあったことになる。
我々は進化人類学的に他者の表情から感情を読み取る能力を発達させてきており、顔の美醜についても優れた審美眼を持つ“審査員”でもある。我々の顔に対する優れた審美眼が曲線の好みの根源にあるとすればもはや本能に近い嗜好ということにもなりそうだ。
「芸術家やデザイナーははるか先を行っている」
研究チームはまた、参加者が曲線として認識した空間の画像が、同じ空間の計算上の測定値と必ずしも一致するわけではないことも確認することができた。つまり曲線の認識はかなり主観的であることになる。
「人が画像を見ると、3次元の心的表現を形成することは十分あり得えます」と研究の共著者でトロント大学のダーク・ベルンハルト=ワルター氏は指摘するが、もちろんそのような心象風景を2次元で数学的に測定することは不可能である。
ベルンハルト=ワルター氏は今後、研究者は画像のどの部分が人々が美的に心地よいと感じる曲線感覚に変換されるかについて、より広い視野を持つ必要があると説明する。
「芸術家やデザイナーは科学者よりはるか先を行っています。彼らはすでに有機的な曲線を使って、快適さ、美的喜び、家庭的な雰囲気を醸し出しています」(ベルンハルト=ワルター氏)
曲線の理解においてはサイエンスよりもアートやデザインのほうがすでに先に認識を深めているということだ。
たとえば道路標識には円型や四角形、ひし形のほかにも、逆三角形のものがある。そしてこの逆三角形の標識は「止まれ」や「徐行」など、潜在的な危険を示唆するメッセージが示されているのだ。
逆三角形に対する人間の認識として「鋭く尖った刃物」や「怒った人の顔」などの危険なものを連想させる「DPTS(downward-pointing triangle superiority)効果」があるとされ、これらの標識にはさらに強く注意を促す意味で逆三角形が採用されているといわれている。我々が特定のシルエットに対して抱く感情は、デザインの世界ではすでにある程度の経験則的な理解があるのだ。
共著者でトロント大学の博士課程の学生であるデララム・ファルザンファー氏は、この研究は神経科学者や心理学者の研究だけでなく、まさに芸術家、デザイナー、建築家、都市計画者にも関係があると述べている。
「空間が私たちの気分や認知にどのような影響を与えるかを理解すれば、私たちの健康にとってより良い環境を作り、多くの人々の現代生活の経験を豊かにすることができると思います」(ファルザンファー氏)
身の回りのデザインで暮らしを豊かにできる余地はまだまだありそうだ。アートやデザインの奥深さを改めて思い知らされる話題でもあるだろう。
※研究論文
https://www.nature.com/articles/s41598-024-76931-8
※参考記事
https://medicalxpress.com/news/2025-01-straight-edges-probe-brain-clues.html
文/仲田しんじ
疲れている時こそ「ゼルダ」や「マイクラ」をやったほうがいいという科学的根拠
困難な現実から逃げたり、負けを認めて敗走するなど“逃避”という言葉にはネガティブな意味合いがあるが、意外なことにメンタルに好影響を及ぼすポジティブな現実逃避があ...















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE














