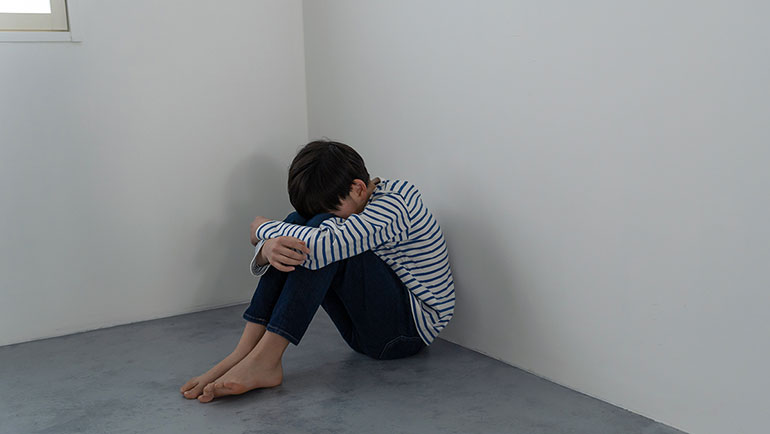
少子化が社会問題となって久しいが、その陰に隠れた問題の1つが、子どもの「不登校」だ。
文部科学省の最近の調査によると、不登校の小中学生は34万人を超えており、高校生も含めると約43万人に及ぶ。しかも、ここ10年余り、毎年増加しているという。
一体、子どもの世界に何が起きているのだろうか?
不登校の問題に詳しく、書籍『元・しくじりママが教える 不登校の子どもが本当にしてほしいこと』(すばる舎)を上梓された、一般社団法人家族心理サポート協会の鈴木理子(りこ)代表理事にお話を伺った。
今の子どもはなじめない学校の教育システム
――そもそも、なぜ不登校の子どもが増えているのでしょうか?
鈴木理子代表理事(以下、鈴木):文科省の調査では、不登校の理由のトップは「無気力・不安」となっています。ですがこれは、おそらく実情を反映してないと思います。この調査の質問紙に回答したのは、当事者ではなく学校の先生なのですね。先生の目線では、やる気がなさそうに見えるから、そういうふうに回答せざるを得ないのです。
不登校が増えている理由ですが、これは本当にたくさんの要素が重なって、今の状況が起きています。ただ、大きな理由はいくつかあって、その1つが、学校の教育システムが現代の子どもにマッチしていないことです。
日本は、縦社会の面が強いのですが、学校でもそうなっています。先生の言うことは絶対だという雰囲気や、クラスの統制をとるためにやむを得ないとはいえ、命令口調が苦しく感じる子もいます
さらに、校内では学業成績や偏差値が、最重要視される価値観になっています。他の多くの国では、勉強が得意な人は、勉強をやればいいというスタンス。それだけで勝ち組みたいな単一の価値観ではないのです。
今の子どもたちの多くは、その価値観にはなじめません。それで、すごく苦しい思いをしています。この点については、国が一丸となって取り組んで、変えていかなくはならないと考えます。
自己否定感が高い子どもが増えている
――社会は多様性や個性を認める考えが出始めていますが、学校はまだまだ閉鎖的という印象は、たしかにありますね。ほかに大きな理由として何がありますか?
鈴木:自己肯定感が低い子どもが多いのが、大きな要因になっています。諸外国と比較して、日本人の若者の自己肯定感の低さはダントツなのです。これは、自己否定感が高いと言い換えられますが、この性格傾向は不登校につながりやすくなります。
落ち込む子どもの様子を見てカウンセリングを受けさせようとする親御さんは多いのですが、自己否定感が強い子どもにとって、それを受けるのは、「自分が駄目だからこういうことさせられる」「周囲の人は、こんな自分を駄目だと思っている」と考え、さらなる自己否定感にもつながりかねないのです。
もちろん、ご本人から、受けたいという希望があれば、すごく有効だと思います。それは、既に自分で何とかしようっていう気持ちが出てきているから、ある程度エネルギーがたまってきているお子さんです。
でも、不登校の子の大半は、その段階までまだ行けないのです。
自己否定感をなぜ持つかと言えば、家庭での関わり方が要因の一つでもあります。子どもを否定するつもりなく、親心で躾をしているつもりが、子どもにとってみたら否定されたと感じてしまうことも多いのです。
核家族化も不登校の一因に
――学校に行けない子どもの増加は、社会の変化も関係するのでしょうか?
鈴木:核家族化が進み、夫婦一組あたりの子どもの数が減ったことで、過干渉な親が増えています。
親はみな、子どもの幸せを願っていて、子どもに愛情はあるのだけど、それが1人だけに向かってしまいやすいのです。
子どもが苦しむところを見たくないあまり、失敗させないように干渉するのですね。子どもの心は、思い通りにいかないことにどう対処するかを、自分で考えることで、育っていきます。最近の親は、その機会を奪ってしまいがちです。
カーリングママという言葉があります。カーリングでは、ブラシで氷を掃いてストーンを目指す場所に導きます。それと同じように、子どもの障害をあらかじめ取り除いてしまいます。
それだと、何かあったときに自分で立ち上がることができなくなります。
問い詰めることなく休ませる
――学校では、スクールカウンセラーを置くところも増えていますね。とはいえ、そもそも登校してこない子どもには対応できないでしょう。となると、親御さんの取り組みがとても大事になるかと思いますが、まず何をすればいいのでしょうか?
鈴木:子どもが不登校になれば、親としては、当然うろたえると思います。ですが、「何があったの?」「どうして学校に行かないの?」と問い詰めるのはいけません。
理由は聞かずに、休ませてあげてください。お話をするなら、体の具合はどうとか、今の状態を聞いてあげられそうだったら聞いてあげましょう。
子どもが、「このアニメ面白いよ」など言ってきたら、興味を示して、一緒にアニメを観たりといったかたちで、子どもと関わるようにしましょう。
今までは、情報収集だけのコミュニケーションになっていたのかもしれません。そういうのはやめて、子どもの話を聞くことに徹しましょう。そのうち、いかに子どもの話を聞いてこなかったかと、実感されるかもしれません。
親の思考のクセからの脱却が大事
――親自身の考え方を変える必要があるわけですね。
鈴木:はい。親が変わることが、なにより大事です。私は「呪い」と呼んでいますが、親御さんは、自分の中に根付いている「すべき」「せねば」という思考のクセに囚われているものです。例えば、「人は真面目に努力すべき」「困っている人には親切にせねばならない」といった倫理観ですね。
これは、まったくなくす必要はありませんが、自分の子どもに当てはめようとしないことが、とても重要なのです。子どもが、こうした思考に則った行動をしなくても、嘆かず、プレッシャーもかけないことです。
自分の心の中にあるルールや制限を見直して、新しくアップデートしていく。そして、子どもとの関わり方も見直していく。それで、親子関係が格段に良くなります。そうなれば、子どもは、生きるエネルギー溜め、自分で決めて、自分の力で歩き出していきます。子どもが学校に行き始めるだけではなくて、親自身がすごく生きやすくなります。
幸せな子どもが増えるには、幸せな大人が増えることが、なにより大事なのです。
お話を伺った方

鈴木理子さん
一般社団法人家族心理サポート協会 代表理事。株式会社ファミリータイズ 代表取締役。慶應義塾大学文学部を卒業後、国際線客室乗務員として8年間従事。研修講師として独立し、約15年でのべ2万人以上をサポート。
自身の三女が中学3年生で不登校になり、親子のコミュニケーションを徹底的に見直す。娘は元気になり、希望の大学に無事進学し、今は社会人として活躍。
「家族に笑顔を取り戻すKET理子塾」と題した親子心理・コミュニケーション講座を主宰。現在までにのべ約600名が受講。復学を目的にはしていないものの、受講後1年後の復学・就職率は約93%に上る。
最新の著書に『元・しくじりママが教える 不登校の子どもが本当にしてほしいこと』(すばる舎)がある。
・株式会社ファミリータイズHP:https://family-ties.jp/
取材・文/鈴木拓也
「優しさはないが厳しい親」と「優しさも厳しさもない親」の下で育つ子どもの特徴
成功者に共通する資質を子供の頃から育てる『Five Keys』の代表・井上顕滋氏によれば、ホンモノの自己肯定感を育むためには、「母性愛」と「父性愛」という異なる...
スポーツと学力の関係は様々な研究があるが、因果関係は不明瞭。モントリオール大学の研究では、10代前半で構造化された競技に参加した女子は、10代後半で学業成績が向...















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE















