
転職や引っ越し、あるいは結婚や離婚など人生を左右する決断は難しく不安がつきまとうものだが、何らかの指針となるものはないのだろうか。新たな研究では重大な意思決定の際に考慮すべき5つの重要な要素を特定している。
人生を変える決断における5つの主要な要素
どの服を着て出かけるのか、お昼に何を食べるのか、帰りにどこかに寄るのか等々、朝起きてから寝るまでの間、我々はさまざまな意思決定を行っているが、かつてのケンブリッジ大学の研究によると人は1日に最大3万5000回の決断をしているといわれている。
多くの些細な選択は何の躊躇もなく即断即決できるというものだが、その中には少ないながらもその後の人生を左右する重大な意思決定もある。重大な意思決定の多くは即断できなくとも無理はない。
判断と意思決定についてのこれまでの科学研究では、カードゲームをプレイするかのようなきわめて単純化、様式化されたタスクが適用されてきたのだが、そのような方法論で人生を左右する重大な意思決定を扱うわけにはいきそうもない。
独マックス・プランク人間開発研究所の研究チームが2024年11月に「American Psychologist」で発表した研究では、日常的な意思決定を超えた人生を変える決断を理解し、研究するための新しい枠組みが提示されている。
研究チームのシャハル・ヘヒトリンガー氏は、日常的な意思決定と人生を左右する決断の大きな違いは、判断の材料となる情報量であると説明している。些細な意思決定ではその気になれば判断材料となる情報を多く収集することができるが、人生を左右する決断では判断材料となる情報をじゅうぶんに集めることが難しく、それが判断を困難にしているのである。
そこで研究チームは視点の転換を主張し、すべての関連情報を手にしている非現実的なモデルを人生を左右する決断に適用するのではなく、意志決定にまつわる現実世界の特性を調べることからはじめた。
方法論的には自然言語処理を使用して現実世界の意思決定を分析する実証的な作業として個人の物語、書籍、オンラインフォーラム、ニュース記事など、さまざまなテキストデータを分析することで、人生を左右する決断における5つの主要な要素を特定した。その5つとは、
●矛盾する手がかり(conflicting cues)
●自己アイデンティティの変化(changes in self-identity)
●不確実な経験価値(uncertain experiential value)
●不可逆性(irreversibility)
●リスク(risk)
である。研究チームは、この5つの要素を考慮することで、人生を左右する決断において心理学的に妥当でわかりやすい意思決定戦略を提案している。
人生を左右する決断を下すための5つの戦略
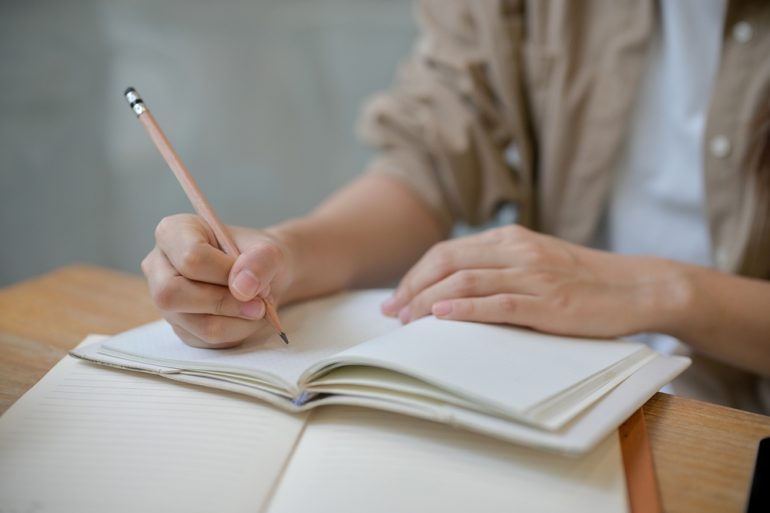
「矛盾する手がかり」は、競合したり両立できなかったり、そもそも比較できなかったりするものを選ぶことである。たとえば身の安全を第一に考えて移住を検討した場合、愛する家族を残していくという代償を伴うかもしれない。
価値観と手がかりが矛盾し比較できない場合に採り得る戦略の1つ「集計ヒューリスティック(tallying heuristic)」は、各選択肢の重要性を考慮せずに“好き嫌い”で比較を簡素化することである。
たとえば移住を考えている場合、移住によって起こり得る現象や事柄をリストアップしていき、その1つ1つを“好き嫌い”で評価して集計することである。“好き”のほうが多ければその決断はじゅうぶんにあり得るということになる。
「自己アイデンティティの変化」は、人生を左右する決断で起きる自分の変化である。結婚して親になったり、長年続いた人間関係を終わらせることなどの変化は、望ましい方へも、望ましくない方へも転ぶ可能性がある。
自己アイデンティティの変化への対策の1つ、「理想的な自己実現戦略(ideal self-realization strategy)」は、決断後に予想される変化した自分が理想的な人物であるかどうかを検証することだ。それが理想的な人物であれば決断を下すことができる。
「不確実な経験価値」は人生を左右する決断の後、何を経験するのかがわからないことである。長らく務めた職場を離れて転職する場合、新たな職場での生活が満足感につながるのか、それとも後悔につながるのは往々にしてわからないものだ。
このような不確実な経験価値を減らすための「他者の経験から学ぶ戦略(learn from others’ experiences strategy)」は、同様の体験をした人物から話を聞いたり、同様の選択に直面した人々を観察することで、起こり得る結果についての洞察を得ることができる。
「不可逆性」とは、離婚や移住などの人生を左右する決断の後、多くの場合は元の状態に戻すことが困難または不可能なことである。
不可逆性を伴う人生を左右する決断については「様子見テスト戦略(testing-the-waters strategy)」によって、完全なコミットメントを行う前に小さくて元に戻せるステップを踏んでみることである。たとえば新たな仕事を検討している場合、可能であれば副業や単発アルバイトなどで働いてみたりすることだ。
「リスク」も常に存在し、人生を左右する決断には報酬の可能性がある一方で、重大な身体的、感情的、社会的、または経済的損失の可能性もはらんでいる。
危害にさらされる可能性を最小限に抑えながら段階的に進めていく「ヘッジクリッピング(hedge clipping)」などの戦略は、リスクを効果的に減らすことができる。たとえば移住前に住居を確保しておけばセーフティネットが確保され、引っ越しがよりスムーズになり不安が軽減される。
人生を左右する決断はそうそうあるわけではないと思うが、もしも直面して考えあぐねている場合、この5つのポイントを考慮してみてもよいのだろう。
※研究論文
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Famp0001439
※参考記事
https://www.mpib-berlin.mpg.de/press-releases/transformative-life-decisions
文/仲田しんじ
2024年の国内出国者数は35.2%増!人間が旅行に行きたくなる心理「フォレスタルジア」とは何か
行ってよかった旅の思い出は後からしみじみと振り返ってしまうものであり、同じ土地にまた行きたくなったり、実際に再び訪れることもあるだろう。 このように過去に体験...















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE














