
大谷翔平選手が妻・真美子さんの第一子妊娠を報告したことでメジャーリーグの産休制度が注目を集めている。MLB選手が利用する出産立ち会い制度の概要と利用状況をまとめた。
目次
2024年12月、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、妻・真美子さんの第一子妊娠をSNSで報告した。めでたい一報に加えて、真美子さんの出産がシーズンに重なった場合、大谷選手がメジャーリーグの「産休制度」を利用するか否かにも注目が集まっている。
本記事では、メジャーリーグの選手が取得可能な「産休」の内容とMLB選手の利用状況、さらには、育児・介護休業法の改正によって浸透しつつある日本の男性育休取得についても解説する。
メジャーリーグ(MLB)の産休制度とは?
メジャーリーグには、選手のパートナーが子どもを出産する際に立ち会うための休暇制度が用意されている。「MLB版の産休」とも呼ばれるその制度の概要を見てみよう。
■メジャーリーグでは選手が出産に立ち会うための産休制度を整備
メジャーリーグには「父親リスト(Paternity List)」と呼ばれる休暇制度がある。父親リストに登録された選手は最低1日、最長3日間の欠場が可能だ。出産予定日に合わせて父親リストに登録されると、休暇を利用して我が子の出産に立ち会うことができる。
■MLB版産休「父親リスト」は2011年からスタート
父親リストは、2011年に導入された比較的新しい制度だ。アメリカの連邦法では日本の産休育休に該当する制度はなく、休業中の雇用保証や出産手当等の経済サポートは、州・民間企業が独自におこなっている。
そのため、メジャーリーグでも独自の制度を創設し、家族を大切にしたい選手の意思を尊重しているかたちだ。
メジャーリーガーの産休取得実績は?

それでは、メジャーリーグが導入した産休制度「父親リスト」は、どの程度利用されているのだろうか。主な選手の取得状況と産休に対する選手の考えを見てみよう。
■過去にはダルビッシュ有選手や鈴木誠也選手も産休を取得
メジャーリーグの「父親リスト」利用者は多い。日本人選手でも2022年にダルビッシュ有選手や鈴木誠也選手が利用。2023年のシーズン中には、大谷選手が所属するドジャースでも4人の選手(ムーキー・ベッツ選手、エバン・フィリップス選手、マックス・マンシー選手、ブルースター・グラデロール選手)が父親リストに入り、話題となった。
■大谷翔平選手はMLBの産休制度を利用するのか
大谷翔平選手がメジャーリーグの「父親リスト」を利用するかは、現時点(2025年3月下旬)では明らかになっていない。真美子さんの出産予定日も公表されていないが、春頃とする見方が強く、メジャーリーグのシーズン(毎年3月下旬~4月前半に開幕、9月末~10月初旬に閉幕)中に予定日が重なるのではないかと見られている。
大谷翔平選手が所属するドジャースには積極的に父親リストを活用する気風があるため、出産日がシーズンに重なった場合、大谷選手が産休を取得する可能性は高いと言えそうだ。
■メジャーリーグに日本のような育休制度はない
メジャーリーグの「父親リスト」は、出産の立ち会いのために最長3日間の選手の離脱を可能にするものであり、日本の制度に置き換えれば産休(産前産後休業)に該当すると言えるだろう。しかし、出産後に育児に専念するための休業保障、すなわち育休(育児休業)に該当する制度は存在しない。
また、メジャーリーグに限らず、アメリカ社会では育児のための休業保障が薄く、産後休業中の雇用は守られても、政府や事業主からの経済的支援(給付金の支給や社会保険料の免除)などはないのが一般的だ。
子どもが最長2歳になるまでの休業や給付金を保障している日本の産休・育休制度は、世界的に見ても非常に手厚い内容となっている。
日本の男性の産休・育休取得の現状は?
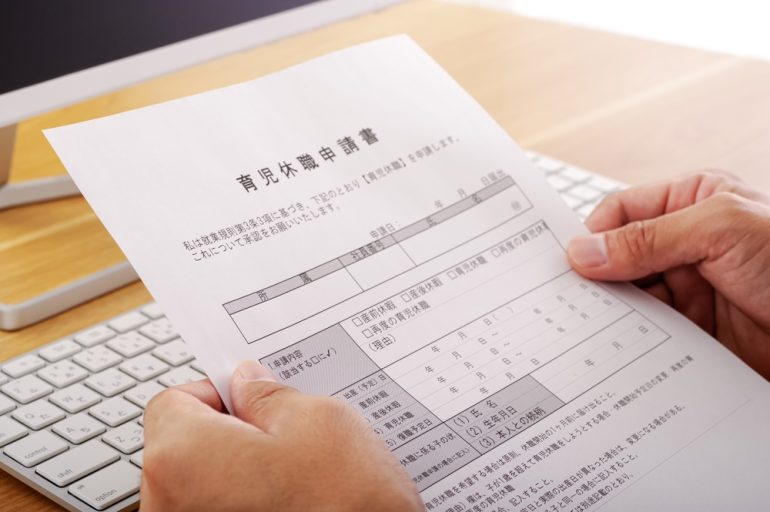
一昔前まで、日本における産休・育休制度の利用者は女性が大半だったが、現在は、若年世代が育休取得に積極的なこと、企業に男性の育休取得状況の公表が義務付けられていることもあって、男性の育休取得率が高まっている。日本の男性の産休・育休取得状況を見てみよう。
■2022年の「育児・介護休業法」改正で男性も産休の取得が可能に
子育てなどで時間的制約を抱える労働者の仕事と家庭の両立支援を進める「育児・介護休業法」は、時代に合わせて改正が繰り返され、段階的な施行が進められてきた。
2022年の改正では男性版「産休」が新設され、生後8週間以内に4週間まで2回に分けて男性が「産休」を取得できるようになっている(産後パパ育休制度)。
さらに2025年4月の改正では、従業員300人超の企業に男性の育休取得率の公表が義務付けられるようになるため(従来は従業員1,000人超の企業)、より広範囲に男性の産休・育休取得が広まると見られる。
■令和5年度の男性育休取得率は30.1%
男性の育休取得率は増加傾向にある。厚生労働省が発表した「令和5年度雇用均等基本調査」によると、2019(令和元)年度に約7.5%だったものが、2023(令和5)年度は30.1%と22.6ポイント上昇している。2022(令和4)年度の17.1%からも13ポイント増加しており、男性が育休を取得することに対する前向きな意識が芽生え始めていると言えるだろう。
政府は2025年度までに男性の育休取得率を50%まで引き上げる方針を打ち出している。
■世界的にも恵まれた日本の産休・育休制度
メジャーリーグの「父親リスト」は、試合に影響が出ることを覚悟した上で家族の出産に立ち会いたいという選手の意思を尊重した制度だが、手厚さという意味では雇用保障と経済支援がセットになった日本の産休・育休制度のほうがメリットは多い。女性のみならず男性も対象とした産休・育休は、世界的にも恵まれた子育て支援制度だ。
大谷選手の第一子誕生を楽しみに待ちながら、この機会に男性の育児参加や産休・育休取得について考えてみるのも良いだろう。
【育休制度利用中に受けられるおもな保障】
・休業保障……子が満1歳(保育所に入所できない等一定の場合は最長満2歳)まで。
・出生時育児休業(産後パパ育休)……子どもの出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間まで取得可能(2回まで分割取得可能)。育児休業とは別に取得できる。
・パパ・ママ育休プラス……両親がともに育児休業を取得する場合、子どもが1歳2か月に達する日までの間で1年間休業可能。
・育児休業給付金……出生日の180日目まで休業開始時賃金日額の67%相当額、それ以降は50%相当額を支給。非課税。
・出生後休業支援給付金(令和7年4月から)……産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を14日以上取得すると、休業開始時賃金日額を取得日数分×13%を支給。非課税。
・免除されるもの……社会保険料(厚生年金、健康保険)、雇用保険料、所得税
※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。
文/編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













