
パスワードは個人情報を守る重要なセキュリティ要素だ。しかし、時代とともにパスワードのハッキング技術が発展しているため、漏洩には気をつけなければならない。この記事では安全なパスワードの作り方を解説する。
目次
安全なパスワードの作り方は、個人情報を守る重要な知識のひとつだ。
パスワードを作る際、自分の名前や誕生日、連続した数字など、推測されやすい安易な組み合わせにしていないだろうか。昨今では、有名企業もハッキングの被害に遭う事件が相次いでおり、パスワードの管理には一層気をつけなければならない。
本記事では、安全で覚えやすいパスワードの作り方を解説する。ぜひ今すぐに、現在使っているパスワードを見直してみてほしい。
安全なパスワードとは
「安全なパスワード」とはよく聞くが、実際どのようにすれば安全と言えるのだろうか。
内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が提唱する「サイバーセキュリティ対策9か条」によると、長く複雑に、なおかつ他と使い回さないことが安全なパスワードを作る重要なポイントだという。ここでは、パスワードを作るコツをもう少し噛み砕いて解説する。
■安全なパスワードを作るコツ
NISCが提唱するサイバーセキュリティ対策9か条における、安全なパスワードの定義をまとめると以下の通りだ。
- 長く
- 複雑に
- 使い回さない
ハッキングの代表的な方法のひとつに、組み合わせできる文字をすべて組み合わせてログインを試す「総当たり攻撃」がある。総当たり攻撃では、パスワードが短いほど開錠までの道のりが短くなり、安易にハッキングできてしまう。
このため、まずはできる限り長い文字列にし、桁数を増やしてパスワードを作ることが重要だ。
また、単語や人物名とわかるものではなく、アルファベット、記号、数字を不規則に組み合わせて、複雑な文字列を作るのも効果的となるだろう。
なお、パスワードを使い回すと一度のハッキングで被害が拡大してしまうため、使い回しはNGと言える。
覚えやすい安全なパスワードの作り方
「覚えやすく安全なパスワードの作成など不可能ではないか」と心配する人もいるだろう。
もちろん、誰もが覚えられるようなパスワードは安全とはいえない。しかし、自分なりにパスワード作成のオリジナルルールを作るなど、工夫を凝らすことで、長く複雑なパスワードを覚えやすくすることは可能だ。
以下3つのポイントを参考に、覚えやすい安全なパスワードを作ろう。
■1.基本のフレーズをアルファベットにする
第一段階として、まずは基本のフレーズを決め、ローマ字読みのアルファベットに変換しよう。
フレーズをアルファベットへ変換する例
- 自転車→zitensha
- 靴下→kutsushita
- カーテン→katen
- スマホ→sumaho
など
これらのアルファベットは、このあとのステップで複雑化させるため、現時点ではわかりやすいものでも問題はない。
■2.マイルールでフレーズを複雑化させる
わかりやすいフレーズを複雑化させるために、以下のようなオリジナルのルールを設け、一段階目で決めたアルファベットに変更を加える。
パスワードを複雑化させるマイルールの例
- aを@に変える
- iを!に変える
- 左から3番目と5番目の文字を大文字に変える
- 下の名前の頭文字を文字列の最後に加える
など
例えば「zitensha」のフレーズを、以下3つのマイルールを加えて複雑化してみる。
- aを@に変える
- iを!に変える
- 左から3番目と5番目の文字を大文字に変える
上記のマイルールを加えたパスワードは「z!TeNsh@」となり、「自転車」から派生した文字列だとはわかりにくいだろう。
■3.サービスやシステムの特徴を加える
サービスやシステムの特徴を加えることで、パスワードの使い回しを防止しよう。
作成中のパスワード「z!TeNsh@」にサービスやシステムの特徴を加える例
- Aaa Shop →最初の文字と最後の文字でパスワードを挟む→Az!TeNsh@p
- BBB Plaza→最初の文字と最後の文字をパスワードの先頭に加える→BaAz!TeNsh@
「Az!TeNsh@p」「BaAz!TeNsh@」など、自分なりに覚えやすく、なおかつ長く複雑なパスワードが作成できた。ここまで解説した3つのポイントを踏まえ、パスワード作りに挑戦してみよう。
パスワードが漏れたときに生じるリスク
万が一パスワードが悪質な人物によって開錠されてしまった場合、その際に生じる被害は計り知れない。例えば、住所や電話番号、クレジットカード情報など、ありとあらゆる個人情報が漏洩するリスクが考えられる。
こういった脅威から身を守るためにも、安全なパスワードの作成が重要だ。
■安全ではないパスワードの例
安全ではないパスワードとして、例えば以下のような文字列が挙げられる。
- IDと同じ
- 自分や家族の名前、生年月日、電話番号
- 住んでいる地域の名前
- 同じ文字列の繰り返し(0000、aaaaなど)
- 安易な文字並び(abcd、1234など)
このようなパスワードは、たとえ文字列が長いとしても推測されやすい。自分ですぐに思いつくパスワードは、他人もすぐに推測できるものであることに注意しよう。
パスワードの作り方に関するQ&A
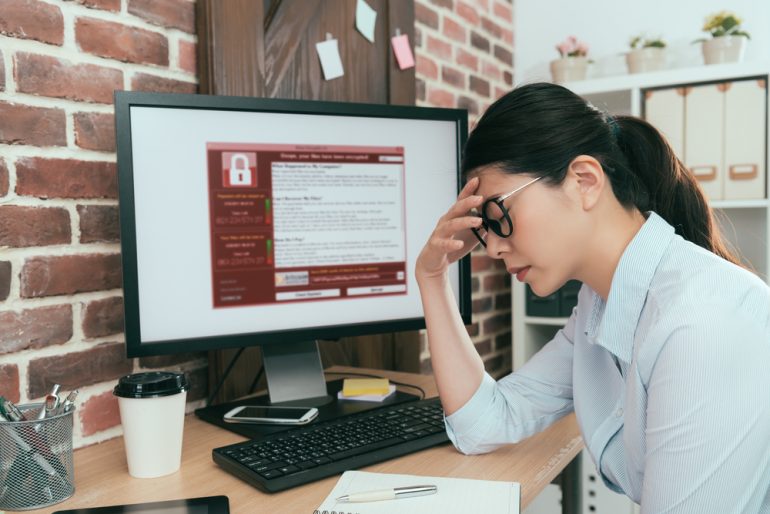 パスワードの作り方に関するQ&Aを紹介する。気になる項目があれば参考にしてほしい。
パスワードの作り方に関するQ&Aを紹介する。気になる項目があれば参考にしてほしい。
■他に覚えやすいパスワードの作り方はある?
他に覚えやすく安全なパスワードの作り方としては、以下のようなアイデアが挙げられる。
- 2つ以上のフレーズに同じマイルールを適用し、文字列を長く複雑化させる
- フレーズのアルファベットを逆さまにする(例:zitensha→ahsnetiz)
- 部屋の中で1番目立つものをパスワードのフレーズにする
など
■多要素認証やログイン通知は効果ある?
パスワードを使ったセキュリティ対策のほかに、多要素認証やログイン通知もセキュリティ対策として効果的だ。
多要素認証はIDやパスワードなどの「知識情報」と呼ばれる要素のほか、指紋などの「生体情報」などを組み合わせるものであり、ハッキングの成功率を下げる効果が期待できる。ログイン通知を設定すれば、自分以外の誰かがログインしたことを把握できるため、ぜひ一緒に取り入れたいセキュリティ対策と言えるだろう。
■パスワードの使い回しはなぜ危険なの?
たった一つのパスワードを開錠されるだけで、他サービスによる被害も雪だるま式に増えてしまうため、パスワードの使い回しはとても危険だ。記事の中で解説したように、サービスやシステムの特徴を加えるなどして、パスワードの使い回しを防止しよう。
■パスワード生成ツールを使用しても問題ない?
パスワード生成ツールは、一般的に長く複雑な不規則な文字列を自動で生成するため、安全性は高いといえる。しかし、完全ランダムのため、覚えにくいというデメリットがあることも理解しておきたい。
なお、無料で使えるパスワード生成ツールには、以下のようなものがある。
- ノートン パスワードジェネレーター
- 1Password パスワードジェネレーター
- ラッコツールズ パスワード生成
- KEEPER パスワード生成ツール
ウェブサイトのツールを利用すれば、iOS、Android、PCなどデバイスを問わずパスワードを作成できるのでおすすめだ。
※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。
文/編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













