
成功者に共通する資質を子供の頃から育てる『Five Keys』の代表・井上顕滋氏によれば、ホンモノの自己肯定感を育むためには、「母性愛」と「父性愛」という異なる2つの愛情の存在が大事であるといいます。そこで、この2種類の愛情について、井上顕滋氏の著書『子育てママに知ってほしい ホンモノの自己肯定感』から抜粋して紹介します。
子どもの中に「I’m OK」を育てる「母性愛」
母性愛は、「母親が子どもに対して持つ本能的な愛情」という意味がありますが、本書では自分の存在をまるごと肯定してくれる、包み込むような愛のことを指します。子どもを抱きしめて、「生まれてきてくれてありがとう」と親が心から子どもに言葉をかけることで、子どもはありのままの自分が愛されていることを感じます。こうして子どもの中に「I’m OK」という感覚が生まれます。
「I’m OK」という感覚から「I can」という感覚を醸成するために、なるべく早い段階で親子間の愛着を形成しておくことが大切です。愛着とは乳幼児期に親子間で築かれる心理的な結びつきのことです。愛着が形成されていれば、その後、厳しいことを言ったとしても、「親は私を愛しているから、私のために厳しく言ってくれているのだ」と受け止めることができるからです。母性愛という「優しさの愛情」で育んできた自己肯定感の土台の上に、年齢を重ねるにつれ、「ダメなものはダメ」と厳しい愛情である父性愛をもって社会のルールを教えていくのです。
社会性の土台をつくる「父性愛」
父性愛は、一般的に「子に対する父としての自然な愛情」という意味ですが、私は「厳しさの愛情」と定義しています。厳しくといっても、いきなり強く叱りつけるというわけではありません。相手は生まれてからまだ数年しかたっていない子どもです。例えば、社会のルールを破る行動をしてしまったとしても、それは意図的にルールを破っているわけではなく、ルールを知らないからというケースがほとんどです。
知らないということは悪いことではありません。その段階では、子どもにどうすればよいのかを優しく教えます。知らないのだからできないのは当たり前だと考えれば、親も冷静に接することができるはずです。しかし、何度か教えられてルールを理解しているにもかかわらず、そのルールを破った場合は「ダメなものはダメ」と厳しく叱ってあげる必要があります。その時に子どもは初めて自分の思いどおりにならないという困難に直面し、フラストレーションを感じながらその対処法を覚えます。こうして、子どもは状況に応じて、自分の感情や欲求を制御しなければならないという社会性の基礎を身につけ始めます。
やがて、子どもも社会のルールを理解するようになり、ルールに従って行動できるだけの力がついてきます。子どもがルールに従って行動できていればそのまま見守りますが、本当はできるのにもかかわらず意図的にルールを破ることがあればそこで叱ります。そうすることで、状況によって自分がどう振る舞うべきかという空気を読む力や、社会に出て必要になる「破ってはいけないルール」を守る感覚が身についていきます。このように社会性を育む上で重要な父性愛に基づく「叱る」という行為はとても大切です。
しかし、男の子を育てているお母さんに多いのですが、自分がほとんど叱られてこなかったので、子どもを叱ることに抵抗があるという人がいます。女の子は男の子に比べると、親の言うことをよく聞いてルールに従って振る舞う傾向があるので、ほとんど叱られずに育ったというお母さんも珍しくありません。しかし、男の子を育てていく上では、厳しく叱ることが必要になる場合も多くあります。母性愛や父性愛という話をすると勘違いされることがあるのですが、母性愛は母親しか注げないわけでもなければ、父性愛は父親しか注げないわけでもありません。理想は両親がともに母性愛を全力で注ぎ、適度に父性愛を注ぐという状況です。
「生まれてきてくれてありがとう」を心から子どもに伝える
最近は共働き家庭も増えて、0歳のときから保育園に通わせているというケースもあります。そのような状況で、母性愛を十分に注げているのかと心配する人もいます。特に、早朝保育や延長保育を利用していると、子どもと関わる時間は非常に限られてきます。ただ、ここで大事なのは、母性愛を十分に注がれているかどうかは子どもが判断しているということです。例えば、どんなに長い時間を一緒に過ごしていても、ただ子どもと同じ空間にいるだけで、母親はスマートフォンをずっと触っているというような環境では、子どもは自分のことは大事じゃないから興味がないんだと認識して、自分は愛されていないと感じてしまいます。
重要なのはどれだけの時間を一緒に過ごしたかではなく、「生まれてきてくれてありがとう」という心からの気持ちを、子どもにどれだけ伝え、表現できているかということです。よくあるのは、きょうだいがいる家庭で、親としては均等に十分な愛情を注いでいるつもりでも、子ども本人はそう思っていないというケースです。ある家庭では、兄が病弱で、弟はめったに風邪もひかないくらい丈夫でした。そのきょうだいのお母さんは、病弱な兄のほうを常に気づかい、病気をするたびに一生懸命に看病してきたので、弟よりも兄のほうに十分に手をかけたつもりでいました。しかし、成長してからお互いの本音を話してみると、兄は自分が病気で寝込んでいるときにお母さんと弟が楽しそうに遊んでいる姿がうらやましかったのだと言います。お母さんが弟と接するときには楽しそうにしている半面、自分と接するときにはいつも困った顔をしていて、自分はお母さんをいつも困らせてしまう要らない存在だと感じていたそうです。
子どもはまだ人生経験が浅いため、このような行き違いが起こりがちです。親はそのことを理解した上で、母性愛を注いでいく必要があります。母性愛を十分に注ぎ、それを子どもがきちんと受け取れたかどうかで、子どものその後の人生に大きな影響をおよぼします。母性愛を注ぐのは、学校教育でできることではありません。親だからこそできることであり、そうやって子どもの心の土台は家庭教育でつくられるのです。子育てには厳しさの愛情と優しさの愛情の両方が必須ですが、両方兼ね備えている親もいれば、どちらか一方に偏っている親もいます。次回、4つのタイプの親と、そのもとで育つ子どもについて、詳しく述べます。
文/井上顕滋
いのうえ・けんじ。1970年生まれ。2004年 Result Design株式会社を設立。最先端の心理学および脳科学を学び、それらを融合させることで人それぞれの持つ能力を最大限に引き出す、独自の能力開発メソッドを確立。3000社以上の企業で経営者・経営幹部への指導や研修のほか、エグゼクティブコーチ、メンタルトレーナーとしてオリンピック出場の日本代表選手や世界一に輝いたプロスポーツ選手のサポートも行っている。自らも経営者として30年以上の部下育成の経験を持つ。2011年に未来の成功者を育てるため、小学生を対象とする日本初の非認知能力専門塾Five Keysを設立。2015年には非営利型一般財団法人日本リーダー育成推進協会 (JLDA)を創設し代表理事に就任。現在は特別顧問。講座などを通じてこれまで指導した小学生の保護者は4万人を超える。
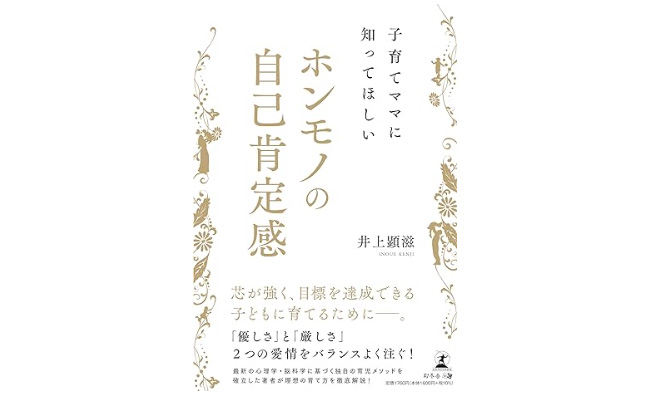 『子育てママに知ってほしい ホンモノの自己肯定感』
『子育てママに知ってほしい ホンモノの自己肯定感』
著:井上 顕滋
【Amazonで購入する】
【楽天ブックスで購入する】















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE















