
信賞必罰は具体的にどういう意味なのか、使う場面に迷うこともあるのではないでしょうか。賞罰について私情を挟まず、厳格に行うという意味があります。本記事では、信賞必罰の意味や由来となった中国の故事、使い方・例文、類義語を解説します。
目次
信賞必罰という言葉を知っていますか?知っていると語彙が広がる言葉の意味を押さえていきましょう。
信賞必罰とは?

信賞必罰は、「しんしょうひつばつ」と読みます。賞罰を厳格に行うという意味です。
ここでは、信賞必罰の意味や言葉の由来を解説します。
■賞罰を厳格に行うこと
信賞必罰とは、賞罰のどちらにも私情を挟まず、公正に行うことを指します。「信」と「必」はどちらも「必ず」という意味があり、功績のある者には必ず賞を与え、罪を犯した者は必ず罰するという意味の言葉です。
「賞」は幅広い概念で、金銭や名誉を与えるほか、功績を褒め称えることも含まれます。「必罰」は罪を見逃さず、人によって刑罰の種類を変えることなく、誰もが同じ罰を受けなければならないことを表します。
参考:デジタル大辞泉
■中国の故事が由来
信賞必罰の出典は、古代中国で書かれた思想家・韓非子(かんぴし)の「韓非子」です。民衆を統制するため、信賞必罰が重要であることが記載されています。
書物には君主が臣下を支配する方法として「必罰して威を明かにす、信賞して能(のう)を尽(つ)くさしむ」という記述があります。「罪のある者は必ず罰して君主の威勢を明らかにし、功績のある者は必ず褒美を与えて能力を発揮させる」という意味です。
刑罰の限度についても、「親しい者、身分の高い者、寵愛する者にも行う」という言葉があり、公平な罰を行うことを説いています。
■組織のルールに採用されることが多い
賞も罰も公平に与えるという信賞必罰は、会社の組織運営においても重視される考え方です。社員の働きを正当に評価し、罪は必ず罰するという組織運営が求められます。
実際に、組織のルールとして採用している会社も少なくありません。企業方針に「信賞必罰」という表現を使用している会社もあります。
信賞必罰を経営方針に取り入れることで組織の規律が保たれ、社員のモチベーションが上がるというメリットがあります。
■信賞必罰にはデメリットもある
信賞必罰は組織運営に必要な考え方ですが、徹底しすぎるとデメリットも発生します。信賞必罰を極めるために成果主義を採用し、さらに個人の業績に応じて報酬に反映させるという「結果主義」だけになると、さまざまな問題が起こるためです。
結果主義は最終結果のみにフォーカスして評価し、途中のプロセスを考慮しません。契約の件数や金額だけで評価してしまい、営業先を訪問した数や情報収集といったプロセスは評価の対象としないという特徴があります。
さらに、短期的な成果に焦点をあてるため、競争の激化を招くことにもなるでしょう。その結果、職場の人間関係の悪化につながる可能性があります。
成果につながらない業務は疎かになる可能性があり、社員は成果を上げることに対するプレッシャーとストレスに悩まされることもあるでしょう。そのため、成果だけでなく、成果を出すまでのプロセスも評価する「信賞必罰」が求められます。
信賞必罰の使い方・例文
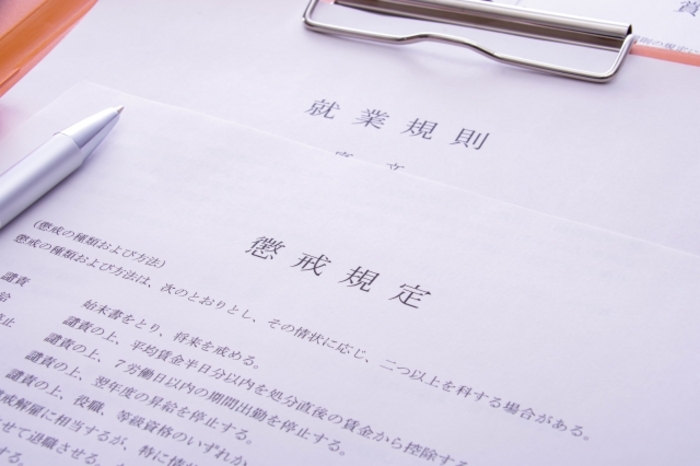
信賞必罰について理解を深めるため、使い方を例文で確認しましょう。
- 我が社には信賞必罰の方針があり、社員のモチベーションアップにつながっている
- 彼は子どものしつけに信賞必罰を取り入れており、よいことをしたらしっかり褒めるが、ダメなときはきちんと叱っている
- 信賞必罰は大切だが、それだけに固執せず、柔軟な対応が必要な場合もある
- 信賞必罰の精神を貫くためには、役員も処罰の対象にしなければならない
- 会社組織にとって信賞必罰の考え方は重要だが、普段の働きぶりなど数字以外の側面も評価する必要がある
信賞必罰の類義語

信賞必罰には、次のような類義語があります。
- 勧善懲悪(かんぜんちょうあく)
- 論功行賞(ろんこうこうしょう)
それぞれの意味を詳しくみていきましょう。
■勧善懲悪
勧善懲悪とは、善良な行いを奨励し、悪い行いを懲らしめるという意味です。言葉の由来は、古代中国の歴史書である「春秋左氏伝(しゅんじゅうさしでん)」とされています。
日本にも飛鳥時代には勧善懲悪の言葉が伝来しており、聖徳太子による「十七条憲法」には「勧善懲悪」の言葉がみられます。
勧善懲悪の例としてあげられるのは、日本の時代劇や昔話や、ドラマなどでよくみられる、ヒーローが悪を滅ぼすというストーリーです。「善」である主人公が勝利し、最後には悪を懲らしめるという勧善懲悪の内容が描かれています。
勧善懲悪は信賞必罰と似た言葉ですが、とくに「悪を懲らしめる」という意味に焦点をあてて使われることが多いでしょう。
(例文)
- 昔から勧善懲悪のドラマは人々に支持されている
- 現実の世界ではすべてが勧善懲悪とはいかず、よい行いが報われないケースもある
参考:デジタル大辞泉
■論功行賞
論功行賞とは、功績や戦績などを調べ、それに応じてふさわしい賞や評価を与えることです。「論功」とは功績の有無や程度を論じて定めることで、「行賞」は賞を与えることを指します。
中国の歴史書「三国志 魏志・明帝紀」が言葉の由来で、書物の中には「功を論じ賞を行う」という一節があります。戦乱の時代にあって、乱をおさめた褒美を与えるという意味です。
論功行賞には信賞必罰の「必罰」はありませんが、功績のある者に必ず賞を与えるという点で、信賞必罰に似ている言葉です。
(例文)
- 新しい人材配置は、論功行賞の意図がよく反映されている
- 新しい内閣に指名された大臣のポストは、論功行賞によるものではないかと噂されている
参考:デジタル大辞泉
信賞必罰は賞罰を公平に行うこと

信賞必罰とは、功績には必ず賞を与え、罪には必ず罰を与えることを指します。賞罰を公平に行うという意味であり、会社の組織ルールに採用されることが多い考え方です。ただし、組織運営で信賞必罰を徹底すると、デメリットにつながる可能性もあります。
信賞必罰の類義語には「勧善懲悪」と「論功行賞」という言葉があげられます。一緒に覚えておくと、信賞必罰の理解が深まるでしょう。これらは似ている言葉ですが、細かいニュアンスは異なるため、それぞれの意味を理解して使うようにしてください。
構成/須田 望















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













