
給与とはどの範囲を指すのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか?給与は会社から支給される労働の対価すべてを指し、基本給のほか、残業手当や各種手当、賞与が含まれます。本記事では、給与と給料との違いや手取りの算出方法、年末調整などを解説します。
目次
給与とは、会社から従業員に対して支給される労働の対価の総称です。基本給だけでなく、時間外手当や各種手当、賞与、現物支給も含まれます。 給与のほかにも、会社から支給されるお金を表現するものに「給料」や「報酬」「所得」「手取り」がありますが、それぞれ意味は異なります。
給与とは何か、改めて理解を深めていきましょう。
給与とは?
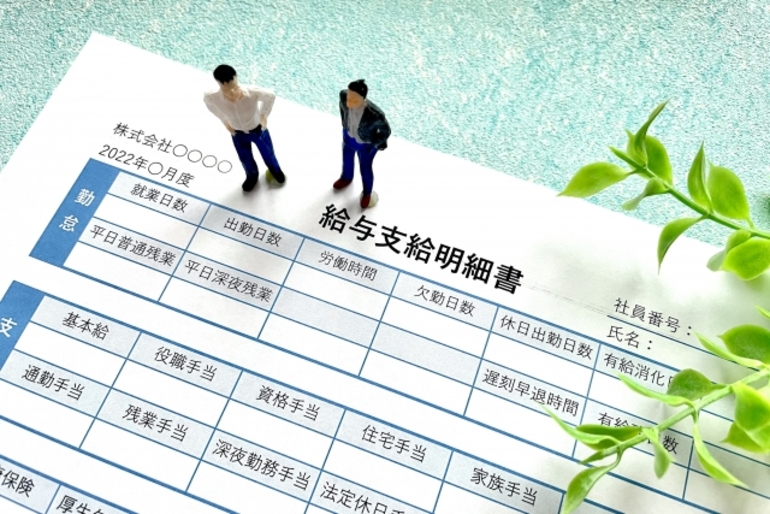
ここでは、給与とほかの言葉との違いについてみていきましょう。
参考:デジタル大辞泉
■「給料」との違い
給料とは、給与から各種手当や賞与などを差し引いたものです。一般的に、給料は基本給を指します。
各種手当や時間外手当を含む給与は労働状況などで変動するのに対し、給料は昇給やベースアップなどが行われない限り、変動がありません。
また、基本給である給料は現物給与を含まず、金銭のみという点も給与と異なる点です。
■「報酬」との違い
報酬とは、給与と同じく、会社から支給される労働の対価すべてのことです。
給与は雇用関係にある労働者に支払われるものを指しますが、報酬は雇用関係にない者へ支給する対価も含む点が異なります。
委任契約をしている役員や社員、業務委託をしているフリーランスなど雇用関係にない者への支払いは、給与ではなく報酬となります。
■「所得」との違い
所得とは、年間の給与の合計額から「給与所得控除」を差し引いた金額のことです。給与所得控除とは、給与をもらう給与所得者に対して設けられた制度で、事業者における必要経費にあたります。
所得税の課税対象となる「給与所得」を算出する際に用いられ、所得税法により、1年間の給与収入額に応じた控除の金額が定められています。
■「手取り」との違い
手取りとは、実際に受け取る金額のことです。給与は会社から支給される労働対価のすべてですが、そのすべてが従業員の手元に入るわけではありません。所得税や住民税といった税金や、社会保険料などが控除されます。
控除される金額は給与額や家族構成などによって異なり、手取りとして従業員に支給されるのは、およそ給与の8割程度です。
給与に含まれるもの

給与は会社から支給される労働対価で、次のものを含みます。
- 各種手当
- 現物支給
- 賞与
それぞれの内容をみていきましょう。
■各種手当
手当とは、会社が従業員に対して支給する基本給以外の賃金のことです。法律で支給が定められているものと、会社が任意で支給するものの2種類があります。
法律上の手当には、次のものがあげられます。
- 時間外労働手当(残業手当)
- 深夜労働手当
- 休日労働手当
任意で支給する手当の一例は、次のとおりです。
- 通勤手当
- 住宅手当
- 家族手当
- 出張手当
- 資格手当
手当は、通勤に必要な費用や住宅にかかる費用など、個人の環境によって避けられない負担を調整するとともに、業務上生じる責任や能力に報いるという目的があります。
■現物支給
現物支給とは、金銭以外で支給される給与のことです。現物給与とも呼ばれます。金銭以外で支給される現物給与は、食事代補助や通勤定期券、自社製品などが一例としてあげられるでしょう。
労働基準法では、給与は通貨で支払わなければならないと定められています。しかし、従業員の同意があれば、現金以外の方法で支給することが認められています。
現物給与は通貨に換算し、従業員の給与所得として課税対象になるのが原則です。
■賞与
会社から賞与が支給される場合、賞与も給与に含まれます。賞与は会社が任意で支給するもので、支給の有無や金額は会社ごとに異なります。
多くの会社が採用しているのは、「基本給連動型賞与」です。「基本給の3ヶ月分」というように定められ、基本給をベースに計算されるのが一般的です。
会社や個人の業績に応じて金額を決める「業績連動型賞与」もあります。業績の良いときに支給されるため、基本給連動型のように一定額が確実に支給されるものではありません。しかし、業績に応じて支給額が決まるため、従業員のモチベーションを高めるという効果があります。
給与から手取りを計算する方法

従業員の手元に入る手取りは、次のように計算します。
- 総支給額を計算する
- 控除額を差し引く
手取りを計算するステップをみていきましょう。
■1.総支給額を計算する
まず、1ヶ月分の総支給額を計算します。給与の締め日が過ぎてから、タイムカードなどの勤怠管理表で各従業員の勤務時間や割増賃金の対象となる勤務の有無を確認します。
1日8時間・週40時間までの法定時間を超えた労働時間がある場合、必ず規定の割増賃金を支払わなくてはなりません。有給休暇の使用時間がある場合は、それも含めます。
さらに、通勤手当や家族手当などの各種手当を計算し、総支給額を算出します。
■2.控除額を差し引く
総支給額を算出したら、控除額を計算します。控除するのは所得税や住民税、社会保険料であり、従業員ごとに計算しなければなりません。税金は、給与の金額に応じて算出します。
控除する社会保険料は健康保険料と厚生年金保険料(介護保険料)、雇用保険料であり、会社も一定の割合を負担するのが一般的です。給与からは、従業員の負担分を差し引きます。
控除の合計額を計算したら、総支給額から差し引いて手取り額を決定するという流れです。
給与の年末調整とは
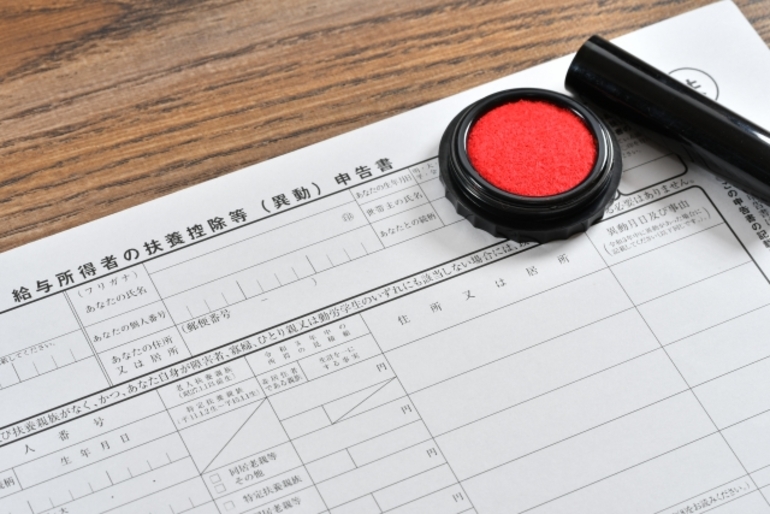
給与から差し引かれる所得税は、年末調整で再計算します。年末調整とは、会社が従業員に支払った給与や賞与の合計額から所得税の総額を再計算し、過不足金額を調整して年税額を一致させる手続きです。
ここでは、年末調整の手続きについて解説します。
■所得税の再計算
年末調整は、所得税を再計算する手続きです。給与から毎月差し引かれる所得税は概算額であり、所得税の最終的な金額は、年間所得が確定しなければわかりません。年間所得が年末に確定した時点で、会社はあらためて年間の所得税を再計算し、過不足を精算します。
一方、住民税には年末調整のような手続きはありません。前年の1月1日から12月31日までの所得により、各自治体が1年分の税額を決定します。確定した税額は会社に通知され、翌年の給与から差し引かれます。
■税金が還付される場合がある
年末調整により、所得税を払い過ぎていた場合には、過払いの分が還付されます。一方で、年の途中で扶養控除対象者が減ったり、賞与の支給額が毎月の給与の合計額よりも多かったりした場合などは不足分が発生し、追加徴収されることもあります。
また、生命保険料や地震保険を支払っている場合、各種申告書を提出することで所得税控除を受けることが可能です。
年末調整で受けられない控除もあるため、注意が必要です。ふるさと納税を利用していたり、高額な医療費を支払っていたりする場合は、確定申告をすることで、所得税の還付を受けられます。
給与について理解を深めよう

給与は従業員が会社から受け取る労働対価のすべてであり、時間外手当や各種手当、賞与などを含んだ総称です。給料や報酬、所得とは異なるため、違いを知っておきましょう。
従業員が毎月受け取る手取りは、給与から税金や社会保険料を差し引いた金額です。差し引かれた所得税は年末調整で再計算され、払い過ぎていた所得税がある場合は、還付される場合もあります。
構成/須田 望















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













