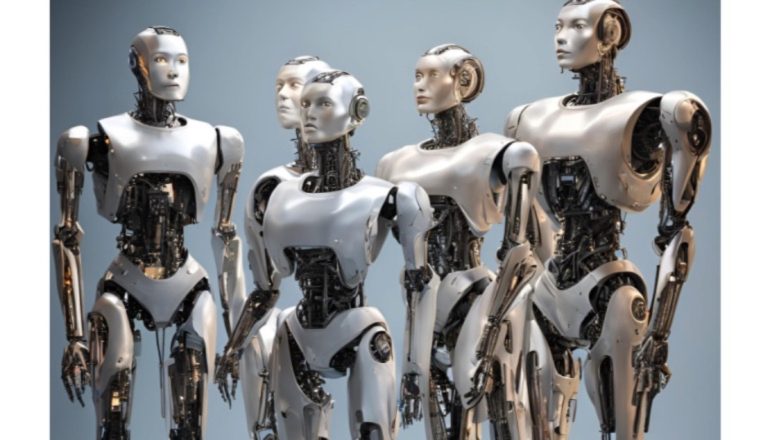
パラレルミライ20XX「In Parallel」
静寂が、島の朝を包んでいた。空はまだ暗く、わずかに薄明るい青が広がり始めている。
波は遠くから押し寄せるが、風が静かにささやく音だけが、耳に届いていた。
砂浜沿いに立ち並ぶ建物も人の気配を感じさせず、街灯がひっそりと道を照らしている。
その光の下、自動運転車の列がまるで息を潜めるようにそこにある。

Kは目を覚ました。窓から見える景色はいつもと変わらない、ある一つのことを除いて。
朝の冷たい空気が、最近買い替えたカーテン越しに部屋の中に流れ込むと、Kはそっとベッドから抜け出し、冷えた床に足をつけた。
家の中はしんと静まり返り、外からは物音ひとつ聞こえない。
Kはゆっくりと服を着替え、台所へ向かった。棚から豆を取り出し、グラインダーで丁寧に挽くと、ほのかに香りが立ち始めた。やがて、ポットから蒸気がシュッとのぼる音を立てる。
熱いお湯をフィルターの上からゆっくり注ぐと、豆が膨らみ、蒸らされた香りが一層広がる。
コーヒーの温かさが冷たい朝の空気と対照的に心地よかった。
時計を見ると、まだ午前五時過ぎ。島が完全に目覚めるには少し早い時間だ。
窓際に歩み寄り、カーテンをわずかに引いた。
道端に並んだ自動運転車は今日も動かない。三日前からまったく動いていないのだ。
この島では、島外の1社が提供する無人車だけが走っている。ガソリン車は既に過去の遺物となり、すべての移動はその乗り物に委ねられていた。
Kは車列に目を留め、しばらく考え込んだ。島の外から技術者が来て、修理をしてくれると聞いていたが、いまだに何の進展もない。島の人々も特に動揺することなく、ただ待ち続けている。
Kはコーヒーを飲み干すと、広場へ向かう準備を始めた。今日も市場が開かれる。新鮮な魚や野菜、手作りの品々が並び、いつも通りの賑わいが広がっているはずだ。技術者が来るのを待ちながら、島の日常は淡々と続いている。
静かな路地を抜け、緩やかな坂道を上がり広場に着くと、すでに市場には島の人々が集まっていた。いつもの活気がそこにある。上空に飛ぶドローンは、広場全体を見守っている。

電子タグで価格が表示された商品が並ぶ中、子どもたちはその片隅で遊び、大人たちはスマートグラスで情報を確認しながら商品を手に取って談笑している。誰も自動運転車のことや技術者のことを気にしていないように見える。それは、Kにとってどこか不思議な光景だった。
「おはよう、K」と声をかけてきたのはNだった。彼は手に魚の入ったバスケットを持ち、にこやかに微笑んでいる。
「おはよう、N」Kは微笑みを返した。「今日は技術者、来ると思うか?」
Nは肩をすくめて「どうだろうな。まあ、来なければ来ないで、生活は続くさ」と言った。
その言葉に、Kは何も返すことができなかった。
確かに、島の生活は続いている。自動運転車が止まったままでも、人々は徒歩や自転車で移動し、市場で買い物をし、笑顔を見せている。しかし、その平穏さがどこか不気味に感じられるのはなぜだろうか。Kはその思いを抱えたまま、Nと別れて市場を歩き続けた。
しばらくしてKは港へ向かうと、そこには顔馴染みの船乗りの少年Sが立っており、自動運転船が波に揺られて停泊しているのが見えた。背筋を少し丸め、無言で波を見つめるSはKに気づくと、こちらに歩み寄り「技術者は今日も来ないみたいだよ」と言った。
その表情は少し疲れが見える。
「本土からの通信も不安定で、港にも連絡がないんだ。今日も期待できそうにない」
Kは小さく頷いた。
「そうか……」
Sは続けて言った。
「皆、特に気にしていないみたいだよ。このままでも生活できるって。でも、僕は少し不安なんだ。こんなに長く、何も変わらないなんて……」
KはSの言葉を聞きながら、同じような不安を心に抱いている自分に気づいた。
「そうか…ありがとう」とKは答えたが、心の中では小さな失望が広がっていた。今日もまた、技術者は来ない。それでも、明日こそは来るのかもしれない、という期待をどこかで捨てられずにいる自分に気づいた。
2人はしばらく沈黙したまま立っていた。その後、KはSに問いかけた。
「そもそも、技術者が島に来る必要があるのかな?島外からコードの修復はできるんじゃないか?」
Sは考え込みながら答えた。
「それができれば、こんなに待つ必要はなかったはずだよね。でも、何かが邪魔してるんだと思う。本土との通信がうまくいってないせいなのか、それとも何か大きな問題があるのか……わからないんだ」
Kはその言葉に再び小さく頷いた。
「なるほど……外の問題が、ここまで影響しているのかもしれない」
Sは苦笑した。
「そうだね。でも、それを知ったところで僕たちにできることはないから……待つしかないよね」
Kはその言葉を聞きながら、再び心の中に広がる無力感を感じた。
翌日、Kは再び港へ向かった。すると、そこにはSが立っていた。しかし、彼の姿は昨日と違ってひどく憔悴して見えた。目の下にはクマができ、肩は落ち込み、全身から疲労が漂っている。
「また会ったね」とSはかすれた声で言い、虚ろな目でKを見つめた。
「昨日と同じで、技術者はやっぱり来ない。本土の状況はさらに悪化しているみたいで、連絡もまったく取れないんだ」と、Sはため息混じりに続けた。
KはSのやつれた姿を見て、どうしようもない焦りを感じていた。
「そうか……君も無理をしているな」と優しく声をかけると、Sはかすかに笑い、力なく肩をすくめた。
「もう、どうしたらいいのか分からないんだ。ただ、このまま待っていても何も変わらないのに……どうしてみんなは平気なんだろう?」とSは声を震わせながら問いかけたが、答えることができなかった。Kも同じように、何も変わらない島の人々の態度には不安を感じていた。
しかし、その不安の正体を掴むことができず、ただ静かにSの肩に手を置いた。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













