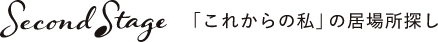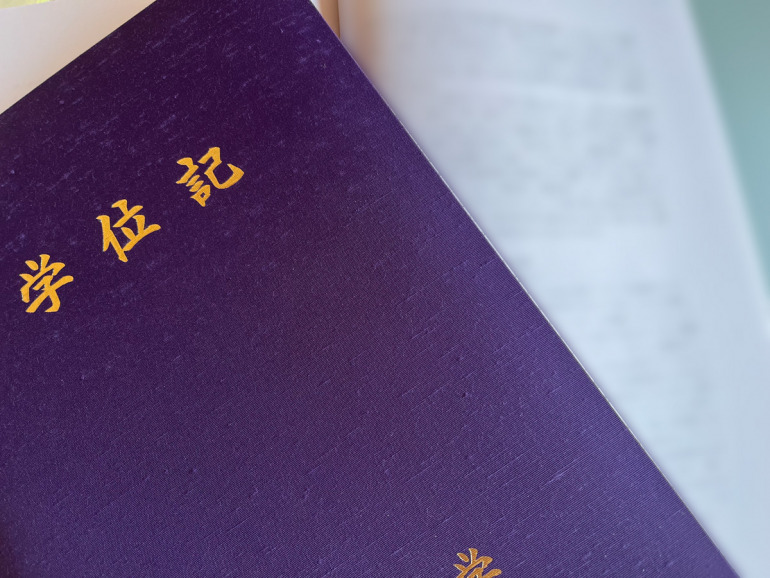大変だったのはデジタル関係。AIに翻弄されAIの恩恵も受ける
かつての学生時代と違って、なんでもコンピューターでやらなければならないのは大変だったとのこと。
出欠を取るときも、呼ばれて返事をするのではなく、パソコンでクリック。オンライン授業だったら、それぞれの部屋に分かれて話し合って発表する。講義によって違うさまざまのアプリに、何十人もの学生が書き込んで、それを画面共有。データの処理も当たり前のようにパソコンです。
「英語による授業は録音して、日本語に翻訳して文字起こしするアプリを使って内容を把握します。英語の文献は、Googleカメラでざーっと撮って翻訳することができるんです。
今は言語の問題も随分と楽になっているんですよね。AIに翻弄されながら、AIの恩恵も受けられました。
デジタル系は一番苦労したけど、若い子たちは優しくて、よく教えてくれます。空き時間に講習してもらったりしました」
3000円居酒屋もパンケーキも恋愛相談も
学生みんなが普通に接してくれたのは不思議なぐらいで、とても感謝していると大川さんはいいます。
「仲間として迎え入れてくれましたね。ディズニーランドとか水族館とか、遊びに行こうと誘ってもらったし。ご飯を食べに行こうといわれて、どんな店かなと思ったらサイゼリア。3000円飲み放題の居酒屋にもよく行きました。
ゼミや科目のLINEのトークルームにも入っていたし、なにかあったら教えてくれるし。
もう一度青春をやったような感じで楽しかった。パンケーキ食べに行こうとか、おいしいカレー屋さんがあるから行こうとか。
全然排除されなかったし“なに?このおばさん”っていう扱いは1度もされなかった。
人生の経験者としてリスペクトはしてくれて、就職や恋愛の相談に乗ったりもしました。みんなのお母さん的な年齢だから。でもおごってあげたりするわけじゃないんですよ。みんなイコールというスタンスではあったから」
20代の考えを聞けたのも面白かったといいます。
「例えば講義で、結婚というテーマを与えられて話し合ったことがあったんですが。20数人の女子たちの中で、結婚したいっていうのは一人もいないんです。男子も5,6人いたうち結婚したいというのは半分でした。なぜ結婚したくないかと聞くと、メリットがなにも感じられないっていう。そういう時代なのかと驚きました」
大学院は社会人経験をしてから行ったほうがいい?
大学院では、一方的に講義を聞くことは多くありません。「協働的な学び」が今の教育のキーワード。教授が答えを教えるのではなく、話し合いながら考えをまとめて発表してレポートにすることが一般的。そこでは、社会人経験があることが強みになったとのことです。
「例えば、ある課題解決案についてプラスとマイナスを考える時に、若い子たちは自分の20数年の経験からしか語れない。私は、自分の親としての子育て経験からも考えられるし、社会人として若い人を見て来た視点からも語れるわけです。
日本におけるマイノリティーとか多文化共生についてといっても、20数年生きて来ただけで語れるのは限りがあるわけですから。そういう差がレポートの説得力に出てきます。
大学院では経験値がものをいうことが多くあり、学部を卒業してすぐよりも、年齢を重ねてから行ったほうがいいんじゃないかと思ったぐらいです」
論文を書き上げ、40年前の袴をはいて卒業式に
「学生たちは、レポートに苦労していました。私は学生時代に書くのが早かったわけではないけど、会社で何十年も報告書とか企画書とか書いてきたから、今は彼らより早いんですよね。余裕がない学生たちは、全部一生懸命書くから大変だけど、こっちはある程度手の抜き方がわかっているから楽だった気がします。
もちろんレポートの締め切りで、久々に夜中の3時4時までやることもありました。修論(修士論文)の時は1日10時間、12時間とか書いて、教授に見てもらっては修正するのを繰り返して大変でしたが。
娘に、お母さんがいくつになっても勉強するのは尊敬しちゃうと言ってもらえました。大変そうだったのは同じでも、会社員時代に大変なときはピリピリしていて、大学院のときは幸せそうだったから、家庭が円満になったそうです(笑い)」
その大変だった修論を書き上げ、大川さんは無事に大学院を卒業。卒業式には、大学を卒業した22才のときの牡丹色の着物を着て紺色の袴をはきました。
「40年前に着物を作ってくれた母は、もう90才近くて随分弱っていますが。私が卒業式に着るというので、喜んで準備してくれました。思わぬ親孝行にもなったようです」

授業料は年間53.6万円。学びの時間を十分に享受
国立大学院の年間授業料の標準額は53万5800円で、入学料の標準額は28万2000円。私立は大学によって異なりますが、ほぼ合計100万円をこえます。
大川さんは、自分が大学院に行くことは、収入を得る準備のためではなく道楽だからと考え、私立ではなく学費の安い国立を選びました。投資として考えるなら損得はわからないけど、充分に楽しめたことは確かだといいます。
「長いこと働いてきた。お金をもらうために、労力を提供してきたわけです。だけど学校に行ったら、自分が授業料を払う側でしたから。こんなにいろいろなものを享受することができるんだ、働いてきたこの数十年は自分の時間を売っていたんだ、と感じました」
学ぶ期間を持つことは、これまでの半生を振り返り、今後の生き方を考えるきっかけにもなるようです。
大学院に行った一番の収穫は「若返り」!?
最後に、大学院に行った一番の収穫は?と聞くと、笑って「気持ちが若返ったことかな」という答えが返ってきました。

20代の同級生と。中央が大川さん
「気が付くと、それまでは同世代とのつきあいばかりになっていたんですよね。話すのも健康がどうの介護がどうのばっかり。でも、大学院に行ったら、まわりの若い子たちはみんな希望を持っているし、悩みも“将来どうするか“で未来を向いている。だから、自分も年齢を忘れられた気がします。夫や娘からも若返ったと言ってもらえました」
大卒以上の社会人の89%が再教育を「受けたい」または「興味がある」と考えています。再教育で利用したい教育機関として挙げられた1位は大学院の46.9%で、2位の大学(学部)19.5%を引き離しています(※1)。一方、社会人の大学院進学は「勤務時間が長くて十分な時間がない」「費用が高すぎる」「職場の理解を得られない」といった現場の声があるように(※2)、多くの人が、実際に大学院に行くのは難しいとあきらめているのも事実でしょう。
しかし、今回のインタビューで、大川さんは「すごく楽しかった」という言葉を何度も口にしました。「思っているより大変じゃないし、ともかくおすすめですよ」とのことです。
※1「職業能力開発総合大学校能力開発研究センター調査報告書」平成17年より
※2「大学教育に関する職業人調査」平成21年東京大学<科研費調査研究>無作為に抽出した事業所の大卒社員25,203人に対するアンケートより
取材・文/新田由紀子