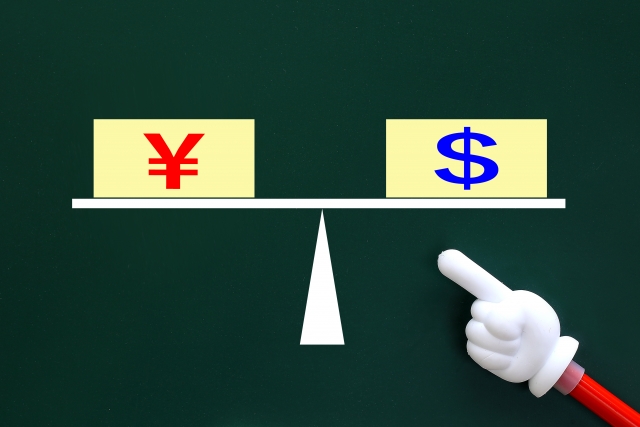三井住友DSアセットマネジメントはこのほど、同社チーフマーケットストラテジストの市川雅浩氏がその時々の市場動向を解説する「市川レポート」の最新版として、「米長期金利上昇と株安が進みドル円は一時150円台に~今後をどうみるか」と題したマーケットレポートを公開した。レポートの詳細は以下の通り。
米国では強い雇用指標に長期金利上昇と株安で反応、ドル円は一時150円台をつけて乱高下
10月3日発表された8月の米雇用動態調査(JOLTS)は、非農業部門の求人件数が961万件と市場予想(881.5万件)を上回り、労働需給の引き締まりを示唆する結果となった。
これを受け、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が強まると、米10年国債利回りは一時4.81%近辺まで上昇(価格は下落)し、連日でおよそ16年ぶりの高水準をつける展開となり、ダウ工業株30種平均など米主要株価指数は軒並み大幅安となった。
一方、為替市場では、JOLTS発表後の米長期金利上昇を背景に、ドル円は一時1ドル=150円15銭レベルに達し、2022年10月21日以来、約1年ぶりのドル高・円安水準をつけた。
しかしながら、ドル円は150円台をつけた直後、一気に147円43銭レベルまでドル安・円高が進み、その後はすぐに149円台に戻るなど、非常に値動きの激しい相場展開になった。
米金利上昇と株安は安易な利下げ期待の修正によるもので一巡なら金利上昇と株安は一服へ
米10年国債利回りは8月に、しっかり4%台乗せとなった後、米経済の底堅さを背景に、上昇基調が続いている。
長期金利が上昇する環境のなかでは、株価収益率(PER)の高いハイテク株の相対的な割高感が意識されやすく、このところの米主要株価指数の動きをみると、やはりハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数のパフォーマンスは低調だ(図表1)。また、米株安の影響は日本株にも及んでいることが確認される。
本来、米経済の強さは株高要因だが、フェデラルファンド(FF)金利先物市場などでは、経済の強さにもかかわらず、来年の利下げの織り込みがかなり進んでいたため、これが急速に修正され、米長期金利上昇と株安につながったと推測される。
そのため、安易な利下げ期待の修正が一巡し、米連邦準備制度理事会(FRB)による政策の舵取りが市場に信認されれば、米長期金利上昇と株安は一服する可能性が高いと考えている。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE