老人ホームで最期の時を迎える老人たちのベッドに寄り添い、身体を擦こすりつけ、顔を舐なめ、そして傍らで静かに、おくる。一緒に暮らして最期のときまで寄り添う犬猫たち。
『盲導犬クイールの一生』の著者・石黒謙吾氏が死を看取る犬・猫たちと人間との絆を描いた『犬が看取り、猫がおくる、しあわせのホーム』(光文社)より一部抜粋し、神奈川県・横須賀市にある特別養護老人ホーム「さくらの里 山科」とそこで一緒に暮らして最期のときまで寄り添う犬猫たちのエピソードを紹介していく。

文福の看取り行動が可能にする最期のケアへの準備
文福に人の死期を確実に悟る能力があるということは、裏を返せば、その兆候が見えたら、入居者を見守る職員や家族は、別れへの〝準備〞ができるということにもなる。行動もだけれど、気持ちのほうも含めて。
65歳から入居可能な「さくらの里」に暮らす入居者は、施設全体で100人。平均年齢は90歳で、1年間に亡くなる方がそのうち30人前後。へんな言い方だが、職員さんたちにとって、死はある意味、平凡な日常の少しだけ先のできごとだ。
文福がいる犬ユニットには10人の方が暮らしていて、年間に3人前後の方が最期の時を迎えるという。11年のあいだに文福はそのすべての方に看取り行動をとってきたのだが、最初にその行動に気づいたのは、2年ほど経ってからだった。
看取り介護態勢に入ったある入居者の個室の前で文福はずっと座っていて、悲しそうにうなだれていたという。その様子を職員同士で話していて、このユニットのリーダー・出田恵子さんが思い出した。そういえば、半年前と、さらにその数ヶ月前に亡くなった方の時も、文福が同じ行動をとっていたことを。
そして半日後、文福は部屋の中に入ってくると、ベッド脇に座ってじっと入居者を見ている。さらに翌日には、ベッドの上に乗って顔を舐める。そのあとは、トイレとごはん以外はベッドを離れずに、傍らに寄り添った。翌日、息を引き取るまでずっと……。
これ以降、ユニットに暮らす誰に対しても文福は、亡くなる数日前から必ず同じように看取ってきた。一緒に暮らしてきて旅立ちを迎える人がいる。ならば、自分ができることはせめて最期の時を見送ること。そう思っているのだろう。
文福のこの行動が指針となって、熱望していたことが叶った人がいた。
ある男性の入居者が、昔、漁師だった頃に過ごしていた漁港に行きたいと言い続けていた。余命1週間と宣告を受けてから2週間。医学的には外出などとんでもない状態だったが、ターミナルケアとして「その人らしい最期」を考える職員たちは相談し、「連れて行ってあげたい」となった。しかし体調はいつどうなるかわからない。そこで、文福の看取り行動が始まっていないことで決断し、実行に移す。
漁港に着き、涙して喜ぶ男性、付き添ってきた娘さん、職員たち。
無事にホームに戻ると血中酸素濃度が大幅に上がるなど体調が回復していた。
4日後、文福は部屋の前に佇み、夜には室内に。翌日、ベッドに上がり寄り添いが始まる。その夜、男性は旅立った。とても満ち足りた表情だったという。
 「犬が看取り、猫がおくる、しあわせのホーム」
「犬が看取り、猫がおくる、しあわせのホーム」
石黒謙吾(著) 光文社
 【特報】9/25 オンエア、10月2日(月) 午後2:30 〜 午後3:00に再放送あり
【特報】9/25 オンエア、10月2日(月) 午後2:30 〜 午後3:00に再放送あり
NHK「ネコメンタリー 猫も、杓子も。」
文/石黒謙吾
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE









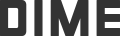 最新号
最新号







