老人ホームで最期の時を迎える老人たちのベッドに寄り添い、身体を擦こすりつけ、顔を舐なめ、そして傍らで静かに、おくる。一緒に暮らして最期のときまで寄り添う犬猫たち。
『盲導犬クイールの一生』の著者・石黒謙吾氏が死を看取る犬・猫たちと人間との絆を描いた『犬が看取り、猫がおくる、しあわせのホーム』(光文社)より一部抜粋し、神奈川県・横須賀市にある特別養護老人ホーム「さくらの里 山科」とそこで一緒に暮らして最期のときまで寄り添う犬猫たちのエピソードを紹介していく。
人の死期を感知する文福と人の匂い
文福は、もともと保護犬だった。柴犬系の雑種で茶色、推定13歳か14歳のオス。
「さくらの里」にやって来たのは、2012年春。まさに桜の咲く頃だった。
彼はここで何度となく奇跡と思える看取りのシーンを見せてきた。
入居者に死期が近づいてくると、だんだん近くにいようとする。そして、衰弱が進むと、3日前あたりから寝ている個室のドアの前から離れずにずっと中を向いて座る。さらに、いよいよその時が近づいてくると、ベッドの上に横たわる老人に寄り添い、顔をぺろぺろと舐め、見守り、最期を看取る。入居者は、そんな文福を抱きしめ、やわらかな顔で天国に召されていく。
看取りの犬、である。人間の「おくり人」とは意味が違うが、「おくり犬」という表現でもいいかもしれない。これが一度や二度ではなく、必ずこの行動をとるのだから、たまたまその時そうなったという偶然ではなく、死期をはっきりと感知できているとしか考えられない。文福はすでに20人を超える人を看取っているのだ。
施設長の若山さんは、「なぜわかるのでしょう?」と尋ねられると、「匂いでわかるんじゃないかと考えています」と答えている。僕なりにいろいろお話を伺ってみたのだが、たしかにそうとしか思えない。科学的な証明までには至っていないが、獣医師さんによる見解でもその考えが示されているようだ。
しかし、このホームにはほかの犬たちもいるが、この行動をとるのは文福だけ。それはなぜなのか? 若山さんはこう考える。
「さくらの里」に来る前、文福は、保健所の保護センターにいた。どこかで保護された犬や猫が入ってきて、一般的には1週間ほど引き取り手が現れないと、殺処分になってしまう。保健所によって違いはあるのだが、たいがいは、処分が近い部屋へと日を追って移動し、死の順番を待つ、という状況となっている。
そんな中に身を置き、死へのリミット1日前でセンターから救い出された文福は、死にゆくほかの犬たちから発せられたなんらかのメッセージによって、特別な能力を身につけたのかもしれない。だから文福は、対象が犬であっても人であっても、自分がそうであったように「死」への恐怖を少しでもやわらげてあげたい、そう感じているのではないか。
若山さんのそんな推論を聞いて感じ入った僕は、入居者を見守る文福の目を覗き込んで「そうなの?」と尋ねた。すると、静かに見返してくれた。
 いつもリビングにいる文福は、入居者みんなにかわいがられ、そして、よく、ユニットの入り口を向いて「見張り番」をしている。
いつもリビングにいる文福は、入居者みんなにかわいがられ、そして、よく、ユニットの入り口を向いて「見張り番」をしている。
 「犬が看取り、猫がおくる、しあわせのホーム」
「犬が看取り、猫がおくる、しあわせのホーム」
石黒謙吾(著) 光文社
 【特報】9/25 オンエア、10月2日(月) 午後2:30 〜 午後3:00に再放送あり
【特報】9/25 オンエア、10月2日(月) 午後2:30 〜 午後3:00に再放送あり
NHK「ネコメンタリー 猫も、杓子も。」
文/石黒謙吾
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE










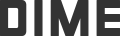 最新号
最新号







