今回のアイデアノミカタは画家「デイヴィッド・ホックニー」です。
現在、日本では27年ぶりとなる大規模個展が東京都現代美術館で開催中(7/15-11/5)ですが、ここでは作品解説ではなく「画像はどれも、目で見たものの説明だ」というホックニーが表現そのものをどのように考え、アプローチしているのかに迫っていきたいと思います。
画像の歴史は洞窟に始まる
そもそも自然界に二次元が存在しないこと、これはホックニーの作品を考える上で重要な指摘です。なぜなら二次元とは抽象化されたものあるからです。
例えば目の前に平面に見える絵画があるとします。
しかし、私たち人間よりもずっと小さな虫の視点で同じ作品を見た場合、キャンバスも紙も凸凹した三次元の立体を感じることが出来るはずです。
つまり平面、二次元とは全て様式化されたものと解釈することが可能です。
ホックニー自身、どういうものが美術か実は分からないと発言しており、少なくとも美術を作っているとは言っていません。あくまでも画像を描写している、そして美術の歴史よりも必要なのは画像の歴史だとも語っています。
これはとても興味深い言及ではないでしょうか。
そもそも画像の本質とは、二次元のなかで三次元を表現することです。
そのため前提となる二次元が存在しない、ということに気づけば、写真もその例外ではないのです。言い換えれば写真が現実と考えると、写真自体も「描写のひとつ」であるという視点に気づかないのです。
またホックニーは、こうした画像の始まりは言葉よりも古い可能性があると発言しています。
つまり先史時代の洞窟壁画も人々の証言であり、目で見たものの説明が画像であるということです。ある日、誰かが動物を描いたとき、その絵をみた人がその後に同じ動物を見たときには、絵を見る前よりもハッキリと動物の姿が見えたのではないでしょうか。
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE











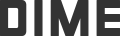 最新号
最新号






