脳は意外と賢くない
「脳科学」という言葉がメジャーになったのは、比較的最近のことだ。当初は胡散臭いイメージを持たれることもあったこの学問分野も、常に注目を浴びるようになっている。ここまで存在感を増したのは、我々を人間たらしめている高度な思考も感情も、脳があるからこそ、という考えがあるからだろう。
一方、脳に対する全幅の信頼が揺らぐ研究結果が増えている―どうやら、我々が思っているほどには、脳は賢くないらしい。
科学ジャーナリストのアニー・マーフィー・ポール氏は、「脳の能力はかなり限定的です。あまり喜ばしくない科学的な事実がここ数十年で明らかになっており、脳の限界に気づく科学者が増えています」と説く。そして、「私たちに必要なのは、“脳の外”で考えること」だと、著書『脳の外で考える――最新科学でわかった思考力を研ぎ澄ます技法』(松丸さとみ訳、ダイヤモンド社)で力説する。
ポール氏の言う「脳の外」とは、AIと脳を接続して云々といったSFじみた話ではない。それは、首から下の身体のこともあれば、周囲の環境や空間、専門家や仲間を指すこともある。そうした要素が、脳の限界を押し広げ、人生の質を改善してくれるという。
しかし、「脳の外」で考える力は、ほとんど開発されることなく、大半の人には未知の世界。はたしてそれは、どのような世界なのだろうか?

直感を重んじる一流トレーダーたち
一例としてポール氏が挙げるのは、「内受容感覚」だ。これは視覚や聴覚といった五感とは別の、体内の至るところにあるセンサーによる感覚を指す。たとえこの言葉を知らなくても、我々は知らないうちにこの感覚を使って、仕事や生活に役立てているらしい。具体的な話として、組織行動学学者による、一流の金融トレーダーへの聞き取り調査が紹介されている。
“そのときにわかったのは、トレーダーたちは脳に縛られたやり方で物事を進めたことがほとんどないということです。代わりに、体内から湧き上がる感覚に頼っている、と彼らは話しました。
ある人は、このプロセスを説明する際、とりわけ体感的な言葉を使いました。「直感を信じないといけません。多くの判断は一瞬のことなので、どこが瀬戸際か、どんな手を打つか、わかっていなければいけません」。”(本書47~48pより)
別のトレーダーが「腹にずしんとくる直感」と表現するその感覚は、神の啓示といったものでなく「内受容感覚」によるものだという。また、直感と呼ぶほどでなくても、「震えやため息、呼吸の加速、筋肉の緊張」といった形で現れると、ポール氏は記している。
その感覚は大抵の場合、あまりにもささやかで、つい見逃してしまいがちだ。そのことを象徴する実験を、ポール氏は紹介している。その実験の参加者は、コンピューターの画面に表示された、伏せたカードで作られたAからDの4組の山から、山を選んでカードを表にするように指示される。カードの表には賞金か罰金が書かれていて、罰金は避け賞金を稼ぐように求められる。実はAとBの山は多額の罰金カードが含まれる「悪い山」。他方、CとDの山は罰金よりも賞金の比率が高い「良い山」となっている。参加者にはそのことは知らされず、全くのノーヒントでこのゲームをする。
このゲームの間、参加者たちは生理的にどれだけ興奮しているかを測定するため、指は電極につながれていた。参加者は、50枚カードをめくったところで、AとBの山は危険度が高いと認識したと答えた。しかし、それよりずっと前の10枚めくったところで、悪いカードの山をクリックしようかと考えているとき、電極は興奮状態を示し、無意識的にその山を避けるようになったという。
実験後の参加者へのインタビューでは、ゲーム後半まで、「なぜ自分が、ある山をほかの山よりも多く選ぶようになったのかは、本人も理解してなかった」そうだ。これがまさに内受容感覚のなせるわざであり、ポール氏は、「参加者の“脳”が理解するよりずっと前に、参加者の“体”はわかっていた」と指摘する。
活用すれば便利そうなこの感覚を高める方法がある。その1つがマインドフルネス瞑想だ。ポール氏は、この瞑想法を行うことで「体内のシグナルへの感度を高めるうえ、そのために重要となる脳の部位“島皮質”の大きさと活動を変化させることがわかっています」と説明する。マインドフルネス瞑想は、日本でも一時期流行したが、内受容感覚の開発を意識してやってみるのも悪くはなさそうだ。
高収入の親はジェスチャーが多い
「脳の外」で考える方法として、もう1つポール氏が挙げるのは「ジェスチャー」だ。
ジェスチャーといえば、起業家が聴衆を前にしたプレゼンテーションで、身振り手振りで自社商品をアピールする姿が目に浮かぶ。その姿はちょっと大仰で、信頼感に欠ける印象がなくもない。
しかしある研究では、投資家向けのプレゼンで、「ジェスチャーを巧みに活用した創業者は、新規事業への資金を獲得する確率が12%高い」という結果もある。
また、ジェスチャーの効用は、起業家のためだけにあるのではない。仕事や日常生活において、相手に話の内容を覚えてもらうのにも有用だ。ポール氏は、次の研究結果を紹介する。
“ある研究では、ジェスチャーつきのスピーチ動画の方が、実験参加者が話のポイントを思い出せる確率が33%高くなる結果になりました。この効果は、動画を見た直後から表れていましたが、時間の経過とともにさらに大きくなりました。スピーチの動画を見た30分後、実験参加者がスピーチのポイントを思い出す確率は、ジェスチャーつきの方が50%以上高くなりました。”(本書154pより)
そもそも我々はみな、意識しないでもジェスチャーを日頃から使っている。キングス・カレッジ・ロンドンのクリスチャン・ヒース教授は、体の動きと言語表現における相互作用を研究するため、医師と患者の対話を映像に記録した。その映像では医師が、「これは言ってみれば、ええと、炎症を抑えるのに役立ちます」と話したとき、「ええと」の前にすでに、手で何かを抑えるような動きを3回している。話そうとする前に、その内容のコンセプトはジェスチャーで示されているというのは興味深い。そして聞き手も、相手の話を聞く前に、ジェスチャーを見てうなずくなど反応している。ポール氏は、「私たちの会話はほとんどが手によってなされ、口にする言葉は単なる補足」だと記すが、実際そのとおりなのかもしれない。
また、より衝撃的な話として、「高収入の親は、低収入の親よりも多くジェスチャーをする」とも。幼な子は親を見て学ぶものなので、ジェスチャーの多寡もそっくり受け継がれることになる。1歳2ヶ月の子供を90分観察した研究では、高収入の家庭の子は、平均で24の意味をジェスチャーで伝えた。一方、低収入の家庭の子は、それが13の意味にとどまった。それが就学年齢になると、語彙力の差となって顕在化している。
逆にジェスチャーを有効活用することで、外国語の学習など、さまざまな場面で役立つことをポール氏は示唆する。
長くなるので、本稿では内受容感覚とジェスチャーの2例を紹介するにとどめるが、ポール氏の著書は、予想外の気づき我々に与えてくれる。500ページを超える大著だが、読んで得るものは多いはずだ。
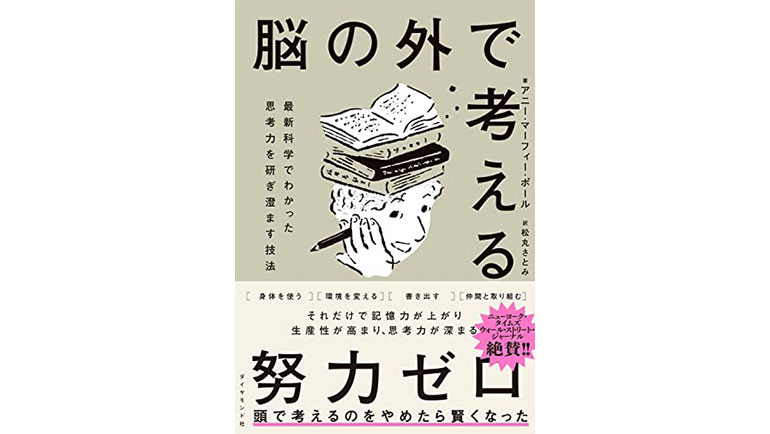
文/鈴木拓也(フリーライター)
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE









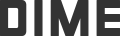 最新号
最新号







