生前に「公正証書遺言」を作成すると、自分の意思で遺産の分け方を決められるほか、相続トラブルの予防等にも繋がります。
今回は公正証書遺言について、作成のメリット・手続き・費用などをまとめました。
1. 公正証書遺言とは
「公正証書遺言」とは、遺言者本人に代わって公証人が作成する遺言書です。
民法では、遺言書の作成方式として、主に「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3つが認められています。
本人が全文を自書する「自筆証書遺言」と並んで、公正証書遺言はよく用いられている遺言書の作成方式です。
2. 公正証書遺言を作成するメリット
公正証書遺言を作成することには、相続対策として大きな効果があります。公正証書遺言を作成する主なメリットは、以下のとおりです。
・自分の意思で遺産の分け方を決められる
・相続人間のトラブルを防げる
・相続税の納税資金対策ができる
・信頼性が高く、紛失・改ざんの心配がない
2-1. 自分の意思で遺産の分け方を決められる
公正証書遺言には、主に遺産の分け方を記載します。その記載内容は法的効力を有し、相続人は原則として、公正証書遺言記載のとおりに遺産を分けなければなりません。
誰にどの遺産を与えるかを自分自身で決めたい場合には、公正証書遺言を作成しておくのがよいでしょう。
2-2. 相続人間のトラブルを防げる
公正証書遺言によってあらかじめ分け方が指定された遺産は、遺産分割の対象から除外されます。
分割方法について揉めるリスクの高い遺産(不動産など)がある場合には、公正証書遺言を作成しておくことが、相続トラブルの予防に役立ちます。
2-3. 相続税の納税資金対策ができる
遺産が多額に及ぶ場合には、相続税の課税についても考えておかねばなりません。
たとえば高額の不動産を相続する一方で、預貯金や上場有価証券などを一切相続しなかった場合には、相続税の納税資金の確保に困ってしまう可能性があります。
公正証書遺言を作成する際、各相続人が納税資金に困らないような遺産の分け方を決めておけば、このような問題は防ぐことが可能です。
2-4. 信頼性が高く、紛失・改ざんの心配がない
専門的知識を有する公証人が作成する公正証書遺言は、一般に自筆証書遺言によりも高い信頼性が認められる文書です。そのため、公正証書遺言が無効になるリスクは低いと考えられます。
また、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんなどの心配がありません。
相続トラブルを予防する目的で遺言書を作成する場合には、公正証書遺言が最適の方式といえるでしょう。
3. 公正証書遺言の作成手続き
公正証書遺言の作成手続きは、大まかに以下の流れで進行します。
(1)公証人との案文調整
(2)作成日時・場所の調整
(3)公正証書遺言の作成
3-1. 公証人との案文調整
まずは公証役場に連絡をとり、公証人に遺言書の案文を送付します。
公証人は、有効な遺言書として問題ないかを形式・内容の両面からチェックし、必要に応じて修正を提案します。本人・公証人間のやり取りを経て案文が確定したら、公証人が公正証書遺言の原本を準備し、作成当日に備えます。
3-2. 作成日時・場所の調整
公正証書遺言の案文確定後、本人と公証人の間で作成日時と場所を調整します。
作成場所は公証役場とするのが一般的ですが、公証人に自宅などへ出張してもらうことも可能です。ただし出張を依頼する場合は、公証人手数料が増額となる点にご注意ください。
なお、公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会いが必要となります。
以下の者は証人になることができませんので(民法974条)、それ以外の者から証人を選定します。
(1)未成年者
(2)推定相続人および受遺者、ならびにこれらの配偶者および直系血族
(3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
証人を自分で手配できない場合は、公証役場に手配を依頼することも可能です。ただしその場合、証人日当として1名当たり1万1,000円程度が必要となります。
3-3. 公正証書遺言の作成
公正証書遺言の作成当日は、以下の流れで手続きが進行します。
(1)公証人が遺言者に対して、公正証書遺言の原本を見せながら、内容を読み聞かせます。
(2)遺言者が原本に署名・押印します。遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。
(3)証人2名が原本に署名・押印します。
(4)公証人が民法所定の方式に従って作ったものである旨を付記して、原本に署名・押印します。
公正証書遺言の作成完了後、原本は公証役場で保管され、正本と謄本が本人に交付されます。弁護士などを遺言執行者に指定した場合には、正本と謄本のいずれかを遺言執行者になる人が保管するのが一般的です。
4. 公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言の作成費用(公証人手数料)は、対象財産の価額に応じて以下のとおりです。
|
目的の価額 |
手数料 |
|
100万円以下 |
5,000円 |
|
100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
|
200万円を超え500万円以下 |
1万1,000円 |
|
500万円を超え1,000万円以下 |
1万7,000円 |
|
1,000万円を超え3,000万円以下 |
2万3,000円 |
|
3,000万円を超え5,000万円以下 |
2万9,000円 |
|
5,000万円を超え1億円以下 |
4万3,000円 |
|
1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
|
3億円を超え10億円以下 |
9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
|
10億円を超える場合 |
24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
※公証人に出張を依頼する場合は50%加算、さらに日当と交通費が発生
※対象財産の価額が1億円以下のときは、1万1,000円を加算
※原本の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過1枚ごとに250円を加算
※正本・謄本の交付につき、1枚ごとに250円の手数料が発生
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE











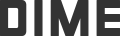 最新号
最新号






