裁量労働制は「能力を活かせる働き方」「自由な働き方」として、転職を希望する方の間で注目を集めています。
たしかに、裁量労働制にはメリットもありますが、反対にデメリットもある点に注意が必要です。裁量労働制によって働くかどうかは、メリット・デメリットの両面を総合的に考慮した上でご判断ください。
今回は、裁量労働制で働くメリットとデメリットを、労働基準法の観点からまとめました。
1. 裁量労働制とは
裁量労働制とは、使用者(会社)が業務の進め方や時間配分などを具体的に指示せず、労働者の裁量に委ねる制度です。
労働基準法では、以下の2種類の裁量労働制が認められています。
(1)専門業務型裁量労働制
以下の19業務について認められています。
専門業務型裁量労働制を導入するには、労働組合または労働者の過半数代表者との間で、労使協定の締結が必要です。
①新商品や新技術などの研究開発業務
②情報処理システムの分析、設計業務
③記事取材、編集などの業務
④新たなデザインの考案業務
⑤放送プロデューサー、ディレクター業務
⑥コピーライター業務
⑦システムコンサルタント業務
⑧インテリアコーディネーター業務
⑨ゲームソフトの創作業務
⑩証券アナリスト業務
⑪金融商品の開発業務
⑫大学教授の業務
⑬公認会計士業務
⑭弁護士業務
⑮建築士業務
⑯不動産鑑定士業務
⑰弁理士業務
⑱税理士業務
⑲中小企業診断士業務
(2)企画業務型裁量労働制
事業運営に関する事項の企画・立案・調査・分析の業務について認められています。
企画業務型裁量労働制を導入するには、労働者側の代表者を半数以上含む労使委員会において、5分の4以上の多数による決議が必要です。
2. 裁量労働制で働くメリット
労働基準法上、裁量労働制で働く労働者には、少なくとも以下の2点について裁量を与えなければなりません。
(1)仕事の進め方を自分で決められる
(2)勤務時間を自分で決められる
労働者にとっては、これらの裁量を活かして能力を発揮し、自由な働き方ができるメリットがあります。
2-1. 仕事の進め方を自分で決められる
裁量労働制で働く労働者に対して、使用者は業務の遂行の手段と時間配分の決定(=仕事の進め方)について、具体的な指示をしないものとされています。
したがって、以下のような細かい業務の進め方については、裁量労働制で働く労働者が自由に決められます。
・業務をどのような手順で行うか
・仕事を完成させるため、具体的にどのような作業を行うか
・業務の時間配分をどうするか
2-2. 勤務時間を自分で決められる
裁量労働制で働く労働者に与えられた「時間配分の決定」に関する裁量には、始業・終業時刻を決定する裁量も含まれると解されています。つまり、いわゆる「定時」に拘束されず、勤務時間を自分で決められるということです。
自分の生活リズムの中に仕事を組み込みたい方にとっては、裁量労働制は魅力的な働き方といえるでしょう。
3. 裁量労働制で働くデメリット
裁量労働制にはメリットがある一方で、以下のデメリットがあることには十分注意が必要です。
(1)残業代が支払われない
(2)労働時間が制限されていない
3-1. 残業代が支払われない
裁量労働制で働く労働者には、「みなし労働時間」が適用されます。
実際の労働時間にかかわらず、労使協定(または労使委員会決議)で定められた時間数労働したものとみなされるのです。
これは、裁量労働制で働く労働者に対しては、残業代が支払われないことを意味します。一見すると高待遇に見えても、残業代が支払われないため、労働時間に比べて賃金が割安になってしまうケースがあることに注意が必要です。
なお、深夜労働(午後10時から午前5時)については例外的に、通常の賃金の25%以上の深夜手当が支払われます。
(例)
・専門業務型裁量労働制
・通常の賃金が1時間当たり4,000円
・3時間の深夜労働をした
→3,000円(=4,000円×25%×3時間)以上の深夜手当が支払われる
3-2. 労働時間が制限されていない
みなし労働時間の適用により、裁量労働制で働く労働者については、実際の労働時間が法定労働時間によって制限されることはありません。
したがって、繁忙期で仕事が多い場合や、仕事の進め方が悪く時間がかかってしまう場合などには、際限のない長時間労働を強いられるリスクがあります。
裁量労働制を導入する企業には、対象労働者に対する健康福祉確保措置を講ずることが義務付けられています。
裁量労働制で働く労働者は、会社の健康福祉確保措置を効果的に活用しつつ、過重労働に陥らないように仕事をコントロールしなければなりません。それができる人であれば、裁量労働制で働くことに向いているといえるでしょう。
取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。
https://abeyura.com/
https://twitter.com/abeyuralaw
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE











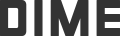 最新号
最新号






