
『柊』がどのような意味を持つ漢字なのか知らない人もいるのではないでしょうか。ここではその意味や成り立ちを紹介します。古くから日本人になじみのある柊の特徴や花言葉についても触れています。イメージや名前の例についてもご紹介します。
「柊」の意味とは?

まずは、『柊(ヒイラギ)』がどのような植物なのか、由来と併せて見ていきましょう。漢字の成り立ちについても紹介します。
とげのある葉が特徴の常緑小高木
『柊』はモクセイ科で1年中緑の葉が茂っている『常緑樹』です。関東以西の本州・四国・九州などの山地に自生しており、葉が固くとげのような鋭い切り込みがあるのが特徴です。
秋から冬にかけて白い花が咲き、良い香りがします。節分に飾られることが多いので、見たことがある人もいるのではないでしょうか?
混同されやすいのが、西ヨーロッパやアフリカ北部が原産地のモチノキ科のセイヨウヒイラギです。赤い小さな実が付いており、クリスマスに飾られる木です。光沢のある楕円形の葉が、のこぎりの歯のようにとがっているのが特徴です。
「ひいらぎ」の由来
『柊』という名前は、鋭いとげがいくつもあるような葉の形と関係があります。刺さるとヒリヒリ痛むことを意味する古語の『疼ぐ(ひいらぐ)』が由来だと考えられています。
痛みがうずくという意味の『疼木』という当て字が使われたというのも説の一つです。
植物の柊が由来とされる『ヒイラギ』という名の淡水魚もいます。中部地方以南の本州・四国・九州に生息している魚です。尾びれや背びれに鋭いとげがあり、その特徴が柊の葉と似ていることから名付けられたとされています。
漢字の成り立ち
柊は、『木』と『冬』が組み合わさった漢字です。『木』は、木が立っている様子を表したもので、『樹木』という意味があります。
『冬』は、糸の端を結んだ様子を表したもので、『ものの端』という意味です。末端という意味から、一年の最後の季節である『冬』に用いられています。
柊は一年を通して緑の葉が見られますが、花を咲かせるのは11~12月ごろです。冬に花を咲かせる木という意味で『柊』という名前が付いたとされます。
柊はどんな意味を持つ植物?
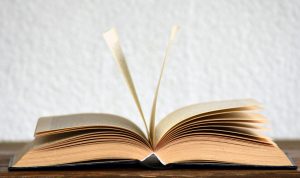
『柊』は、どのような植物なのでしょうか?花言葉についても紹介します。
魔よけ、厄よけ
柊は、古くから『魔よけ』や『厄よけ』に使われてきました。邪気払いの意味がある節分の伝統的な飾りに『柊鰯(ヒイラギイワシ)』があります。柊の枝に焼いた鰯の頭を刺して、玄関先などに飾る風習です。
柊には、『鬼の目突き』という別名もあります。鬼が柊の葉のとげに目を突かれ逃げて行ったという話があり、魔よけや厄よけの木として使われるようになったのです。鰯を飾るのは、臭いの強いものも魔よけになると考えられているためです。
ちなみに、欧米でセイヨウヒイラギのクリスマスリースを飾るのも、魔よけの意味があります。
花言葉は「先見の明」「歓迎」など
柊には複数の花言葉があり、その一つが『先見の明』です。柊の葉は、年数とともにとげがなくなり、丸みを帯びた形に変わっていくのが特徴です。変化していく様子から付けられた花言葉だといわれています。
花が咲くとよい香りがし、香りに歓迎されているような様子から『歓迎』という花言葉もあります。幹の強さから『剛直』や、魔よけに使われることから『保護』や『用心深さ』という花言葉もあり、ポジティブな意味があるといえるでしょう。
冬生まれの子どもの名付けに使われる

子どもの名付けには、漢字の持つ意味だけでなく、イメージを大切にする人もいるでしょう。そこで、『柊』のイメージや込められる願いを紹介します。名前の例も挙げるので、名付けの参考にしましょう。
強さやたくましさのイメージ、願い
柊は強い幹を持ち、丈夫で寿命が長いという特徴があることから、『強さ』や『たくましさ』をイメージできます。「健康に育ってほしい」や「どんな逆境にも負けない強い人になってほしい」といった願いを込めることもできるでしょう。
古くから魔よけとして使われていることから、『守られている』イメージもあります。名前に用いることで、「不運や危険などから身を守ってくれますように」「大切な人を守れますように」という願いを込められます。
「柊」が含まれる名前と読み方の例
『柊』は音読みで『しゅう』と読むため、『柊斗(しゅうと)』『柊弥(しゅうや)』『柊平(しゅうへい)』『柊真(しゅうま)』『柊太(しゅうた)』といった名前があります。
男の子の名前に使われることが多いですが、女の子でも『柊果(しゅうか)』『柊菜(しゅうな)』などの名前を付けられます。『しゅ』と読ませることで、『柊莉(しゅり)』など個性的な名前も可能です。
一緒に使う漢字は何通りもあるので、比較的組み合わせやすい漢字といえるでしょう。
まとめ
『柊』は古くから魔よけに使われてきた常緑樹で、ポジティブな意味の花言葉を持っています。良いイメージもあり、名付けの際に願いを込めやすいのも魅力です。漢字の組み合わせもたくさんあり、男女両方の名付けに使えます。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













