
女の子の名前に使われることが多い漢字の一つが『愛』です。『愛』には、どのような意味や由来があるのでしょうか?漢字の持つイメージや使い方と合わせて紹介します。
「愛」の意味と由来は?
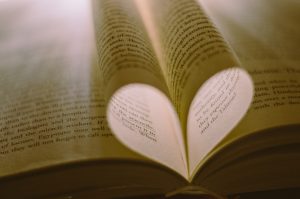
何となく意味が分かるとしても『愛』の意味を明確に説明できない人もいるのではないでしょうか?
親が子をかわいがる、好きな人を慕うなど
『愛』は、親が子をかわいがる気持ちや、好きな人など特定の人を慕う気持ちのことです。その他にも『音楽への愛』のように、ある物事を大切に思う気持ちや、『人間愛』のように個人的感情を超え、温かく慈しむ気持ちなど、幅広い意味があります。
『愛』は他の漢字同様に、弥生時代頃に中国から仏教とともに伝来したと考えられています。
現代中国では、部首の『心』が抜けた字で書かれますが、これは繁体字である『愛』を簡略化した簡体字で、『いとおしむ』『いつくしむ』など漢字の意味や使い方は同じです。
漢字の成り立ち
『愛』は、部首の『心』と『旡(あい)』『夊(夂、すい)』から成り立っている漢字です。『心』は人の心、『旡』は人が振り返ろうとする気持ちや姿、『夊(夂)』は歩くことを表しています。
つまり、『人が歩きながら後ろを振り返る心情』や『人が振り返りながら歩く』という意味がある漢字なのです。そこから『心にかける』という意味になり、現在の意味に広がっていったと言われています。
「愛」の使い方

『愛』は、どのように使われているのでしょうか?熟語や有名な名言、『恋』との違いについても紹介します。
「恋」との違い
恋は『恋に落ちる』という言葉がある通り、瞬間に生まれることがあるものです。一方、愛は互いによって育まれていくものという違いがあります。
恋は、「恋しい」「会いたい」など相手を思う気持ちが強過ぎて思い悩むという意味の『恋焦がれる』という言葉が示す通り、『満たされない気持ち』がある状態です。
相手のことを四六時中考えてしまうほど好きなのに、振り向いてもらえないなども、『満たされない気持ち』があるため、恋になります。恋心が満たされたときに、『愛』に変わるというのが一般論です。
しかし、実際には気付かないうちに恋が愛に変わっていたということも多く、いつから愛に変わったのか明確に知ることや線引きすることは難しいと言えるでしょう。
「愛する」「愛でる」のように使う
使われる頻度が高いのが『愛する』です。愛情を注ぐ、特定の相手を慕うという意味があります。
・彼は愛する家族を養うために懸命に働いた
・愛する子どもためなら頑張れるものだ
・彼女の恋人は映画を愛する青年で、映画監督を目指している
慈しむことや美しさを堪能し感動するという意味の『愛でる(めでる)』と使われることもあります。
・子犬を愛でていると、心が癒される
・花見の名所は、美しい桜の花を愛でながら食事を楽しむ人であふれていた
・夜空に浮かぶ満月を愛でていると、ノスタルジックな気持ちになる
「愛」を使った名言
『愛』を使った名言は少なくありませんが、中でも有名なものを紹介します。心に留めておくと、役立つことがあるかもしれません。
世界的に有名な『星の王子さま』の著者であるサン・テクジュペリの名言が、『愛する、それはお互いに見つめ合うことではなく、ともに同じ方向を見つめることである』です。
結婚生活において大切なことの一つなので、結婚する友人に贈る言葉として使えるでしょう。
また、『愛情には一つの法則しかない。それは愛する人を幸福にすることだ』というフランスの小説家・スタンダールの名言もあります。
親子間の『無償の愛』に通じるものがあるのではないでしょうか。愛する人を幸せにすることで、自分自身にも幸せが回ってくるということもあるでしょう。
「愛」を使った言葉

『愛』は日頃使う言葉に使われていることも少なくありません。使い方が分かるように例文とともに紹介します。
「愛想」
『愛想(あいそ)』は、『人に接するときの態度』を表す言葉です。例えば、『愛想が良い人』というのは、いつでも笑顔で接する人で、好感を持たれやすいです。
『人に対する信頼感』という意味もあり、『愛想を尽かす』のように使います。『お愛想』とすることで、『勘定』や『心遣い』という意味にもなります。
・彼女は子どもの頃から愛想が良く、近所の人からもかわいがられている
・彼女からLINEの返事が来ない。愛想を尽かされたかもしれない
・お愛想お願いします
「ご自愛」
年賀状など季節のあいさつの結びなどにも使われるのが、『ご自愛(ごじあい)』です。『自分を大切に労わり、健康に気を付けること』という意味の『自愛』に、尊敬を表す『ご』を付けています。
『ご自愛ください』というフレーズで使われ、『お体を大事になさってください』と、相手の健康を願う気持ちが込められたフレーズです。
・寒さが厳しくなり風邪がはやっておりますので、くれぐれもご自愛ください
・酷暑の折、何卒ご自愛のほどお祈り申し上げます
・季節の変わり目で寒暖の差が激しい時期ですので、どうぞご自愛くださいませ
「慈愛」
『慈愛(じあい)』は、『愛』に『慈しむ』という意味を持つ『慈』を組み合わせた言葉です。『親が子どもを慈しんでかわいがるような深い愛情』という意味になります。
『慈愛に満ちた』『慈愛にあふれた』など、さまざまな言い回しがありますが、『慈愛深い』は間違いなので、注意しましょう。正しくは、『慈悲深い』です。
・慈愛にあふれたストーリーが話題の映画を見に行った
・看護師の彼女は、常に慈愛の心を持って患者と接している
・〇〇先生は、慈愛に満ちあふれた笑顔で子どもたちに接してくれる
「愛嬌」
『愛嬌(あいきょう)』は、『にこやかで、かわいらしいこと』を表す言葉です。ニコニコしていて笑顔が印象的な人などが、『愛嬌のある人』です。
『愛嬌を振りまく』という言い回しで、『相手を喜ばす言葉や振る舞い』という意味にも使われます。
『愛想』と混同されがちですが、実際には異なります。意識しなくても自然とにこやかさが出るのが、『愛嬌』です。
愛想は人に良い印象を与えるためにする態度や動作であるのに対し、『愛嬌』はもともと身に付いているものという違いがあります。
・誰からも好かれる愛嬌のある人に育ってほしい
・愛嬌のある人と一緒にいると、自然と明るい気持ちになれることが多い
・愛嬌を振りまける人は、周囲の人に好かれる傾向にある
名付けで人気の「愛」

『愛』の持つ意味から名付けにも人気です。どのように使われているのか紹介します。
古くから主に女の子に使われる
『愛』は古くから女の子の名前に使われていましたが、大正時代に流行し、昭和時代には人気の名前第1位になるなど大ブームになりました。
それまで多かった『〇子』という名前から、『愛』や『彩』『舞』のような一文字の名前がトレンドになったのです。
『愛』が大ブームになった背景には、バブル時代が深く関係しているとされています。経済成長真っただ中で、残業や接待が当たり前の風潮がありました。
単身赴任や塾通いも珍しいことではなくなり、家族の触れ合いが薄れていった中で、家族の結びつきを大切に思う気持ちがあったことが『愛』が好まれた理由の一つと考えらえています。
「あ」と読ませる当て字としても
『愛莉(あいり)』『愛香(あいか)』など二文字で使われることもありますが、『愛』を『あ』と読ませる当て字として使われることも多いです。例えば、『結愛(ゆあ)』『莉愛(りあ)』『愛花里(あかり)』などです。
近年は、独自の読み方をする名前も増えています。『愛菜(まな)』『華愛音(はあと)』『琥々愛(ここあ)』『愛花(まなか)』などです。一文字で『めぐ』や『ちか』と読むこともあります。
さまざまな組み合わせや読み方ができるため、名付けに使いやすい漢字と言えるでしょう。
「愛」が持つイメージ

名付けに使うときには、漢字の持つ意味だけでなく、イメージも大切です。『愛』には、どのようなイメージがあるのでしょうか?
やさしく、あたたかい人とのつながり
『愛』は、親が子どもをかわいがる気持ちや好きな人を思う気持ちという意味があるため、 『愛する気持ち』をイメージする人が多いです。愛する気持ちからは、『やさしさ』や『いちずさ』がイメージできます。
『愛らしい』という言葉からは『かわいらしさ』、親の子ども対する変わらぬ無償の愛からは、『力強さ』もイメージできるでしょう。また、愛のある人は他人を思いやれる人なので、『あたたかさ』もイメージできます。
近年は、SNSの進化などにより、『人とのつながり方』が変わりつつあります。愛を持って人と接することの大切さや愛にあふれた人とのつながりをイメージする人もいるでしょう。
人から愛情を注がれる
『深く愛する』という意味の『愛情』という言葉から、『愛情を注がれる』というイメージもあります。周囲に愛情を注がれる人になってほしいというのは、親が子どもに願うことの一つではないでしょうか。
周囲の人から愛されたり、かわいがられたりする人は『愛されキャラ』といわれ、ポジティブに捉えられています。愛されキャラは、誰に対してもおおらかで笑顔が多く、周囲の人も明るくさせるようなイメージがあります。
一緒にいると幸せな気持ちになれたり、安心できたりする人が多く、そういう人になってほしいという願いを込めて名付けに使うこともできるでしょう。
まとめ
『愛』は、家族や恋人をかわいがる、慕うなどの意味があります。『やさしい』『あたたかい』『かわいらしい』など良いイメージがあるため、古くから女の子の名付けに使われており、昭和時代のトレンドでした。
その後も他の漢字と組み合わせて使われることが多く、近年は独自の読み方で使う人も少なくありません。
『愛』には多くの名言や日常生活で使える熟語もあるので、紹介した例文を参考に実際に使ってみましょう。















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













