昭和の時代……現代と違い、娯楽や情報も少なかった1970年代あたりまでは、日本の国民的スポーツといえば野球だった。
東京にもまだ多くの空き地が点在し、子どもたちは、学校が終わると、誰が声をかけるわけでもなく、グローブやバットを持って空き地に集合し、日が暮れるまでボールを追いかけていた。
大人たちも、職場や工場などでチームを作っては、日曜日を迎えるたびに、家族からの小言を右から左に受け流しつつグラウンドに向かい、野球を思う存分楽しんでいた。

そんな「野球漬け」の環境で育った男たちにとって、バッティングセンターは一人でも野球が楽しめる特別な場所だった。
また、雨が降って試合が中止となった時には、仲間たちと共に試合ができない鬱憤を晴らすのに一役買ってくれる頼もしい存在でもあった。
しかし時代が移り変るとともに、生活が豊かになり、多くの娯楽や情報が日常に溢れるようになった現代では、野球はもはや、かつてのような絶対的な存在ではなくなった。
それに伴い、バッティングセンターもその多くが姿を消していき、人々はバッティングセンターについて郷愁の中で語ることが多くなってしまった。
バッティングセンターはこのまま人々の記憶の中に埋もれていってしまうのだろうか。
そんな存亡の危機に立たされているバッティングセンターにスポットを当て、これまでバッティングセンターが歩んできた歴史と、苦境に立たされつつも、それに立ち向かい奮闘する人たちの現在(いま)を映し出すことで、逆風の中どのように生き残っていくかのヒントを示してくれる一冊が、2022年2月に上梓された『日本バッティングセンター考』(双葉社)だ。
「日本バッティングセンター考」の著者、カルロス矢吹氏インタビュー
今回、この企画の出版に至った経緯やバッティングセンターのこれからについて、著者であるカルロス矢吹氏に話をうかがうことができた。

『日本バッティングセンター考』
著者:カルロス矢吹
発行:株式会社双葉社
定価:2035円(税込)

カルロス矢吹氏 1985年宮崎県生まれ。大学在学中より、グラントンベリーなど海外音楽フェスティバルでスタッフとして働き始める。以降、日本と海外を往復しながら、ライター業やラジオ・TVの構成を開始。コンサート運営、コンピレーション編集、美術展プロデュースなど、アーティストのサポートも行う。2012年より、日本ボクシングコミッション試合役員に就任。
きちんとした形で世に出さなければ、協力していただいた方々に申し訳が立たない
――『日本バッティングセンター考』を出版しようと思ったきっかけを教えてください。
カルロス矢吹(以下カルロス) 元々中学まで野球をやっていて、今でも草野球チームで野球をやっている関係で、自分にとってバッティングセンターは身近な存在でした。
これまでバッティングセンターの話題といえば、ホームラン賞を連発する老人とか、お客さん側ばかりにフォーカスされていたので、オーナー側の話を紹介したいなと思ったのが最初のきっかけです。
――どうしてオーナーサイドの話を紹介したいと思われたのですか?
カルロス バッティングセンターについて知りたいと思ったときに、いろいろ調べたのですが、とにかく資料らしきものがなく、この謎を突き止めるには自分がやるしかないな……ということですぐに取材を始めました。
ただでさえバッティングセンターはどんどん数が減っていて、オーナーにはご高齢の方も多いので、とにかく聞けるうちに聞かないといけないですし。
そうやって取材を重ねて、貴重な話をたくさんうかがっていく中で、これはきちんとした形で世に出さなければ、協力していただいたオーナーやメーカーの方々に申し訳が立たないと思ってまとめたのが、『日本バッティングセンター考』です。
――実際に取材を進めてみてバッティングセンターに対するイメージは変わりましたか?
カルロス 「バッティングセンターなんてどこも同じじゃん」と思われるかもしれませんが、それぞれの施設によってそれぞれのストーリーがあって、同じ話というものがひとつもなく、興味深いものばかりでした。

気仙沼バッティングセンターの外観。オーナーが東日本大震災の被災を契機に開業を決意したセンターだ。
カルロス わかりやすい例でいえば、最初に取材したのが宮城県の気仙沼バッティングセンターで、その翌日に岩手県の前沢バッティングセンターを取材したのですが、バッティングセンターに対するスタンスが真逆でした。
片や、子どもとの約束を守るために始めたというストーリーでしたが、もう一方は、いかにしてバッティングセンターでビジネスを展開していくかという話が中心でした。
同じバッティングセンターなのにここまで違うのかと思うのと同時に、この時点で、絶対おもしろいものができると確信しました。
海を渡ったタイのバッティングセンターから総工費3億円の施設まで取材
――今回の取材で、最も印象に残っている施設を教えてください。
カルロス 一番はやはりタイのバンコクにあるバッティングセンターです。オーナーは長年タイに在住していたとはいえ、野球という文化がない国でバッティングセンターを作るというのは、それなりの勝算はあったにせよ、インパクトは大きかったですね。

バンコクバッティングセンターの外観。受付で料金を払ってプレーする。1ゲーム100バーツ(約372円)。

夏休みにはバッティング教室も開催。
カルロス 国内でいうと、宮崎県にあるFUNKY STADTUM宮崎です。2019年に3億円かけて作った施設で、施工を手掛けた(バッティングセンター施工)専門業者のキンキクレスコでも、ここまでコストをかけた施設は15年ぶりくらいという規模で、しかも経営母体がラウンドワンのようなチェーン店ではなく、個人オーナーというのが印象的でした。

FUNKY STADTUM宮崎の外観

屋内型のバッティングセンター。フロアも手入れが行き届いている。
カルロス もちろん採算的にはこれからでしょうし、ほかに本業もある方ですが、「バッティングセンターをやりたい」というロマン派のオーナーの夢を実現した施設でした。
――カルロスさんのような30代前後の人たちでもバッティングセンターにロマンを感じますか?
カルロス 自分たちの年代くらいまでは、子どもの頃に気軽にバッティングセンターに通っていて、老若男女あそこに集まる様々な人間たちを見ているので、ある種のノスタルジーを感じる世代だと思います。
ただ、20代くらいの人たちとってみると、バッティングセンターは、プロの選手や野球の強豪校を目指す人たちが打撃練習をしに行く場所、というイメージになってしまうかもしれません。
――どうしてこのような変化が起こったのでしょう。
カルロス 最大の原因はスマートフォンの普及だと思います。スマホでお金を使ってしまうとほかの遊びに使えないですから。その意味でいうと、バッティングセンターだけでなく、ゲームセンター、カラオケボックスにとっては大きな転換点になったのは間違いないでしょう。
これに加えて少子化も大きく影響しています。大阪など少年野球が盛んな地域を除いて、特に地方では来場者減につながっていると思います。
〝スマホ時代〟にバッティングセンターが生き残っていくためには
――そんなバッティングセンターが生き残っていくために何が必要だとお考えですか。
カルロス やはりリピーターだと思います。かつては一見の客がたくさん集まればいいという経営スタンスでしたが、これからは、自分のバットで打ちにくる、いわゆる「マイバット族」を捕まえることが重要かと思います。
もしバッティングセンター単独で生き残っていくとすれば、完全予約制の打撃練習場的な施設にするとリスクが低いと思います。
ただ、より現実的な対応で考えると、網走のバッティングセンターFull Swingのように、メインのビジネスはほかにあって、バッティングセンターを付加価値として提供し、グループとして収益を出していくのが理想的かもしれません。
――もし、カルロスさんがバッティングセンターの経営者だったとしたら?
カルロス 自分がオーナーだったら、まず最初に、未就学児童1日1打席無料というキャンペーンをやりたいです。重要なのは、子どものうちにこういった遊びを体験しておくことだと思います。
体験したことがないのに大人になってからわざわざバッティングセンターには行かないからです。それに来場すれば、保護者を含めてさすがに1打席で帰ることはないと思いますし。
ただ、イチからバッティングセンターを作ることはさすがに厳しいかなと思います。後継者を探しているところがあれば考えたいかな(笑)。もちろん前オーナーさんとの相性もあるので簡単ではないですか。
――どんなバッティングセンターになるのでしょうか。
カルロス 自分もバッティングセンターにノスタルジーを感じるロマン派なので、予約制みたいなことはしたくないです。ふらっと立ち寄った野球初心者の人たちも気軽に受け入れるような場所を提供したいと思います。
――最後になりましたが、カルロスさんのバッティングセンターを巡る旅はこれからも続いていくのでしょうか?
カルロス こういう本を出してしまったので、これからも続く……というより、続けざるを得ないというのが正直なところでしょうか。
取材したオーナーとの交流も続いていますので。ただ、できれば取材者というよりは、バッティングセンターを利用するユーザーとして関わっていきたいなと思っています。

取材・文/TOSHI.ヒロシ
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE









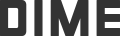 最新号
最新号







