
年末年始が近づいている。この時期は大学駅伝が大きな話題になるが、ここ数年は「厚底シューズ」が好成績を挙げるようになった。
反発力に富んだカーボンプレートで推進する仕組みの「ナイキの厚底」は、たったの数年で勢力図を塗り替えてしまった。
2021年の箱根駅伝では、何と日本メーカーのアシックスのシューズを履いている選手はひとりもいなかった。
この「厚底ショック」は、市民ランナーにも波及している。
が、あくまでもフィットネス目的で走っている人にとって、厚底シューズは有益なものなのか?
箱根から薄底が消えた!
上述の厚底シューズとは、一言で言えば「強力な反発により推進力を生み出すシューズ」である。
このシューズが登場する以前は、競技用シューズと言えば薄底だった。
極限までの軽量化が追求され、まさに羽根のような軽さのシューズこそがトップアスリートに相応しい製品だった。
そして薄型軽量シューズメーカーの「第一人者」こそが他でもないアシックスだったのだ。
それがたったの5年足らずで逆転した。
見た目にも重苦しいナイキの厚底シューズを履いた選手たちがトップ集団を率いるようになると、それまで薄底にこだわっていた他の選手や大学陸上部はこぞって厚底に履き替えた。
その流れは当然ながら、トップアスリートではない市民ランナーにも波及する。あくまでも趣味として走っている人にも、厚底が浸透しつつある。
が、だからといってフィットネス目的の市民ランナーが安易に厚底に手を出すのも考えものだ。
最先端シューズが怪我の原因に?
競技用の厚底シューズは、従来の薄底シューズとは真逆の概念から生み出されたものである。
それを詳しく書くと長くなってしまうが、簡単に表現すれば「走法が違う」ということだ。
踵から踏み込む日本人が厚底シューズを履く場合、それに慣れるための訓練に時間を費やさなければならないと言われている。
言い換えれば、厚底シューズはつま先走法に合わせた製品なのだ。
日本の一般的なランナーが安易に厚底シューズを履いて走ると、太股の裏側やふくらはぎを痛めてしまう可能性が高い。
一方で従来型の薄底シューズ(特に日系メーカーの製品)は、日本人の平均的な走り方を徹底追及してきたということもあり、履いた瞬間から足に馴染む場合が多い。
シェイプアップ程度のランニングであれば、無理をして最先端のシューズを選ぶ必要はまったくない。
競技用ではない「厚底」を選ぶ
また、ここまで書いた厚底シューズとはコンセプトが異なる「厚底」を選ぶというのもひとつの手段。
こちらは「初心者向け」と言われるもので、推進力ではなくクッション性が優先された厚底シューズである。
固い地面を数十分走る際に生じる衝撃を吸収する、というものだ。このようなシューズであれば、踵の部分にしっかりとしたヒールカウンターもあるから、踵が設置した際のグラつきも抑えてくれる。
大手メーカーの製品であれば、安価の割に作りがしっかりしているということもある。
効率的なシェイプアップを目指すランニングに用いるなら、むしろこのような意味合いの「厚底」が最適だ。

取材・文/澤田真一
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE










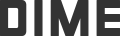 最新号
最新号






