
アナログゲーム、テーブルゲーム、非電源ゲーム……様々な呼び名がある中で、最近ではボードゲームを略して「ボドゲ」と呼ぶことが増えてきた。ボードゲーム愛好家のことを「ボドゲーマー」と呼ぶし、会社などでボドゲーマーが集まって「ボドゲ部」として活動することもある。
いずれにせよ、新たな略称が生まれた背景には、プレー人口の拡大があることは間違いない。新型コロナの猛威にもめげず、ボードゲームのプレー人口は増加中だ。それに伴い「ボードゲームカフェ」の店舗数も、2018年末には全国で約350店といわれていたが、2021年末には493店(※)と右肩上がりだ。
ボードゲームが支持される理由のひとつに「おうち時間の増加」が挙げられるだろう。中でも、自宅で家族と過ごす時間が増えたことにより「子供と楽しめるボードゲーム」が人気を集めている。
特に近年増えてきているのが「学びながら遊ぶボードゲーム」だ。プログラミングを疑似体験したり、すごろくで日本各地の名産品を覚えられたりする。
これだけ聞くと難しそうなゲームに思えるかもしれないが、そのどれもが、子供でも楽しめるように工夫されている。知識や経験だけで勝敗が決まらぬよう、サイコロを振ったりシャッフルされたカードを引いたりするなどゲームシステムに「ランダム性」を組み込むことで、子供でも大人に勝つチャンスがあるように設計されている。
パッケージに対象年齢が表記されているものがほとんどだが、子供向けと侮ることなかれ。大人のほうが夢中になってしまう、なんてこともあるかもしれない。
※ボードゲーム情報サイト『ボドゲーマ』に登録されている店数をもとに修正。
ボドゲなのに、ロボの動きを〝プログラミング〟する!?
『ロジックロボット』3300円
複数あるカードを使ってロボットの動く道筋を指定する「プログラミングフェーズ」と、実際に動かす「アクションフェーズ」を繰り返してゴールへと誘導する。ロボットの動きをイメージできるかどうか、プログラミング的な思考力が試されるが、サイコロを振った分しか進めないため思いどおりに動いてくれないことも。
[ 実際にプレーしてみた!]
複数のマップがあり、地形に応じて有効なプログラムはガラリと変わるので、「これが強い」という絶対的な設定はない。適材適所を見極める柔軟な思考力も鍛えられそう。
子供と一緒に全国各地の名所、名産を学ぶ
『るるぶ 線路でつながる!都道府県カードゲーム』2200円
ゲームで遊びながら、都道府県や鉄道、特産品などの知識を身につけることができる。ボードを使った「日本一周のりものノリノリ・ツアー!すごろく」のほか「都道府県ものしりポーカー」、「順位で勝ち抜けゲーム」など6種類の遊び方があり、子供の成長に合わせて、飽きずに何度でも遊べる。
[ 実際にプレーしてみた!]
ゲームのひとつ「都道府県カードゲーム」は「7ならべ」にルールが似ているなど、ボドゲ初心者でも入りやすい。カードに書かれた特産品情報は、大人のほうが楽しめそう。
全世界3000万部のベストセラーがボドゲになった
『7つの秘宝』9680円
RPGを題材にしたゲームで、2人もしくは4人でプレーする。すごろくのようにサイコロを振ってマップ上の様々なイベントをこなし、装備やアイテムを蓄えてから、6体の中ボスと魔王を倒す。ターン数(自分の手番が来る数)には上限が設けられているので、プレーヤー同士で協力しないとクリアが間に合わない仕組みになっている。
[ 実際にプレーしてみた!]
プレーヤー間で協力しないと戦力は魔王に到底及ばない。こんなにプレーヤー同士で議論するゲームはあまりないかも。本を読んだことがない人でも楽しめる構成になっている。
取材・文/編集部
※本記事内に記載されている商品やサービスの価格は2021年12月20日時点のもので変更になる場合があります。ご了承ください。
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE















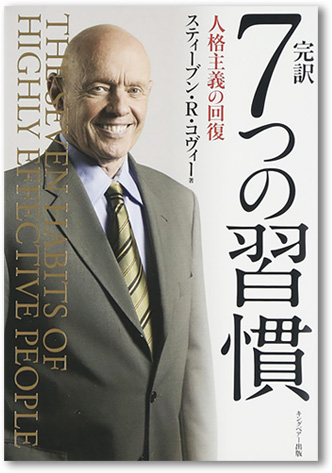

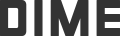 最新号
最新号






