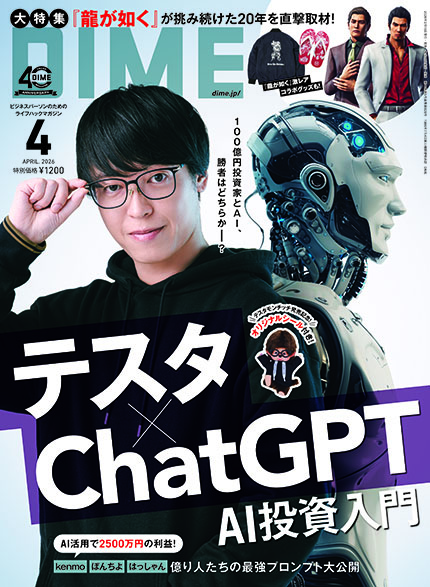気温差の激しい秋、そしてもうすぐくる真冬。疲れや倦怠感を感じているなら要注意。強い身体を作るために対策を取っておきたい。
その強い身体作りの方法の一つが、近年、研究者たちの間でも注目を集める、細胞のエネルギーを作り出す「ミトコンドリア」を増やすこと。
大阪大学大学院 生命機能研究科ミトコンドリア動態学研究室 准教授、岡本浩二氏の解説により、ミトコンドリアの数を増やし、質を高める方法を紹介する。また、管理栄養士監修の秋バテレシピも合わせて見ていこう。
秋疲れ・冬の寒さが近づく今、身体を元気にする鍵をにぎるミトコンドリア
冬の寒さにも負けない体をつくるには、自分の体内のミトコンドリアの数を増やすことが重要だという。ミトコンドリアは、体内でどんな働きをしているのだろうか?
【取材協力】
岡本浩二(おかもと・こうじ)氏
大阪大学大学院 生命機能研究科ミトコンドリア動態学研究室 准教授
1995年広島大学理学研究科生物学科専攻・博士課程修了。理学博士。1995年東北大学、1996年テキサス大学サウスウェスタンメディカルセンター、1999年ミュンヘン大学、2002年ユタ大学、2006年基礎生物学研究所、2009年東京工業大学を経て、2010年より大阪大学大学院生命機能研究科ミトコンドリア動態学研究室、特任准教授、2015年7月より准教授。
「人間の体にある一つ一つの細胞の中には、核や小器官がありますが、その1つにミトコンドリアがあります。ミトコンドリアは、細胞のエネルギーをつくる大変重要な役割を担っています。エネルギーが不足すると細胞に元気がなくなり、体全体の疲労感や倦怠感につながります」
「ヒトの細胞も機械と似ているところがあり、エネルギーによって動きます。電気でいえば、液化天然ガス、石油、石炭を燃やして火力発電によって電気を得るように、人間の体の中では、食べ物から吸収された糖、脂質、タンパク質から、酸素を利用して『ATP』という物質を合成して細胞のエネルギーをつくっています。
ミトコンドリアは、細胞の発電所に例えられます。発電所がうまく稼働していればエネルギーが十分につくられ、不足すると細胞のすべての活動に影響します」
●ATPの使い道
1.細胞増殖
2.DNA 、RNA、タンパク質などの合成
3.熱の発生
4.運動
5.神経活動
6.物質の吸収と排出
7.細胞や細胞小器官などの修復
8.その他、すべての活動
「ATPは貯金をすることができません。常にミトコンドリアで作り続けなければならないのです。発電所であるミトコンドリアが停止したら、人間は3分しか生きられないことがわかっています」
今注目されるミトコンドリアと免疫との深い関係
近年、ミトコンドリアが免疫と深い関係があることが明らかになり、研究者達のホットな研究対象となっているという。
「免疫システムには、生まれつき体に備わっている自然免疫と、後天的に作り出される獲得免疫があります。最初に自然免疫系が働き、次に獲得免疫が働きます。ミトコンドリアは、自然免疫ではウイルスの感知や司令塔の役割を担い、獲得免疫ではT細胞やB細胞といった免疫細胞の分化に関わり、抗体産生につながっています」
現代人の生活はミトコンドリア不足になりがち
そこで岡本氏は、「疲労感や倦怠感だけでなく、免疫低下を予防するためにも、ミトコンドリアの数を増やし、質を高めることが大切」だと述べる。
しかし、現代人の生活はミトコンドリア不足になりがちだという。
「現代人の課題である運動不足、過労、心的ストレス、不規則な生活、過食・偏食、睡眠不足は、ミトコンドリア不足を招くことがわかっています」
さらに、ミトコンドリアは年齢とともに数が減るという。
「ミトコンドリアの数の減少は10代から始まり、年齢と共に大きく下降していきます。さらに、ヒトの細胞で調べた研究では、ミトコンドリアの活性も年齢と共に低下していることがわかりました。ミトコンドリア呼吸酵素の活性は年齢とともに直線的に下降し、50歳では、生まれたときに比べて半減することがわかっています」
ミトコンドリアの数を増やし、質を高めよう
岡本氏によれば、年齢と共にミトコンドリアの数は少なくなるが、高齢になってからでも増やすことができるという。どんな方法で増やせるのだろうか?
岡本氏は次の4つを挙げる。
●ミトコンドリアを増やす方法
1.適度な負荷の運動
2.バランスの取れた食事
3.プチ断食
4.還元型 Co10 不足を避ける
「質の良いミトコンドリアを増やす方法は、適度な負荷がかかる運動、バランスの取れた食事、プチ断食です。
あくまでマウス実験での知見ですが、適度な負荷の運動やプチ断食で、ミトコンドリアを増やすのに必要なタンパク質・脂質・核酸などの遺伝子発現が上昇することがわかっています。
適度な負荷の運動の一例として、『中腰でのスクワット10回』をインターバルを入れつつ、3セットなどでも、ある程度の効果が期待できます。プチ断食は、一例として週1-2回、朝食・昼食・夕食のいずれか一つをパスする、などでもよいといわれています。運動もプチ断食も、ある程度の個人差があるかもしれませんので、自分に合ったレベルを見つけることが大切だろうと思われます。
食事では、還元型CoQ10(コエンザイムキューテン)の不足に気をつけましょう。
この秋、さらにその先も元気に過ごすために、質の良いミトコンドリアを増やしていきましょう」
●還元型CoQ10とは
「還元型CoQ10は、すべての細胞に存在する脂溶性のビタミンのように働く物質です。もともと細胞内に存在する物質ですが、不足するとミトコンドリアでエネルギーをつくる能力が低下します。
また、還元型CoQ10は抗酸化物質としても働くことがわかっており、ミトコンドリアから発生した活性酸素を除去する働きがあります。
還元型CoQ10が不足すると、この2つの働きをスムースに行うことができなくなり、ミトコンドリアの数と質の低下につながります」
また、栄養バランスのとれた食事は、ミトコンドリアの質と高め数を増やすという。さらに、CoQ10が多く含まれる食品を積極的に摂るのがいいそうだ。
●CoQ10が多く含まれる食品
牛モモ、牛カタ、牛レバー、豚カタ、鶏心臓、ハマチ、ブリ、ツナ缶、アボカド、白菜、納豆、いりごま、カリフラワー
手軽にできるミトコンドリア対策レシピ
疲労感や倦怠感を感じているなら、ぜひ意識したいミトコンドリアの数を増やすこと。そこで、管理栄養士の京須 薫氏が考案した、ミトコンドリア対策におすすめのCoQ10が多く含まれる食品を使ったレシピを2つ紹介する。
【レシピ考案】
管理栄養士 京須 薫氏
フィットネスクラブでダイエットプログラム開発、広報誌へのレシピ、食の情報紹介などに携わる。その後は自治体や企業での健康教室講師や乳幼児の離乳食から中高年の特定保健指導(メタボ予防・改善)まで幅広く活動。 特定保健指導では500名以上の相談に携わる.現在は、東京都八王子市で「おそうざい・おべんとう ユタカ」を経営。著書に『サプリのように摂りたい!コエンザイムQ10レシピ』(河出書房新社、株式会社ティップネスと共著)。
●「ブリのおろし煮」
【材料】(2人分)
・ブリ 2切れ【1人分CoQ10:1.3mg】(ゲンキ還元プロジェクト調べ)
・下味用(塩 ふたつまみ、酒 小さじ1)
・大根 4cm(100g)
・しめじ 1/4パック(25g)
・A(酒 大さじ2、みりん・しょうゆ 各大さじ1)
・油 大さじ1
・片栗粉 適量
・大根の葉 適量
【作り方】
1.ブリは下味用の塩と酒をふり、10分程度おく。大根は皮をむいてすりおろし、おろし汁もとっておく。しめじは石づきを取りのぞいて小房に分ける。大根の葉は小口切りにして塩(分量外)をふり、耐熱容器に入れ、ふんわりとラップをかける。電子レンジで約1分加熱する。
2.フライパンに油を熱し、水気を拭き取って片栗粉をまぶしたブリを入れ、中火で両面こんがりと焼く。キッチンペーパーにとり、余分な油を切る。
3.鍋にAとしめじ、大根おろしをおろし汁ごと入れて、火にかける。煮立ったらブリを加えて、5分ほど煮る。器に盛り付けて水気を切った大根の葉を散らす。
●「牛肉とピーマンのオイスターソース炒め」
【材料】(2人分)
・牛かた薄切り肉 120g【1人分CoQ10 2.4mg】(ゲンキ還元プロジェクト調べ)
・パプリカ(赤) 1/2個(60g)
・カラーピーマン(赤、オレンジ) 1個(30g)
・たまねぎ 1/4個(50g)
・油 小さじ2
・A(酒 大さじ1、オイスターソース 大さじ1/2、しょうゆ 小さじ1、
・にんにく(すりおろし) 少々
・塩、こしょう 少々
・塩 ふたつまみ
【作り方】
1.ピーマン、カラーピーマンはヘタと種を取って細切りに、たまねぎはくし切りにする。牛肉は食べやすい大きさに切り、塩、こしょうを振る。Aの材料を混ぜ合わせておく。
2.フライパンに油(小さじ1)を熱し、1の牛肉を入れ、ほぐしながら色が変わるまで炒め、いったん取り出す。
3.キッチンペーパーでフライパンをふきとり、残りの油(小さじ1)を熱する。たまねぎを入れて炒め、透き通ってきたら、ピーマン、カラーピーマンを加える。油が回ったら牛肉を戻す。さらにAを加えて全体にからめ、塩、こしょうで味をととのえる。
これからの季節に向けて元気な身体を作り、仕事や生活でパワフルに活動しよう。
取材・文/石原亜香利















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE